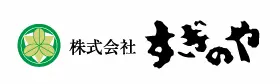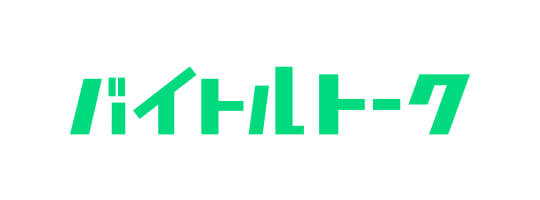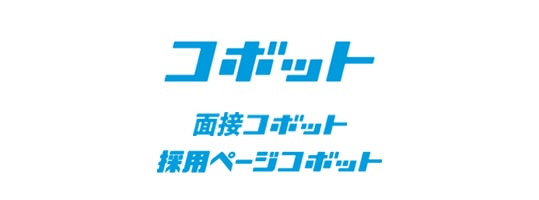株式会社すぎのや様は1971年創業、和食レストラン「すぎのや本陣」を運営。現在、茨城県を中心に31店舗展開しています。dipサービスの本格的な利用は2022年10月から。新型コロナの影響で求人費が縮小し、取引先を厳選した結果dipを選んでいただきました。今回お話を伺った人事総務本部長の與座様には、dipを選んだ決め手やdipサービスの活用方法だけでなく、ツール導入に対する考え方や採用・人事戦略のコンセプトなど幅広い話題をお話しいただきました。
- 課題
- すぎのやの「人事課」を任せられるパートナー探し
- 採用支援にとどまらず各店舗のweb移行支援やツール研修など、すぎのや様の「人事課」的な役割を担えるパートナーを探していた。
- 結果
- 各店舗の採用支援、店舗・本社の業務効率化に成功
- すぎのや様がかかえる課題を丁寧にヒアリングし最適なサービスを提案した結果、「信頼に足る会社」と認めていただき、採用支援や業務効率化に成功。
「人事課」を任せられるパートナー。辛抱強さが信頼につながった

「バイトル」導入にいたった背景・課題を教えてください。
株式会社すぎのや 経営改革・社長室 経営企画・システム統括・人事総務担当 人事総務本部長 與座 清様(以下・與座様):まず現状のアルバイト採用は各店舗でおこなっており、原稿の作成や掲載/停止も各店舗が管理しています。我々の役目は各店舗の採用がうまくいくように媒体を選定したりツールを導入したりといったバックアップ業務になります。
新型コロナの影響で求人費を縮小せざるを得なくなったわけですが、各店舗が求めていたのはコストのかかる紙媒体。紙媒体は効果が見えにくいというデメリットもあったため、Web媒体への移行が大きな課題でした。もうひとつの課題は求人に関する取引の集約。以前は各店舗の判断で媒体を選んでいましたので、ある店舗ではA社の媒体を使い、隣の店舗ではB社と取引という状況が当たり前でした。そのため、当時管理している口座は70以上にものぼっていたんです。
dipを選んだ決め手は何だったのでしょうか。
與座様:私自身がさまざまなジャンルの業務を兼務していたので、できれば当社の人事課もしくは採用課の役割を担ってもらえるような会社を探していました。パートナー会社を探すなかで、当社の状況や課題はすべての会社にお話ししました。しかし、多くの会社は「こういうことができます、こういう商品があります」と自分たちのことをアピールするばかりで、当社の課題にマッチしているとは感じなかったんです。そのなかでdipさんは当社の状況を丁寧にヒアリングしたうえで適切な提案をタイムリーにしてくれました。
dipさんの話を詳しく聞きたいと思っていましたが、どうしても求人費に予算を割けませんでした。そのため、「月に一回は連絡して状況を確認してほしい」と当時のdip担当にお願いしました。それから毎月忘れることなく電話をくれたんです。dipさんからしたら本当に大変だったと思いますが、オーダーがないのをわかっていてもきちんと連絡し続けてくれたので、信頼に足る会社だと感じ「dipさんにお任せしよう」と決めました。
辛抱強く待ち続けたことでdipが信頼を勝ち取ったのですね。
與座様:そうですね。加えて、採用業界の知見もしっかり持ち合わせていて、我々を「なるほど」と思わせてくれることも多かったですね。我々もさまざまな情報収集や検証をおこなっているのですが、採用業界は半年から1年で状況がどんどん変わっていきます。5年前のトレンドをいまでも追いかけている会社があるなか、dipさんは最新の市場動向を冷静に分析しているなと感じていました。そのうえで適切な提案をしてくれた。しかもタイムリーなタイミングで。dipさんは当社のために、実際に手を動かしてくれた数少ない会社のひとつでしたね。
店舗が自走するためには道具の「遊び方」まで教える
「バイトル」を導入したことでどのような効果がありましたか。
與座様:多くの店舗で採用実績が出たことも大きな効果ですが、それ以上に求人掲載の効果が可視化されたことが重要だと思っています。応募数や面談設定率、採用率といった数値だけでなく、メールのやり取りなど採用の過程までわかりますので店舗ごとに最適な軌道修正ができる。これは紙媒体ではなかなかできないと思います。
原稿の中身に関しては完全にdipさんにお任せしているのですが、感心したのが各店舗としっかり連携をとりながら原稿を作っていた点です。よくある「成功事例」が我々にも当てはまるかはわからないじゃないですか。dipさんはパターンにあてはめようとせず、1店舗1店舗と丁寧にコミュニケーションしていたからこそうまくいったのだと思います。驚いたのが、我々の原稿を読んだ他社の営業さんが「あの原稿は誰が作っているんですか」と聞いてきたことです。他社が参考にするくらいきめ細かく作ってくれてとても助かりましたね。
「すぎのや本陣」にはパソコンやスマホ操作に慣れない店長が多かったと聞きます。「面接コボットforアルバイト」の導入はどのように進めたのですか。
與座様:そうですね。Webへの移行や業務効率化を進めるうえで、パソコンやスマホの不慣れな店長が多いのは課題でした。ただ、これもdipさんが店長を集めてオンラインで「面接コボットforアルバイト」の使い方をレクチャーしてくれたんです。「これを使うとこれだけ便利になる」「応募者にとってもメリットがある」といったポイントは、一般論としてそうなのですが、私からも伝えるよりも、大きな功績を残しているdipさんから言ってもらったほうが説得力はありましたね。
「バイトル」も「面接コボットforアルバイト」も、とても丁寧に導入を進めていった印象を持ちました。媒体やツール導入で意識したことはありますか。
與座様:我々は各店舗の採用ができない代わりに、採用しやすくなる環境を整えるのが仕事。ただし、私は「道具を与えさえすればどうにかなる」とは思ってないんですよ。道具を用意するのは本社なんだけども、その使い方、言い換えると「遊び方」まで教えることが欠かせないと思っています。「遊び方」というのは、ある決まった手順だけを覚えることではなく、状況にあわせて使い方を工夫できること。店舗がツールを使いこなして自走していくには「遊び」が重要だと思っています。
オリジナルの成功体験を求めて 従業員のセンス見出す採用を

與座様は現在、すぎのやの企業戦略のコンセプト策定を進めているそうですね。これまでの質問から視野を広げ、組織作りに対してお考えのことはありますか。
與座様:私が思うに、会社という存在はレースで1位をとるために戦っているわけではないんです。スポーツの世界では順位を競ってみんなが1位を狙いにいきますが、会社はそうではない。つまり、1位を目指すのではなく「選ばれる」ことに意味があるんです。うまくいっている会社の取り組みを真似することが一般的かもしれませんが、私はそれを打破したい。外食産業で高いシェアを獲得しているゼンショーホールディングスさんやマクドナルドさんの成功体験を、当社がそのまま真似すれば売上があがるかというと、そうとは限りませんよね。もしかしたら、まったく違う業界の成功体験を取り込んだほうが良い可能性もある。そしてこの先には、会社ごとに異なる「オリジナルの成功体験」を作ることが、お客様から選ばれるために不可欠だと思うんです。
レースで1位をとるためではなく「選ばれる」ためにオリジナルの成功体験が重要、と。選ばれる組織作りには、どのような採用・人事が求められるのでしょうか。
與座様:一言でいえば、センスを持つ人を採用しセンスが磨かれる環境を作ることだと思います。その人だけが持つ感覚をいかにして見出すか。従業員向けのコンテストっていろんな会社が実施しているじゃないですか。スキルや技術の共有も大事だと思いますが、私としてはロールモデルとしてパターン化するのは少し違和感があるんです。「店長はこうあるべきだ」とかね。というのも、スキルや技術はいずれコモディティ化するはずなんです。しかし、その人しか持ちえないセンスは自分で磨くしかないだけに、ほかの誰にも真似できない。
私が好きな言葉に「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず」(孔子『論語』より)があります。これは「物事を理解し知っている者は、それを好きな人には及ばない。物事が好きな人は、それを心から楽しんでいる者には及ばない」といった意味になりますが、この「それを心から楽しんでいる者」こそが、センスを持った人です。この人たちにスポットライトを浴びせる、小さな成功体験を積み上げさせるのが会社の役割だと思うんです。
最後に、すぎのや様の今後の展望を教えてください。
與座様:まだ公表できない情報もありますが、会社としては「新生すぎのや」という言葉を使っていろいろと動いている段階です。今後の採用や人事に関しては、センスのある人に活躍してもらうことも重要でありながら、従業員が納得感、センスメイキングを持って仕事できる環境作りも同じように大事です。
別の言い方をするとモチベーションですね。従業員のモチベーションには「意義があるかどうか」「楽しいかどうか」の2つが欠かせないと思っています。意義というのはたとえば、ざるそばを一万杯売ると途上国に学校が建つといった社会貢献。「楽しい」というのは、どんな楽しさでもいいと思うんです。この職場に来ると何か元気もらえるとか、孫ぐらいの世代と一緒に仕事ができるとか。「恋人を見つける」という動機だっていい。とにかく楽しさが見つかる職場を作っていきたい。楽しくなければ仕事じゃない(笑)
すごくいろいろなことを話しましたが、dipさんの話に戻すと、今後dipさんには各店舗ともっと密接な存在になってもらいたいと思っています。それから、「バイトル」や「面接コボットforアルバイト」などいろいろな道具を入れたので、これらをもっと有効活用していきたいなと。dipさんとは良いときも悪いときも付き合っていきたい。私はそう思っています。