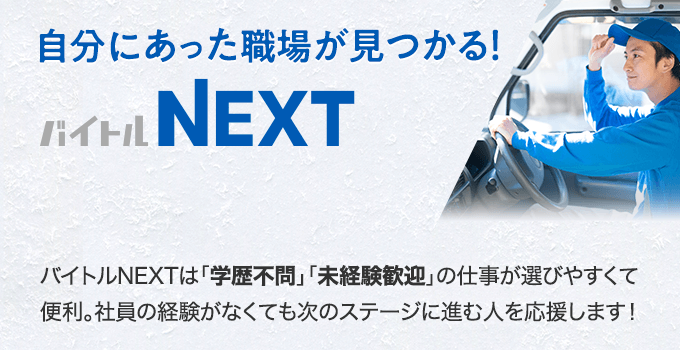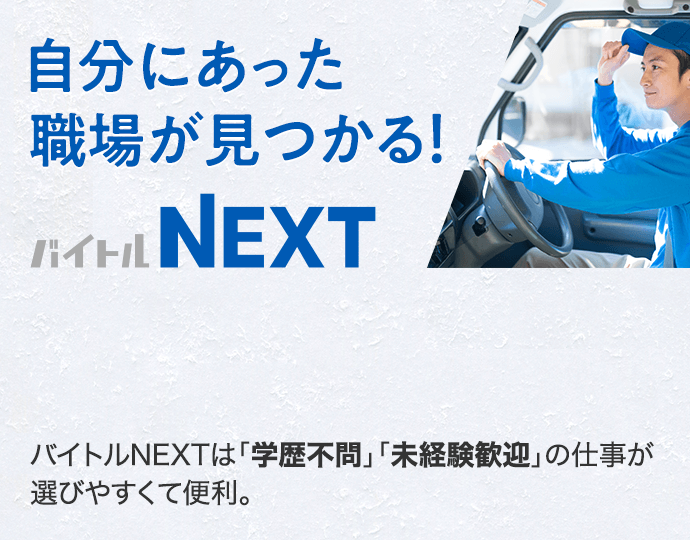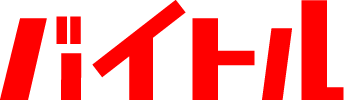タクシー運転手に必要な二種免許取得は難しい?費用・合格率を徹底解説

タクシー運転手になるには「二種免許」の資格取得が必要です。ドライバー未経験の方や二種免許の取得を検討している方は、試験でどのような問題が出るのか、合格率はどれくらいなのかが気になりますよね。
この記事では、二種免許取得の方法とそれにかかる費用・時間、そして試験の内容について解説します。なるべく費用をかけずに取得できるタクシー会社の「二種免許取得支援制度」についてもご紹介するのでぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
-
タクシー運転手になるには二種免許の取得が必須
-
「二種免許」は、運転する車両の大きさによって以下の5種類に分けられます。
- 普通自動車第二種免許
- 中型自動車第二種免許
- 大型自動車第二種免許
- 大型特殊自動車第二種免許
- けん引第二種免許
このなかで、タクシー運転手になるのに必要な免許は「普通自動車第二種免許」です。
ここでは「一種免許」と「二種免許」の違い、そして「普通自動車第二種免許」の試験を受ける条件について解説します。二種免許を持っていると「お客さまを乗せて運転できる」
一種免許 - ・日本の公道で自動車および原動機付自転車を運転するための免許
- ・日々の通勤や外出で運転するのに必要(対価は発生しない)
二種免許 - ・タクシー・バス・ハイヤーなど旅客自動車を運転するための免許
- ・営利目的でお客さまを乗せて運転するのに必要(対価が発生する)
「二種免許」はタクシー運転手やバス運転手など、お客さまを自動車に乗せて目的地まで送迎することを仕事にする場合に取得が必須になります。
二種免許試験の受験条件をチェック
二種免許の試験を受けるには、いくつかの条件をクリアしている必要があります。タクシー運転手になるために二種免許の取得を検討している方は、自分が受験条件に当てはまっているかチェックしてみてください。
■受験資格
- 年齢が満21歳以上であること
- 大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、取得から通算3年以上経過していること
※参考:受験資格(警視庁)
■適性検査の合格基準
視力 - 両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること
- ※眼鏡やコンタクトレンズで矯正可能
深視力 - 三棹(さんかん)法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること
色彩識別能力 - 赤色、青色及び黄色の識別ができること
聴力 - 両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること
※補聴器の使用が可能
※参考:適性検査の合格基準(警視庁)
「深視力」とは、立体的に物を見る能力のことです。タクシー運転手は「運転のプロ」として物体の位置や速度を素早く認識し、状況に応じて適切な運転ができることを求められます。
受験資格特例教習を受ければ19歳から受験が可能になる
2022年5月に「二種免許」の受験資格の見直しが実施され、特例として「年齢要件」と運転の「経験年数要件」がそれぞれ引き下げられました。
受験資格 年齢要件 経験年数要件 通常 21歳以上 大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許取得から通算3年以上 特例 19歳以上 大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許取得から通算1年以上 また、この特例を受けるには「年齢要件」「経験年数要件」のそれぞれに対して以下の追加教習を受講する必要があります。
■「年齢要件」の特例を受ける条件
旅客自動車等の運転に必要な適性(自己制御能力)に関して、座学や実車を含む7時限以上の教習を受ける。
■「経験年数要件」の特例を受ける条件
旅客自動車等の運転に必要な技能(危険予測・回避能力)に関して、座学や実車を含む29時限以上の教習を受ける。
「年齢要件」に関する特例を受けて「二種免許」を取得した場合、本来の資格要件である21歳になるまでの間は「若者運転者期間」となります。
※参考:第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)
-
二種免許試験の合格率と出題される問題の傾向
-
二種免許を取得するには「学科試験」と「実技試験」に合格する必要があります。それぞれの試験内容と気になる合格率について解説するので、初めて二種免許の試験を受ける方は参考にしてくださいね。
二種免許試験の合格率は54%!
令和4年の「運転免許統計」によると「普通自動車第二種免許」の合格率は54.1%です。一般的な自家用車を運転するのに必要な「普通自動車第一種免許」の合格率は74.5%なので、それと比べると二種免許の取得は難易度が高くなります。
お客さまの命を預かり送迎する「運転のプロ」にふさわしい知識と運転技術があるかを見られる二種免許の詳しい試験内容を見ていきましょう。
※参考:運転免許統計 令和4年学科試験|一種免許より応用問題が多め
- 問題数:全95問(文章問題90問・イラスト問題5問)
- 回答形式:全問マークシート(文章1問1点・イラスト1問2点)
- 採点方式:減点法
- 合格基準:100点満点の90点以上で合格
基本的には一種免許の学科試験と同じように常識問題や交通ルールに関する問題が出題されます。全95問のうち5~10問だけ旅客輸送に関する二種免許特有の問題が出題されるので、とくにその点をよく勉強しておくといいでしょう。
教習所に通って免許を取得する場合は、学科教習でひとつずつ講師の解説を聞きながら学習できます。教習所に通わず独学で勉強して免許取得を目指す「一発試験」を検討している方は、書籍の問題集やスマホアプリ、ネットの例題集で勉強するのがおすすめです。実技試験|運転のプロになるために厳しく採点
- 試験:教習所の場内試験と路上試験を受ける
- 合格基準:両方の試験とも90点以上(各項目から減点法)
※一種免許の合格基準は80点以上
二種免許の実技試験の合格基準は一種免許よりも高めに設定されており、より厳しく採点されます。
お客さまの安全を確保するために危険の少ない運転行動を適切に選択できるか、そして万が一危険な場面に遭遇した場合に、それを回避できる高度な危険回避能力があるかを主に判断されます。▼主な実技試験の内容
場内試験 - ・S字型の鋭角コースやV字コースの切り返し
- ・縦列駐車または方向転換
- ・障害物設置場所の通過
路上試験 - ・路端への停車及び発進
- ・転回(進んでいた方向と逆に進行するための方向転換)
路上試験の「路端への停車及び発進」では、実際にお客さまからの停止要請があった想定で行われます。停止禁止場所を理解しているか、正しい位置に停車できるかなどを見られます。
合格したら取得時講習を受ける
学科試験と2種類の実技試験に合格したら二種免許を取得できますが、合格したあとに「応急救護処置講習」と「旅客者講習」2種類の講習を受ける必要があります。
旅客の安全確保のために必要な対応をするために必要な知識を6時間前後の講習で学びます。
-
二種免許の資格取得方法とかかる費用と期間
-
二種免許の取得方法は以下の2パターンです。
- 教習所で取得する(通い/合宿)
- 一発試験で取得する
それぞれ取得にかかる費用の目安や期間、試験合格の難易度が変わるので、自分に合った方法を選びましょう。
取得方法①教習所に通って取得
教習所で二種免許を取得する場合、「通い」で少しずつ教習を受講する方法と「合宿」でまとまった期間で教習を受講する方法があります。
取得までの日数(目安) 取得にかかる費用(目安) 通い 約20日で教習所卒業
+本免の学科試験(1日)22万円前後~
+手数料 3,750円合宿 8~10日で教習所卒業
+本免の学科試験(1日)19万円前後~
+手数料 3,750円※取得にかかる費用の目安は入校の時期や教習所の地域によって差があります。
※手数料とは、本免の学科試験受験料1,700円・免許証交付料2,050円です。取得にかかる費用はどちらでも大きな差はありませんが、短期間で二種免許の取得を目指したい方は「合宿」がおすすめです。
また、教習所を選ぶ際は公安委員会(警察)から指定を受けた「指定自動車教習所」をチェックしてみてください。「指定自動車教習所」を卒業すると技能試験が免除され、適性試験と学科試験に合格するだけで運転免許の取得が可能なのがメリット。
全日本指定自動車教習所協会連合会によると、新規に免許を取る人の97%は「指定自動車教習所」の卒業生なので、初めて二種免許の取得を検討している方は「指定自動車教習所」でしっかり教習を受けたうえで試験に臨むのがよいでしょう。▼二種免許取得までの流れ(指定自動車教習所の場合)
STEP.1 適性検査 STEP.2 学科教習1の受講 STEP.3 学科教習・技能教習第1段階の受講(基礎知識) STEP.4 仮運転免許学科試験・仮運転免許技能検定の受験 STEP.5 学科教習・技能教習第2段階の受講(専門知識) STEP.6 卒業検定(路上技能)の受験 STEP.7 住所地の公安委員会で学科試験の受験 STEP.8 普通自動車第二種免許取得 取得方法②運転試験場で一発試験
二種免許は教習所に通わなくても直接免許試験場に行って試験を受ける「一発試験」で取得できます。
取得までの日数(目安) 取得にかかる費用(目安) 一発試験 約20時間
(学科試験約1時間・本免許試験約3時間・取得時講習16時間)36,700円
(受験料4,800円・試験車使用料2,850円、免許証交付料2,050円・取得時講習受講料27,000円)※1回の試験で合格した場合の日数・費用の目安です。
一発で合格できれば二種免許取得までの時間と費用を教習所に通うよりも大きく抑えられますが、自力で一発合格するのは難しく、合格率は10%以下とも言われています。
再受験するたびに費用がかかるため、初めて二種免許の試験を受ける方にはあまり向かない方法です。
また、学科試験は平日毎日実施していますが、技能試験は月に数回しか実施していません。学科試験に合格してから本免許試験を受けるまでに時間が空いてしまう場合があるので注意が必要です。
-
資格取得費免除も!二種免許資格取得支援制度を活用しよう
-
タクシー会社に入社してから二種免許を取得できる
多くのタクシー会社では、人手不足を解消するためにドライバー未経験者を採用する動きが積極的に進められています。
二種免許を取得していなくても「普通自動車第一種免許」があれば入社可能で、入社後に二種免許を取得する費用の負担や試験合格に向けた講習を実施する「二種免許資格取得制度」を導入している企業もあります。
ドライバー未経験で、これから二種免許の取得を目指す方は、まず「二種免許資格取得制度」を実施しているタクシー会社を探し、求人に応募してみるのがおすすめです。二種免許資格取得制度のメリット
-
二種免許を取得すればさまざまなドライバーにチャレンジできる
-
二種免許を取得することで、ドライバーとしてのキャリアの幅が大きく広がります。「タクシー運転手」と一口に言っても、一般的な「流し営業」を行うタクシー以外にもさまざまなニーズに応じたタクシーを運転することができるようになります。
▼特殊なタクシーの事例
観光タクシー 日本の観光客や外国人観光客に各地の観光スポットを案内する 妊婦応援タクシー 事前登録した妊婦のお客さまを病院まで送迎する 育児支援タクシー チャイルドシート・ジュニアシートを備え、子どもを送迎する 介護タクシー 介護保険の要介護者の方の送迎と乗降介助をサポートする 福祉タクシー 1人で外出が難しい方の外出移動をサポートする 上記で解説したような特殊なタクシーのほかにも、ワンランク上の接客スキルが求められる「ハイヤー」の運転手を目指すこともできますよ。
二種免許を取得することでさまざまなタクシーを運転できるチャンスが増えるので、運転が好きな方や接客を伴う仕事をしてみたい方にとっては楽しい仕事です。
また、タクシー運転手と同様にお客さまへの対応が発生するバス運転手は「大型二種免許」の取得が必要です。タクシー運転手に必要な「普通自動車第二種免許」よりも車両が大きい分難易度は上がりますが、タクシー運転手の経験を活かし次のステップとして転職を考えることもできるでしょう。
-
まとめ
-
二種免許の取得方法と、それにかかる費用・時間について解説しました。「二種免許取得支援制度」の内容はタクシー会社によって異なるので、よく確認したうえで入社するようにしてくださいね。
<タクシー運転手の関連記事>
【タクシー運転手の全貌】仕事内容・資格・適性・収入を徹底解説!
タクシー運転手はきついと言われる理由!6つのイメージの実態を解説
タクシー運転手になるには?ドライバーデビューまでの流れをご紹介
こんな人はタクシー運転手に向いている!適性や必要なスキル・魅力をご紹介
タクシー運転手は未経験でもなれる?働きやすいタクシー会社の選び方を解説
【ニーズ上昇中】福祉タクシー運転手になるには?向いている人・やりがいを解説
タクシー運転手の年収は高い?ほかのドライバーとの給与差や稼ぐコツを解説
<バス運転手の関連記事>
バス運転手の年収は高い?路線バスや観光バスなどの給料の傾向と稼ぐコツをご紹介
<トラック運転手の関連記事>
トラック運転手の仕事内容とは?トラックの種類や用途・運送業の仕事の流れを解説
トラック運転手はきつい?イメージと実態のギャップを徹底調査!
大型トラック運転手の仕事内容を解説!トラックの種類ごとの用途も要チェック
大型トラック運転手はきつい?長距離ドライバーがきついと感じるポイント6選
職種 の関連記事
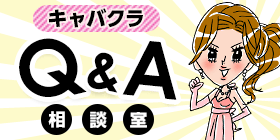
スナックとパブの違いは?|Q&A相談室|バイトル
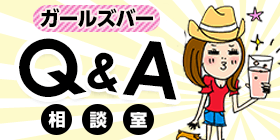
ガールズバーとキャバクラの違いは?|Q&A相談室|バイトル
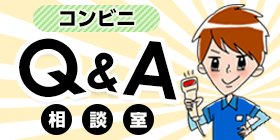
スーパーのグロッサリー部門って?|Q&A相談室|バイトル
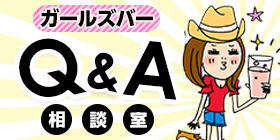
キャバクラとガールズバーの違いは?|Q&A相談室|高時給・高収入バイトならバイトル
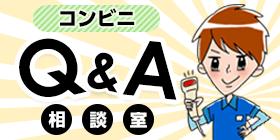
スーパーの日配部門って何を扱うの?|Q&A相談室|バイトル
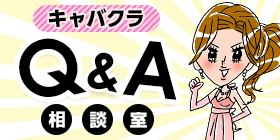
キャバクラでは同伴・アフターはしなきゃダメ?|Q&A相談室|バイトル
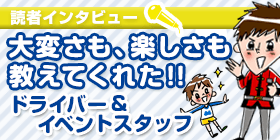
読者インタビュー:ドライバー・イベントスタッフ編

食品工場で正社員として働くのはきつい?仕事内容と向いている人を紹介!
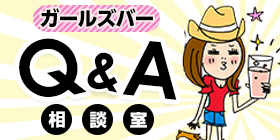
キャバクラ・ガールズバーの「エスコート」ってどんな仕事?|Q&A相談室|高時給・高収入バイトならバイトル
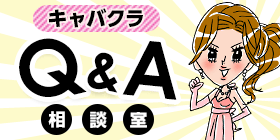
クラブとラウンジの違いは?|Q&A相談室|バイトル
カテゴリ一覧
-
派遣の仕事探し派遣の仕事探し
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書
- 自宅でできる仕事46選!スキルや趣味、得意分野を活かせる在宅ワークを見つけよう /バイト探し・パート探し
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート
- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!