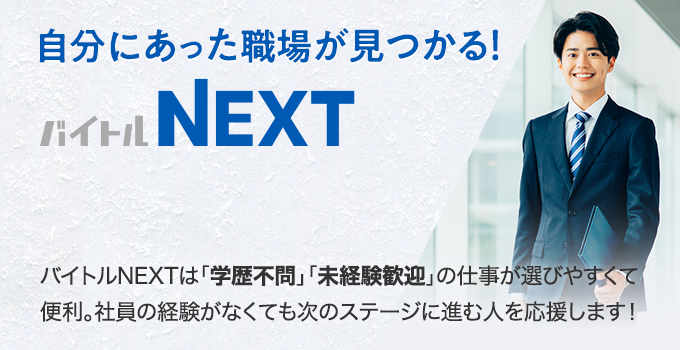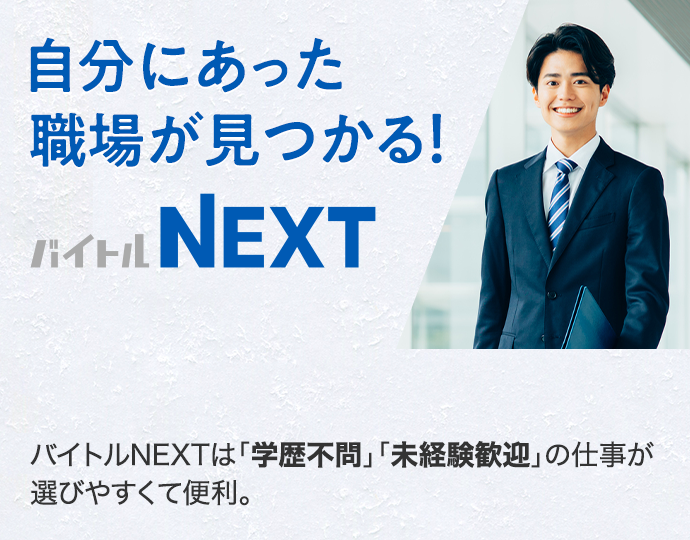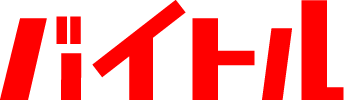【社労士監修】フリーターで保険証を持っていないリスクを解説!国民健康保険に入るには?
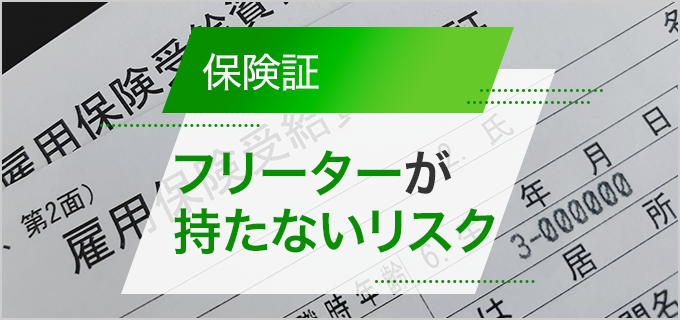
フリーターのなかには、保険証を持っていない方が一定数います。ある程度の額を稼いでいると、いつの間にか親の扶養を抜けてしまい、これまでの保険証が使えなくなっているケースなどが多いようです。
ただ、そのままにしておくとさまざまなデメリットがあり、最悪の場合は差し押さえなどのリスクも。そこでこの記事では、フリーターが保険証を持たないことによるリスクから、保険証を入手する方法まで解説します。
目次
-
フリーターが保険証を持っていないことのリスク
-
健康保険に加入していることを証明する保険証は、持っていないといろいろな不都合が生じます。ここでは、保険証を持っていない(健康保険料を支払っていない)とどのようなリスクがあるのかを解説します。
延滞金が発生する・差し押さえされる可能性がある
日本には国民皆保険制度があり、健康保険への加入は義務となっています。そのため、普段から保険証を使うかどうかに限らず、毎月の保険料は必ず支払わなくてはなりません。
健康保険料を未払いのままでいると、市町村から督促状が送付され、指定の期日までの支払を求められることがあります。期日までに保険料を支払わないと延滞金が科せられるため、速やかな納付が必要です。
さらに延滞が続くと、給与や預貯金、不動産などを差し押さえられる可能性もあります。通院・入院で高額な医療費がかかる
体調不良や怪我で病院を受診すると、窓口で健康保険証の提示を求められます。健康保険に加入している(保険料を納めている)場合、医療費の一定割合が保険からまかなわれるため、その証明書として保険証が必要になるのです。
医療機関は保険証を提示しなくても受診自体は可能です。しかしその場合は、かかった医療費の全額を窓口で支払うことになります。これは、日頃の通院はもちろん、大きな病気などによる入院も対象です。
もし保険証を持っていなければ、定期的な通院や入院が必要になったとき、金銭面で困ることになるかもしれません。身分証明書が準備できないことも
健康保険証は、本人確認が必要な手続きを行なう際などに、身分証明書として使われることがよくあります。銀行口座の開設やクレジットカード作成、賃貸契約のような、本人確認の重要度が高い手続きをはじめとして、生活のなかで身分証の提示を求められる機会は意外に多いものです。
多くの場合、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのものを提示しますが、これらを持っていない方もいるでしょう。その場合でも健康保険証があれば、身分証明が可能となるため便利です。実質的には誰でも持っているはずの保険証がないと、手続きが進まないことも多くあります。
-
フリーターが保険証を持つメリット
-

保険証を持っていると、いざというときに役立ちます。ここではフリーターが保険証を持つメリットについて解説します。
保険診療が3割負担で受けられる
保険証を持っていると、保険診療にかかる費用の一部が健康保険から支払われます。保険診療とは、通常の病気や怪我などに対する診療です。(美容目的の診療などは保険診療になりません)
医療機関の窓口に保険証を提示すると、実際にかかった金額から保険によりまかなわれる分を除いた金額が患者に請求されます。健康保険に加入して年間の保険料を支払う代わりに、通院・入院時の医療費の窓口支払いが軽くなり、いざというときに安心して医療を受けられる仕組みです。
窓口支払の負担割合は年齢によって変わりますが、小学校入学後から70歳までであれば3割です。つまり、実際には3,000円の診療代がかかるケースでは、病院で保険証を提示すれば、全体の3割にあたる900円の支払いで済むことになります。
怪我や病気によっては複数回の通院が必要になることもあり、保険証がなければ負担額はかなり大きくなってしまうでしょう。このような場合、経済的な事情から受診を諦める事態にもなりかねません。身分証になる
私たちは、生活のなかのさまざまな場面で「本人確認書類」を求められます。例えば以下のようなシーンでは、「ご本人であることを確認できる書類はありますか」と本人確認の書類を求められることがあります。
【本人確認書類が求められるシーンの例】
- 銀行口座の開設
- クレジットカードの作成
- 役所など行政機関での手続き
- 給付金や各種手当の受け取り
- 本人限定受取の郵便物の受け取り
- スマートフォン契約やプラン変更
- フリマアプリでの出品
- 古本の買取依頼
- マッチングアプリへの登録
- イベントなどへの入場
- レンタルショップやジムなどの会員制施設での会員登録
健康保険証は身分証としてもよく使われる公的な書類です。身分証の提示を求められた際に、保険証であれば受け付けてもらえることも多いでしょう。特に、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を持っていない方は、保険証が有用です。
-
フリーターが保険証を入手する方法
-
フリーターが保険証を入手するには、大きく分けて4つの方法があります。
親の扶養に入る
親が社会保険(勤め先を通じて加入する健康保険)に加入している場合、親の扶養に入ることで保険証を入手できます。扶養とは、親族から経済的に援助を受けることです。
例えば、子供が生まれると、一般的にその子は親の扶養に入ります。親(扶養者)が健康保険に入っていれば、子供(被扶養者)は自分の保険料を支払うことなく、親が加入している健康保険を利用できる仕組みです。
ただし、フリーターが親の扶養に入ろうとする場合、実際に経済的に親に頼っているという事実がないと認められません。具体的には、以下のような条件が定められています。【原則】
- 被扶養者の年間収入が130万円未満
【同居/別居による追加条件】
- 同居している場合:被扶養者の年間収入が扶養者の年間収入の2分の1未満
- 別居している場合:被扶養者の年間収入が扶養者からの仕送り額未満
保険証を持っていないフリーターの多くは、もともとは親の扶養に入っていたものの、稼いでいるうちに上記の条件に当てはまらなくなってしまい、扶養から外れてしまったと考えられます。再び親の扶養に入る場合は、条件を満たすように収入などを調整しましょう。
国民健康保険の加入手続きを行なう
親の扶養に入るのが難しい場合、国民健康保険に加入して保険証を交付してもらいましょう。加入はお住まいの市区町村窓口で行なえます。手続きの詳細は後述します。
バイト先の社会保険に加入する
アルバイト先で社会保険に入れる場合は、国民健康保険の代わりにそちらに加入することでも保険証を持つことが可能です。フリーターがアルバイト先の社会保険に入れるかは、所定の労働時間などの条件を満たしているかに加え、勤め先の従業員数などによって決まります。
社会保険は、保険料の半分を事業主が負担することが義務づけられているため、国民健康保険よりも負担する保険料を抑えやすい点が大きなメリットです。また、怪我や病気で働けない場合に条件を満たせば支給される「傷病手当金」などは、国民健康保険にはない保障内容です。正社員として就職する
アルバイトとして働く場合、所定労働時間などの条件次第では社会保険に入ることができず、保険証を入手できません。正社員として就職すれば、その会社を通じて社会保険(健康保険)に加入する義務がある場合がほとんどのため、保険証を持つことがでできます。
-
国民健康保険と社会保険の違い
-

ここまでの解説で「国民健康保険」と「社会保険」という用語が出てきましたが、両者の違いがいまいちよくわからない方もいるかもしれません。そこで以下では、それぞれどのようなものか、誰が加入できるかなどの違いがわかるように説明します。
国民健康保険
日本では、日本に住んでいるすべての方がいつでも一定割合の費用負担で医療を受けるための「国民皆保険制度」を導入しています。
国民健康保険は、その国民皆保険制度を支える制度です。都道府県および市町村が運営しており、後述する社会保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外、全員が加入しなければなりません。
国民健康保険に加入することによって保険証が発行され、通院時に医療機関窓口で保険証を提示することで受診料負担を抑えられます。
国民健康保険の加入対象者としては、以下のような方が該当します。- 自営業の方
- 農業や漁業に従事する方
- 職場の健康保険に加入していないアルバイトやパート従業員
- 退職により職場の健康保険を脱退した方
社会保険
社会保険とは企業が従業員を守るための保険制度で、社会保険のなかには健康保険のほか、厚生年金、雇用保険、介護保険、労災保険が含まれています。
先に述べた国民健康保険は、社会保険のなかの健康保険にあたるイメージです。
多くの会社は従業員を社会保険に加入させる法的義務があるため、就職した場合は、その勤め先を通じて社会保険に加入します。
ただし、正社員ではなくアルバイトとして働く場合は、所定労働時間などの条件次第で社会保険に加入できないケースも多くあるため注意が必要です。
その他、健康保険と国民健康保険では、以下のような点が異なります。- 健康保険の保険料支払いは労使折半(会社と従業員で折半)
- 健康保険にある「扶養」の概念が国民健康保険にはない
- 健康保険のほうが国民健康保険より保障が手厚い(例:傷病手当金など)
特に、保険料支払いが会社と従業員(被保険者)で折半になるのは、社会保険加入の大きなメリットです。国民健康保険は保険料全額を被保険者が支払わなければならないため、アルバイトでも勤め先の社会保険に入れる場合は、入ったほうがお得といえるでしょう。
ただ、アルバイトを社会保険に加入させると、それだけ会社側の負担は大きくなります。そのため、アルバイトのシフトを調整して加入義務を満たさないように雇用するなど、社会保険に入ることができない職場も多いのが現状です。
-
フリーターが国民健康保険に加入するには?
-
国民健康保険への加入は、以下のような書類と手順で申請することができます。
準備するもの
国民健康保険に加入する際に必要となるものは、加入する理由によって異なります。例えば、フリーターが親の扶養を抜けたことにより国民健康保険に加入する場合は、以下のものが必要です。
- 本人確認書類
- 個人番号カードや通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類
- 健康保険の喪失年月日(扶養から外れた日)が記載されている証明書
- キャッシュカード、預貯金通帳、銀行届出印(保険料を口座振替で支払うため)
本人確認書類は、一般的に運転免許証やパスポートなどの顔写真付き書類が使われます。これらを持っていなければ、氏名が確認できる書類を2点以上そろえることで本人確認が可能です。認められる書類の種類は、各自治体のルールを確認してください。
健康保険の喪失年月日は「健康保険資格喪失証明書」に記載されています。親の扶養から外れた場合は、親の勤務先を通じて発行してもらうか、個人で年金事務所に届け出をして発行してもらいましょう。
なお、自治体によって必要書類は異なる可能性があるため、詳しくは各自治体のホームページなどで確認してください。加入手順
国民健康保険の加入は、お住まいの市区町村の役場にて手続きできます。上記の必要書類などを持って、担当窓口に申し出ましょう。
ただし、自治体によっては郵送でも受け付けているケースがあります。郵送を希望する方はホームページなどで郵送も対応をしているか調べてみるとよいでしょう。
-
国民健康保険料が払えないときはどうすればいい?
-
国民健康保険料は社会保険のような労使折半がないだけに、支払いの負担が大きいと感じる方もいます。では、毎月の保険料支払いが経済的に苦しい場合は、どうすれば良いのでしょうか。
減額・免除の相談をする
特別な事情があって国民健康保険料を納めることが難しい場合、保険料の減免を受けられることがあります。例えば、収入が少なくて生活が困窮しているなどの理由を添えれば、減免が認められるかもしれません。
相談は、国民健康保険に加入したときの市町村窓口で行なえます。詳細な条件は自治体によって異なるので、まずは問い合わせてみましょう。分割払いの相談をする
減免の対象にはならないものの、どうしてもすぐに支払えないという場合は、役所に分割払いできないか相談してみましょう。役所の担当者も、ただ単に支払いが滞ったまま放置しているのか、支払う意思はあるけれど滞っているのかによって、対応を変えてくれる可能性があります。
最終的に分割払いが認められるかは担当者の判断に委ねられますが、支払いができる日などの情報を整理したうえで、お住まいの役所窓口に問い合わせてみてください。まずは役所に相談、絶対に無視・放置しない
国民健康保険料は、税金と同様に、滞納を放置してどうにかなるものではありません。上述の減免や分割払いの相談をはじめとして、経済的に厳しくてもとにかく放置せず、支払う意思があることを示すことが大切です。
滞納が続くと督促状が届き、無視していると延滞金がかかるなど、さらに悪い結果になることも考えられます。自己判断で無理だろうと諦めず、まずは役所の担当者に相談してみましょう。
-
まとめ:国民健康保険への加入は義務なので必ず入るようにしましょう!
-
フリーターとして一定の金額を稼いだ結果、いつの間にか親の扶養から抜けてしまい、気付いたら保険証を持っていなかったというのはありえるケースです。
ただ、保険証を持っていないといざというときに困りますし、保険料を支払わないままでいると督促状が届き、さらに放置すれば延滞金も発生します。気付いた時点で収入を調整して親の扶養に入りなおしたり、自分で国民健康保険に加入したりして、必ず保険証を手元に持っておくようにしましょう。
国民健康保険の保険料負担は決して軽くなく、支払いが難しい方もいるでしょう。どうしても支払いが難しい場合は、分割払いや減額・免除の申請方法について、役所の窓口で相談するのもおすすめです。記事監修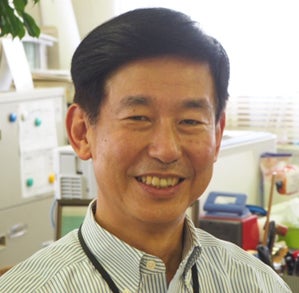
荒武 慎一(あらたけ しんいち)
社会保険労務士、中小企業診断士
昭和53年同志社大学卒業、富士ゼロックス株式会社を経て平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金をわかりやすく解説することで高い評価を得ている。(連絡先:0422-90-9990)
お金・法律 の関連記事
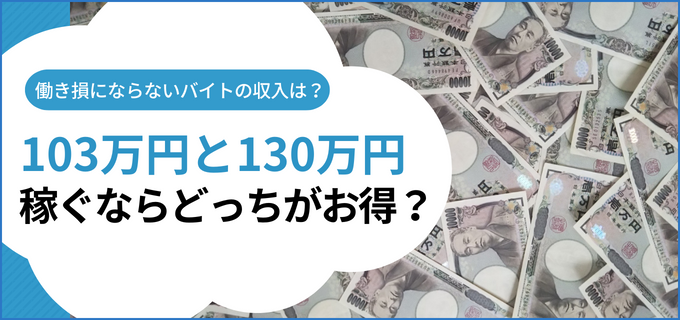
【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】

2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる?
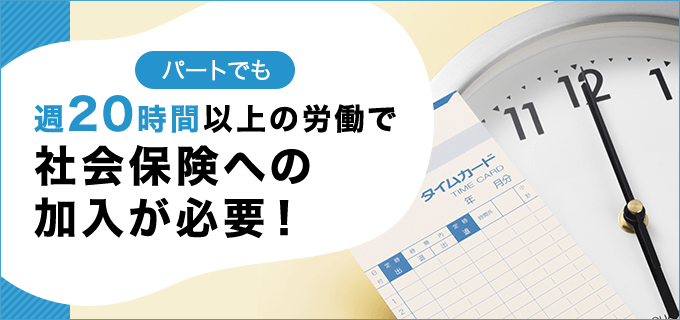
パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要!

【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します
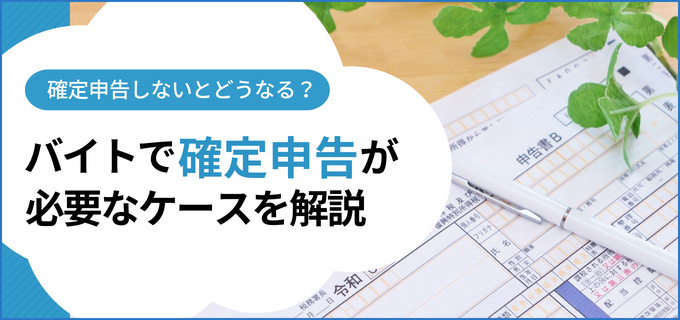
【税理士監修】アルバイトでも確定申告は必要?申告方法や確定申告をしないとどうなるかを解説

【税理士監修】退職後の住民税はどうなる?辞めた時期による納付方法の違いとは 【税金Q&A】

【税理士監修】学生必見!アルバイトでいくら稼ぐと税金がかかる?

【税理士監修】アルバイトを辞めた後の税金と源泉徴収票がもらえないときの対処法【税金Q&A】

給料をもらったが、金額が違う…!こんなときどうする?

【税理士監修】扶養控除の金額とは?配偶者控除や扶養控除のメリットについて解説【税金Q&A】
カテゴリ一覧
-
派遣の仕事探し派遣の仕事探し
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書
- 自宅でできる仕事46選!スキルや趣味、得意分野を活かせる在宅ワークを見つけよう /バイト探し・パート探し
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート
- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!