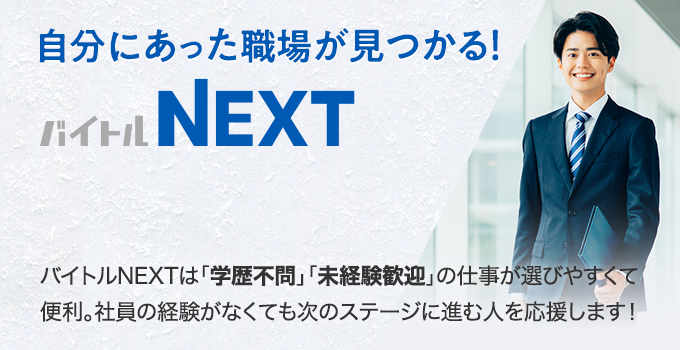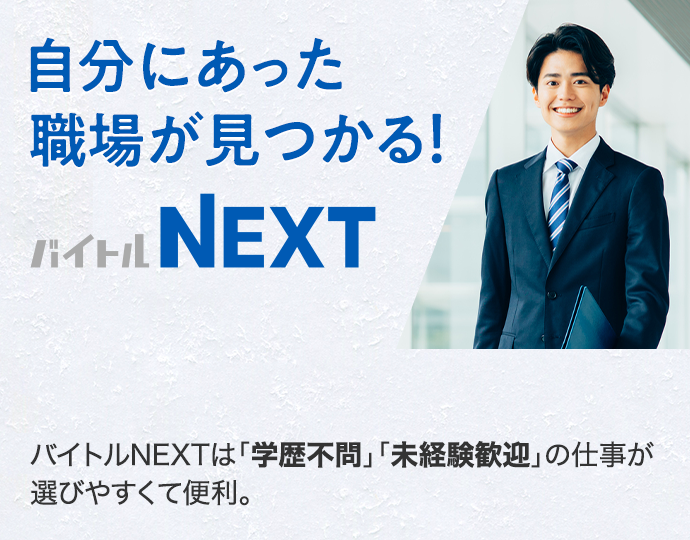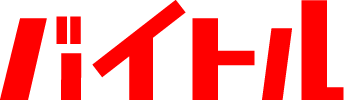【税理士監修】フリーターが支払う税金を一覧で紹介!手取りで損しないために知っておきたいポイントを解説
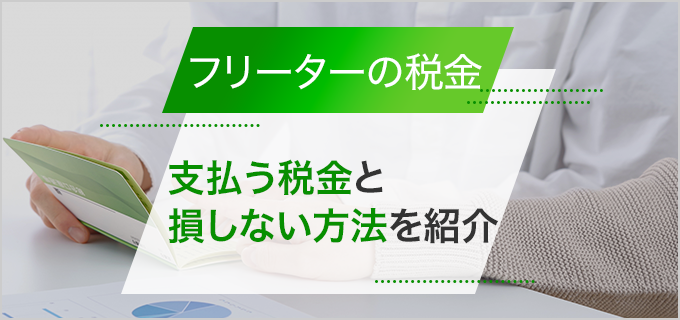
税金や保険料は、フリーターや正社員などの雇用形態に関係なく、基本的に所得のあるすべての国民が納めなければなりません。「フリーターだから払わなくていい」「フリーターだから支払いが遅れてもいい」ということはないため、滞納などしないように注意しましょう。
ここでは、フリーターが納める税金や保険料、手取りで損をしないために知っておきたい控除や年収の壁について解説します。
目次
-
税金の納付方法には2つある
-
税金の納付方法は「給料からの天引き」または「自分で納税する」の2通りです。自分で納税したことがないフリーターの方は、ほとんどの場合、毎月の給料から税金が天引きされているはずです。
では、どのようなケースで納付方法が変わるのでしょうか。まずは、税金の納付方法の違いについて解説します。給料から天引き
天引きとは、アルバイトやパートをしている勤務先が、給料からあらかじめ税金を差し引く仕組みのことです。
収入があるフリーターにはさまざまな税金が発生しますが、通常、フリーターが納めるべき税金は給料から天引きされ、勤務先を通して納税されています。
給料から天引きされるのは税金だけではなく、社会保険も天引きされています。給料から天引きされている項目には以下のようなものがあり、給与明細を見れば、どのような税金がいくら天引きされているのか確認できます。- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料 など
各種税金・保険料が給料から天引きされているのであれば、自分で納付する必要がないため払い忘れる心配がありません。
自分で納税
給料から税金・保険料が天引きされていない場合、自分で納付する必要があります。勤務先の方針で天引きされていない場合や、勤務先が社会保険に加入していなかったり、収入が少なかったりといった場合も、給料から天引きされないことがあるため注意しましょう。
税金・保険料が給料から天引きされていなくても、収入の情報が正しく申告されていれば、納付時期が近づくと税金や保険料の納付書が自宅に送付されます。
税金や保険料にはそれぞれ異なる納付期限があるため、送付された納付書の内容をよく確認し、納付期限までに金融機関やコンビニで支払いましょう。
近年は、バーコードの付いた納付書であればほとんどの税金・保険料をスマートフォン決済アプリで納めることができます。ただし、一部の自治体で非対応の場合もあるため、詳細は住んでいる地域の自治体ホームページ等で確認しましょう。
-
フリーターが支払う税金・保険料一覧
-
フリーターが支払う税金や保険料には、以下のようなものがあります。天引きなのか、自分で納税するのかなど、納付方法と併せて見ていきましょう。
所得税
所得税は、年間の収入が103万円を超えた場合に発生する税金です。収入から各種控除を差し引いた残額(課税される所得金額)に、規定の税率をかけて算出されるため、収入が多くなるほど納めるべき所得税も高くなります。
課税される所得金額 税率 控除額 1,000円 ~ 194万9,000円まで 5% 0円 195万円 ~ 329万9,000円まで 10% 9万7,500円 330万円 ~ 694万9,000円まで 20% 42万7,500円 695万円 ~ 899万9,000円まで 23% 63万6,000円 900万円 ~ 1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円 1,800万円 ~ 3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円 4,000万円以上 45% 479万6,000円 (参考:国税庁「所得税の税率」)
所得税は勤務先の給料から天引きされるケースが一般的です。概算により天引きされた所得税と本来納めるべき所得税にずれが生じていた場合は、年末調整や確定申告で精算され、多く払い過ぎた場合には還付されます。
住民税(都道府県民税・市町村民税)
住民税は、都道府県民税と市町村民税からなる地方税で、居住している自治体によっても異なりますが、多くの自治体で前年の収入が100万円を超えていた場合に発生します。
住民税の課税対象となった場合、住民が一律で支払う「均等割」と、収入に応じて支払う「所得割」によって税額が決定します。
住民税の計算方法は住んでいる自治体によっても異なりますが、おおよその住民税を知りたい場合は以下のように算出しましょう。住民税=均等割+所得割
均等割=5,000円
所得割=課税所得金額×10%なお、住民税は、給料から天引きされる「特別徴収」と、自分で納税する「普通徴収」のいずれかの方法で納付します。普通徴収の場合、支払い方法は一括払いと年4回の分割払いから選べます。
健康保険料(国民健康保険料もしくは被用者保険)
健康保険とは、医療機関での自己負担を一定の割合に抑えられる国の保険制度のことです。健康保険には国民健康保険と被用者保険の2種類があり、基本的に、国民はいずれかの保険に加入する必要があります。
フリーターの場合、一定の勤務条件に当てはまると勤務先の社会保険に加入しますが、社会保険に加入しない場合は国民健康保険に加入することになります。
年収130万円を超えると社会保険の加入義務が生じますが、130万円を超えない場合でも社会保険の適用範囲は年々拡大され、2022年10月からは以下の条件に当てはまるフリーターも社会保険の適用対象となりました。- 学生ではない
- 1ヵ月の給料が8万8,000円以上
- 見込まれる雇用期間が2ヵ月以上
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 勤務先の従業員数が101人以上
(参考:厚生労働省「パート・アルバイトのみなさま」)
社会保険では、健康保険料の半分は勤務先の企業が負担し、残りの半分が給料から天引きされます。社会保険の健康保険料率は都道府県単位で異なりますが、収入の9%台から10%台が目安です。
(参考:全国健康保険協会「令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」)
例えば、社会保険に加入しており、1ヵ月に15万円の収入があるフリーターの場合、健康保険料は1万3,500円~1万5,000円、自己負担額は6,750円~7,500円が目安となります。
国民健康保険の場合、社会保険に加入しておらず年間の収入が130万円を超える場合には加入(保険料支払い)義務があります。
また、国民健康保険においては会社の健康保険のような「扶養」という考え方がないので、同居家族であっても扶養になるわけではありません、全員が被保険者となり、条件が満たされていればそれぞれに保険料が発生します。
国民健康保険加入時の健康保険料は、前年度の所得や世帯人数、年齢の各条件と自治体ごとの料率とで算出されます。詳しい金額を知りたい場合は市区町村役場へ問い合わせましょう。
国民健康保険加入時の健康保険料は、市区町村役場へ申請し、口座振替または納付書で支払えます。(年金受給者は年金からの天引きも可)年金保険料(国民年金保険料もしくは厚生年金保険料)
年金保険とは、将来に備える公的な保険制度で、収入に関係なく20歳以上60歳未満の国民に加入義務があります。
年金保険には、国民年金と厚生年金保険の2種類があり、国民年金は将来「老齢基礎年金」を受給でき、厚生年金は将来「老齢厚生年金」を受給できる保険です。
国民年金の保険料は収入に関係なく一律料金のため、支払いが滞らないよう注意しましょう。令和5年度の1ヵ月の国民年金保険料は1万6,520円です。
(参考:日本年金機構:「国民年金の保険料はいくらですか。」)
勤務先で厚生年金保険に加入する場合は、国民年金の保険料を含む厚生年金保険料が、毎月給料から天引きされます。
フリーターで厚生年金保険に加入しておらず、国民年金のみに加入している場合、口座振替や納付書、クレジットカードで納付しましょう。
なお、国民年金の保険料は、前払い(前納)することで割引が適用されます。まとめて払うほど割引額が増えるので、余裕があるなら利用してもよいでしょう。雇用保険料
雇用保険とは、失業や育児・介護による休業などをしたときに手当を受給するための保険です。以下の勤務条件を満たす場合に雇用保険へ加入でき、加入した場合は毎月の給料から雇用保険料が天引きされます。
- 見込まれる雇用期間が31日以上
- 1週間に実働20時間以上勤務
- 学生ではない(休学中の者など、例外がある)
雇用保険料は厚生労働省が定める雇用保険料率と収入をもとに算出され、フリーターの場合は数百円が目安です。雇用保険の加入要件を満たしていて、雇用保険へ加入したい場合は、勤務先へ相談してください。
その他、消費税や酒税など
その他、正社員やフリーターなどに関係なく、国民全員が負担する税金には以下のようなものがあります。
消費税
商品やサービスを購入する際に消費者が負担する税金で、事業者を通じて国へ納税されます。
酒税
ビールや日本酒などの酒類を購入する際に消費者が負担する税金で、酒類の製造者や輸入者が国へ納税します。
たばこ税
たばこを購入する際に、消費者が負担する税金で、たばこの製造者や輸入者が国へ納税します。
自動車税・自動車重量税
毎年4月1日時点で自動車を所有する人に課せられる税金で、自動車の排気量によって税額が変わります。5月頃に届く納付書を使って納税します。
-
フリーターでも確定申告は必要?
-

勤務先の方針や、フリーターの働き方によっては、確定申告が必要となる場合があります。確定申告が必要なケースと、不要なケースについて解説します。
確定申告が必要なケース
勤務先で年末調整が行なわれない場合、年間の所得を申告し、所得税を納めるために確定申告が必要です。
年内にアルバイト先を退職してしまい、年末調整をしてもらえていなかったり、アルバイトを2ヵ所以上でかけ持ちしたりする場合も、確定申告で正しい所得を申告しなければ なりません。
複数の勤務先から給料をもらった場合、年末調整されなかった給料の合計額が20万円を超えていない場合、確定申告は不要です。確定申告が不要なケース
アルバイトやパートをかけ持ちしておらず、勤務先で年末調整が行なわれている場合は、原則として確定申告は不要です。年間の所得が103万円を超えない場合も所得税の課税対象にならないため、確定申告は不要です。
ただし、払い過ぎた税金の還付を受けたい、年末調整で提出できなかった書類を使って控除を受けたいといった場合は、確定申告を検討しましょう。
-
確定申告をするフリーターが知っておきたい税金の控除について
-
控除とは「一定の金額などを差し引く」という意味の言葉です。税金の多くは収入が多いほど高くなりますが、控除を活用すると課税対象となる所得金額を減額することができ、税額を抑えられます。以下では、フリーターにも関わる控除にどのようなものがあるのか解説します。
基礎控除
基礎控除とは、所得税や住民税を計算する際に、収入の総額から差し引きできる基本の控除です。フリーターの場合、所得税で48万円、住民税で43万円の基礎控除を受けられます。
(参考:国税庁「基礎控除」)扶養控除
扶養控除とは、配偶者以外の親族を扶養する場合に活用できる控除です。扶養対象となる人の年齢によって控除額は異なり、16歳以上で38万円、19歳から23歳未満で63万円と定められています。
70歳以上の親族を扶養する場合は同居の有無で控除額が異なり、同居している場合は58万円、同居していない場合は48万円です。
(参考:国税庁「扶養控除」)
扶養親族がいるフリーターの場合は扶養控除を活用すると税額を大きく抑えられるでしょう。給与所得控除
給与所得控除とは、給料をもらっている人が活用できる控除です。給与所得控除の控除額は年間の収入によって変わり、年間の収入が162万5,000円以下の場合は55万円の控除を受けられます。
年間の収入が増えるほど控除額も大きくなります。
(参考:国税庁「給与所得控除」)配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者(夫や妻)のいる人が利用できる控除です。控除を受ける人の年間の収入が1,000万円以下であり、納税者と生計をともにしていることなどの条件で、配偶者の合計所得金額が年間48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であれば控除を受けられます。
控除額は納税者の収入によって異なり、900万円以下で38万円(控除対象配偶者が70歳以上の場合は48万円)です。
(参考:国税庁「配偶者控除」)
-
税金で働き損になる可能性がある「年収の壁」とは?
-

収入が一定の金額を超えると税金や保険の対象となることから、収入金額によっては税金や保険料を納めなければならず、働き損になる可能性があります。
このようにわずかな年収の差で損得が生じる現象は、ボーダーとなる金額ごとに「年収の壁」と呼ばれます。
「せっかく働いた分の収入が税金や保険料で消えてしまった…」ということがないように、フリーターの方が知っておくべき3つの壁について見ていきましょう。103万円の壁
103万円の壁とは、所得税が発生する年収の壁のことです。
フリーターの場合、適用される基本の控除には、基礎控除の48万円と、給与所得控除の55万円があります。これらを合計すると103万円となり、103万円を超える部分に所得税がかかります。
フリーターで税額を抑えたい場合は、年収が103万円を超えないように働く日数や時間を調整しましょう。この際、同時に住民税が発生する100万円のラインも考慮することで、さらに税額を抑えられます。
ただし、年収を103万円以内に収めようとすると、出勤日数や労働時間に制限がかかり、働き方に縛りが出てきます。新たにアルバイト先を探す際も選択肢が狭まってしまうため、手取り額を多くしたい場合は、103万円の壁にとらわれずに出勤日数や労働時間を増やすとよいでしょう。130万円の壁
130万円の壁とは、配偶者や親族の扶養から外れ、社会保険への加入義務が発生する年収の壁のことです。勤務先で社会保険へ加入すると、社会保険料と厚生年金保険料が天引きされることになるため、手取り額が大きく減少します。
もし、130万円の壁を超えて働く場合、年収を200万円近く稼ぐことができれば、各種税金や保険料を差し引いたとしても130万円以上の手取り額を見込めます。
年収が130万円前後で、それ以上大きく増やせそうにないときは、130万円以下になるように出勤日数や労働時間を調整することで、最終的な手取り額を多く残せるでしょう。150万円の壁
150万円の壁とは、配偶者特別控除の控除額が減額されてしまう、配偶者の収入の壁を指します。
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が48万円を超え、133万円以下の場合に適用できる控除のことです。先述の配偶者控除と異なり、配偶者に48万円を超える所得があっても控除を受けられる点がポイントです。
しかし、配偶者特別控除で満額(38万円)の適用を受けるには、配偶者の課税所得金額を95万円以下に収めなければなりません。
95万円を超えるラインとしては、例えば配偶者の収入から給与所得控除が55万円差し引かれる想定であれば「95万円+55万円=150万」と計算できます。つまり、給与が150万円を超えると課税所得金額が95万円を超えてしまい、配偶者特別控除を満額受け取れません。
(参考:国税庁「年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」)
-
フリーターが税金の負担を軽くするためのポイント
-
フリーターが税金や保険料の負担を軽くするために、どのような工夫ができるのか解説します。
働き損にならない年収の範囲内でシフトを組む
103万円を超えて働き損になる可能性があるのは、親の扶養に入っているフリーターです。
フリーター本人の税金額は、103万円を超えた部分1万円あたり500円ほどと少額ですが、世帯全体の収入で考えると万単位で高くなってしまいます。
理由は、扶養から外れて控除が受けられなくなることで、これまで扶養者だった人の税負担が増えるためです。
上記のフリーターで年収が130万円を超えると、配偶者や親の社会保険の扶養から外れ、フリーター本人の給料から天引きされるものが増えるため、手取り額が大幅に少なくなります。
フリーターで税金や保険料の負担を考える際は、ご自身の状況に合わせて、働き損にならない範囲でシフトを組むようにしましょう。社会保険に加入できるアルバイト先を見つける
アルバイト先で社会保険に加入すると、目先の手取り額は減りますが、厚生年金保険を支払うことで将来に向けた備えができます。
厚生年金保険料は会社と折半であるため、親の扶養内で働いているフリーターなどでなければ、社会保険に加入して損はありません。正社員として就職する
社会保険に入れない環境で働いているフリーターの方は、正社員として就職することで社会保険や厚生年金に加入でき、先述のように将来への備えができます。
正社員はフリーターに比べると福利厚生や手当が充実していることも多く、ボーナスや昇給などもあることから、収入を大きく増やせる可能性があります。税金が支払えない場合は役所に相談する
税金や保険料の負担が大きく、払えないとわかったときは、市区町村役場へ相談しましょう。理由によっては、税金の減免制度を利用できたり、支払いに猶予を設けてもらったりできる可能性があります。
税金や保険料を滞納すると、延滞税が発生したり、財産の差し押さえが行なわれたりする場合もあるため注意してください。税金の支払いに関する規定は自治体によっても異なるため、支払いが難しいとわかったときは、必ず住んでいる地域の市区町村役場へ早めに相談してください。
-
まとめ:働き方を上手に調整して税金の支払いで損をしないようにしよう!
-
フリーターでも、一定の収入があると税金の納税義務が発生します。20歳を超えると国民年金の加入義務も出てくるため、収入によっては税金や保険料の負担が大きいと感じる方もいるでしょう。
所得に対して課される税金は、各種控除を活用したり、年収の壁を越えないようにシフトを調整したりすることで金額を抑えられる場合があります。今より収入を増やして手厚い福利厚生を受けることを目指すなら、社会保険のあるアルバイト先や社員登用制度のあるアルバイト先を探してはいかがでしょうか。
社会保険完備や社員登用制度のあるアルバイト先を探す際は、豊富な仕事情報をチェックできるバイトルをぜひご利用ください!記事監修
増田 浩美
増田浩美税理士事務所所長
女性ならではのきめ細やかな視点を強みに、企業から個人まで幅広い税務のサポートを行う。
ホームページ:http://www.zeimukaikei.jp/
お金・法律 の関連記事
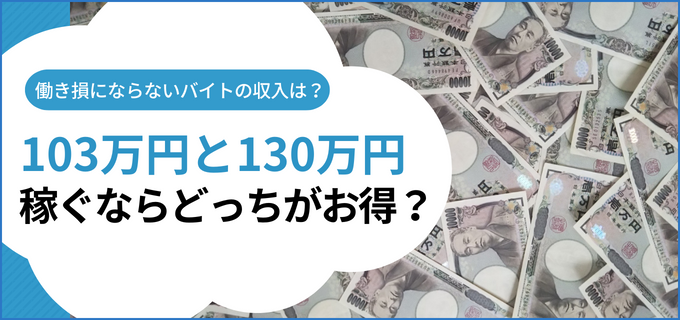
【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】

2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる?
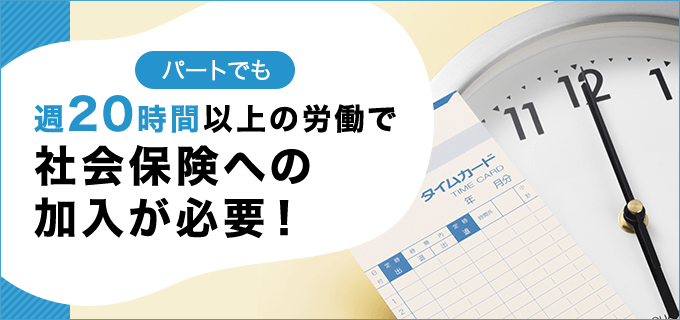
パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要!

【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します
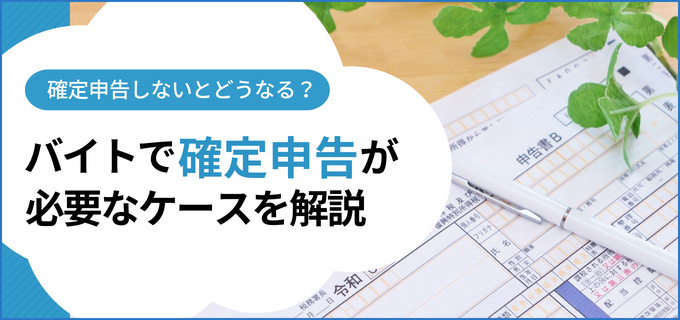
【税理士監修】アルバイトでも確定申告は必要?申告方法や確定申告をしないとどうなるかを解説

【税理士監修】退職後の住民税はどうなる?辞めた時期による納付方法の違いとは 【税金Q&A】

【税理士監修】学生必見!アルバイトでいくら稼ぐと税金がかかる?

【税理士監修】アルバイトを辞めた後の税金と源泉徴収票がもらえないときの対処法【税金Q&A】

給料をもらったが、金額が違う…!こんなときどうする?

【税理士監修】扶養控除の金額とは?配偶者控除や扶養控除のメリットについて解説【税金Q&A】
カテゴリ一覧
-
派遣の仕事探し派遣の仕事探し
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書
- 自宅でできる仕事46選!スキルや趣味、得意分野を活かせる在宅ワークを見つけよう /バイト探し・パート探し
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート
- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!