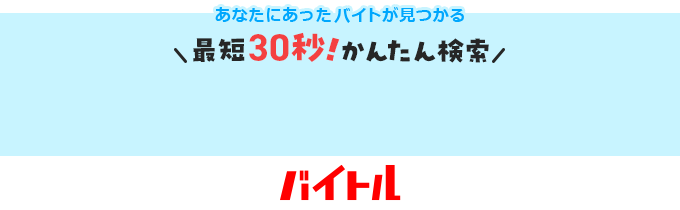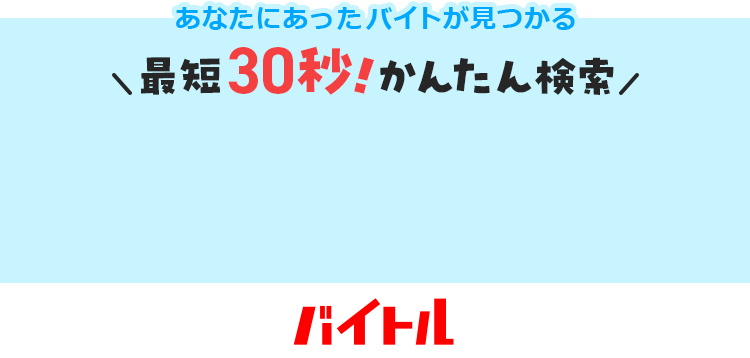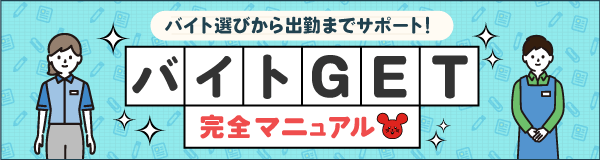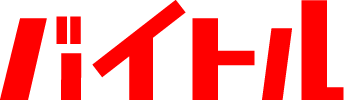【税理士監修】副業で確定申告が必要なのはいくらから?条件ややり方、疑問点を解説

副業・WワークOK!
副業を始めたけれど「確定申告は必要なの?」「どの所得が申告の対象?」といった疑問を抱える方も多いでしょう。副業の年間所得が一定以上を超える場合は確定申告が必要であり、申告しないとペナルティが課せられることも。
申告することで節税メリットや税金の還付を受けられるケースもあるため、申告義務がなくても申告した方が得するケースもあるんです。
この記事では、副業で確定申告が必要な条件ややり方など、初心者にもわかりやすく解説します。最後にはよくある質問をまとめたので、ぜひチェックしてみてください。
目次
-
副業で確定申告が必要なのはいくらから?
-
副業で確定申告が必要かどうかは、収入や所得の金額によって異なります。一般的に、副業による所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。この「20万円」は、副業で得た「収入」ではなく、「所得」を指します。
副業を始めたばかりでよくわからない方も、まずは「20万円」という基準を覚えておくことが大切です。なお、所得が20万円以下でも住民税の申告は必要なので、注意しましょう。
※参考:国税庁「スマホで確定申告(副業編)」収入と所得の違いとは
「収入」と「所得」は似たように思えますが、税金計算では異なる意味を持っています。収入とは、労働に対して支払われる報酬や商品やサービスを提供したことで得られる総額を指します。
たとえば副業で20万円稼いだ場合、副業で得た総額20万円が「収入」にあたります。一方、所得は収入から必要経費を引いた金額です。税金の計算対象となる実質的な利益といえます。20万円の収入に対して5万円の経費がかかった場合、所得は15万円です。
確定申告の必要性を判断する際は、単なる収入額だけでなく、経費を差し引いた所得額に注目することが大切です。
※参考:東京都北区「「収入」と「所得」の違いは何ですか?」
-
副業所得が20万円以下でも確定申告をした方がよい場合
-
副業による所得が20万円以下の場合、一般的には確定申告をする義務はありません。しかし、以下のケースに当てはまる場合は申告する必要がある、もしくは申告することでメリットがあります。
- 住宅ローン控除や医療費控除などを受ける場合
- 副業で所得税が源泉徴収されている場合
- 副業が赤字になっている場合
- インボイス制度に登録しており消費税の納税が必要な場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
住宅ローン控除や医療費控除などを受ける場合
住宅ローン控除や医療費控除、寄付金控除などを受けたい場合、副業所得が20万円以下でも確定申告を行うことで控除が受けられるかもしれません。この場合確定申告をすることで、給与所得にかかる税金が減額されたり、還付金を受け取れたりするメリットがあると覚えておきましょう。
副業所得の大小にかかわらず、確定申告によって控除を確実に受けられるようにすることが重要です。副業で所得税が源泉徴収されている場合
副業で得た収入に対して源泉徴収が行われている場合、確定申告を通じて還付を受けられるかもしれません。たとえば、バイトや契約業務で源泉徴収されていると、年間所得が一定額を超えない場合でも所得税が差し引かれていることがあります。
この場合、確定申告で所得全体を再計算することで、払い過ぎた税金の還付を受けられることが多いです。副業で得た収入を確認し、源泉徴収されている場合は確定申告をしましょう。副業が赤字になっている場合
副業で赤字になっているときは確定申告をすることをおすすめします。副業が赤字の場合、本業での給与所得と損益通算が可能になり、全体の所得を減らすことで税負担が軽減されるからです。
損益通算をすることで最終的な課税額が抑えられると、翌年以降の税金に影響を与えます。副業で経費がかかり赤字になるような方は、この点を押さえておくと良いでしょう。
※参考:国税庁「No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」インボイス制度に登録しており消費税の納税が必要な場合
インボイス制度に登録している場合、消費税の申告・納税が必要なため、確定申告をする必要があります。たとえ所得が20万円以下であっても、消費税の納税義務が生じるため、確定申告を行いましょう。
※参考:国税庁「確定申告」
-
副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必須
-
副業による所得が20万円以下であっても、住民税の申告は必須です。所得税の確定申告義務が発生しない場合でも、住民税は自治体に対しての納税義務があるため、住民税の申告が必要となります。
住民税は主に所得に基づき算出され、各自治体が税額を決定します。副業収入の申告をしないと、自治体が正確な税額を把握できず、最終的に住民税の未納や過少申告につながる可能性も。
住民税の申告を怠ると、あとから追加で納税を求められたり、罰金が発生したりするケースもあります。必ず期限内に正確な申告を行いましょう。
-
副業するなら知っておきたい4つの所得区分
-
副業を始める際は、自分の収入がどの所得区分に該当するかを理解しておくことが重要です。ここでは、代表的な所得区分として以下の4つを見ていきましょう。
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 雑所得
給与所得
給与所得は、会社員やバイトのように雇用契約に基づいて得た収入を指します。副業でも、企業との契約で月給や時給で収入を得ている場合は、「給与所得」として扱われます。
給与所得には給与所得控除があるため、一定の収入までは税金が軽減されるメリットがあります。しかし、給与所得として申告する場合は、勤務先に副業が知られる可能性が高くなるため注意が必要です。
※参考:国税庁「No.1400 給与所得」事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等から生ずる所得をいいます。規模や継続的・反復的に行われているかなどの観点から判断し、たとえば、会社員が行うような副業は、事業所得ではなく雑所得となります。
事業所得は、青色申告を選択することで、青色申告特別控除を受けられるメリットがあります。また、副業で赤字になった場合に、給与所得など他の所得と損益通算することできる点も魅力です。
副業として事業所得を申告する際は、領収書の管理や収支の記録をきちんと行うことが重要です。
※参考:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」不動産所得
不動産所得は、賃貸用の不動産を所有していて得られる収入から必要経費を差し引いた金額が対象です。たとえば、アパートの家賃収入や駐車場の貸付収入などが不動産所得に該当します。
副業として賃貸不動産経営を行っている場合も、不動産所得に区分されます。事業所得と同様、青色申告を選択することで、青色申告特別控除を受けられますし、赤字の場合はほかの所得と損益通算が可能で、税金が軽減される場合もあり、節税につながることも。
不動産経営では、収入と経費の把握をしっかり行い、申告の際に正確なデータを提示することが大切です。
※参考:国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」雑所得
雑所得とは、所得税法で定められた以下の所得にあてはまらないものを指します。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
雑所得は主に、「公的年金等」「業務」「その他」の3つに区分されます。副業の所得は、雑所得の「業務」に該当することが多いです。
※参考:国税庁「No.1500 雑所得」
※参考:国税庁「スマホで確定申告(副業編)」
-
確定申告の種類|青色申告がおすすめ!
-
事業所得または不動産所得について確定申告するには、「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、節税効果を得たい方には「青色申告」がおすすめです。
青色申告は、一定の条件を満たした帳簿を作成することで多くの控除を受けられるため、副業で発生した金銭のやりとりをしっかりと管理しつつ節税を行う方法として適しています。ここでは、青色申告の仕組みやメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
※参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」青色申告とは
青色申告とは、収入と経費を詳細に管理し、一定の帳簿を正確に作成・提出することで、各種控除を受けられる申告方式です。
青色申告をするためには、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出します。
青色申告をすると、55万円(最大65万円)または10万円の特別控除が適用されるほか、家族への給与を必要経費に含めることや赤字を翌年に繰り越すことが可能です。
※参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」
※参考:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」青色申告のメリット
青色申告のメリットは、節税効果が高い点です。特に青色申告特別控除は、55万円(最大65万円)または10万円の特別控除を適用できるため、所得税や住民税を大幅に抑えられるでしょう。
また、家族従業員に対する給与を経費として計上できる「青色事業専従者給与」や、赤字を最大3年間繰り越して控除できる「純損失の繰越控除」もメリットといえます。収支が不安定な副業者やフリーランスにとって、税負担を軽減しやすい仕組みは魅力的です。青色申告のデメリット
一方で、青色申告にはデメリットもあります。申告に必要な帳簿付けや記帳義務があり、正確な会計処理が求められるため、手間がかかる点が課題となりやすいです。帳簿付けには簿記や会計の知識が必要で、作業が煩雑に感じられることもあります。
個人で処理できない場合、税理士に依頼することも可能ですが、費用がかかるため手間とコストを考慮しながら選択することが重要です。
-
【Q&A】確定申告に関してよくある質問
-
最後に、確定申告に関するよくある質問をまとめました。
副業の所得が20万円以上で確定申告しないとどうなる?
副業で得た所得が年間20万円以上の場合、確定申告を行わないと所得税の未納状態になり、ペナルティが課せられる可能性があります。税務署は所得データを把握しているため、申告を怠ると追加徴税や延滞税を請求されることも。
また、無申告加算税という罰金も課せられる場合があり、通常の税金よりも負担が大きくなるかもしれません。確定申告の義務がある場合は、期限内に正確に申告することでリスクを回避しましょう。
※参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」確定申告をすると会社に副業がバレるって本当?
副業所得がある場合、その分住民税が増加します。会社を通じて住民税が支払われると、給与所得から算出した住民税より多く税金を納めることになるため、増額分が目に付く可能性があります。副業所得が0円でない限り、住民税・所得税の増額は免れないでしょう。
パートや副業をしている主婦・主夫でも確定申告が必要?
パートや副業で収入を得ている主婦・主夫も、条件によっては確定申告が必要です。たとえば、副業やパートでの所得が年間20万円を超える場合には、申告義務が発生します。
確定申告の可否は、以下の項目を参考にしてみてください。- 勤め先が1つで年末調整を行う場合は、確定申告は原則不要
- 年度の途中で辞めたパートで源泉徴収されていた場合は、確定申告することで税金が還付される
- 本業のパート以外で年間20万円以上の所得があれば、確定申告が必要
- ダブルワーク(事業または不動産経営)が赤字の場合は、確定申告することで税金が還付される
-
まとめ|副業で得た所得も忘れずに確定申告をしよう!
-
副業所得が年間で20万円を超える場合や特定の控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。また、所得が20万円以下でも住民税の申告義務があるため、申告を忘れないようにしましょう。
確定申告は一見面倒な手続きに思えますが、青色申告を利用すれば控除額が増えたり、納めすぎた税金が還付されたりするなどのメリットがあります。申告手続きを怠ると罰金や追加徴税のリスクがあるため、必要書類をしっかり準備し、手順を確認して早めに取り掛かることが大切です。
副業の成果を最大化するためにも、適切な確定申告を行い、安心して副業を続けましょう。

増田 浩美
増田浩美税理士事務所所長
女性ならではのきめ細やかな視点を強みに、企業から個人まで幅広い税務のサポートを行う。
ホームページ:http://www.zeimukaikei.jp/
※2020年10月に記載した記事です。
※2024年12月、税理士が監修のうえ、本記事を修正・変更いたしました。
お金・法律 の関連記事
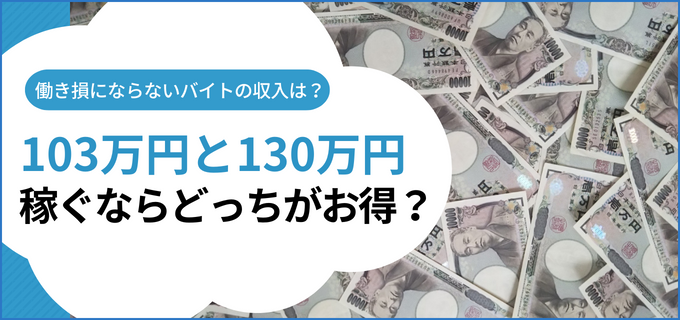
【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】

2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる?
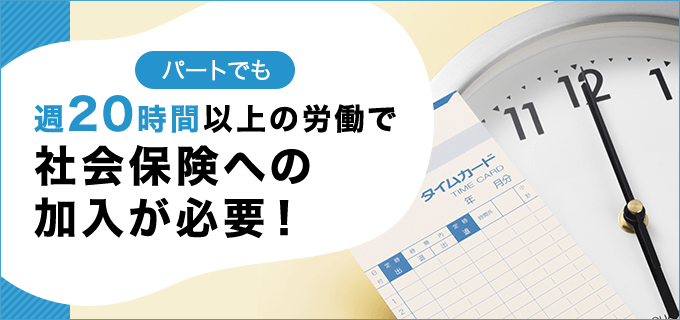
パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要!

【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します
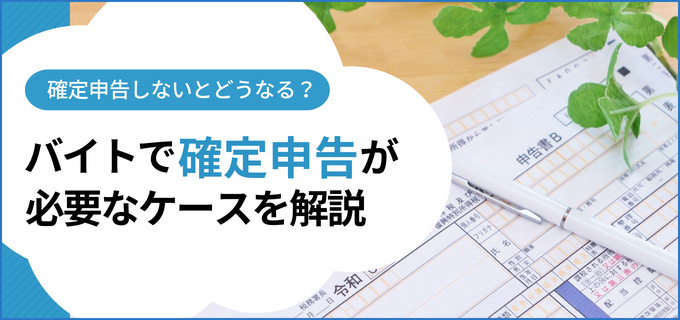
【税理士監修】アルバイトでも確定申告は必要?申告方法や確定申告をしないとどうなるかを解説

【税理士監修】退職後の住民税はどうなる?辞めた時期による納付方法の違いとは 【税金Q&A】

【税理士監修】学生必見!アルバイトでいくら稼ぐと税金がかかる?

【税理士監修】アルバイトを辞めた後の税金と源泉徴収票がもらえないときの対処法【税金Q&A】

給料をもらったが、金額が違う…!こんなときどうする?

【税理士監修】扶養控除の金額とは?配偶者控除や扶養控除のメリットについて解説【税金Q&A】
カテゴリ一覧
-
派遣の仕事探し派遣の仕事探し
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書
- きっと見つかる!自宅で一人でできる仕事46選 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】アルバイトでも確定申告は必要?申告方法や確定申告をしないとどうなるかを解説 /お金・法律
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート
- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!