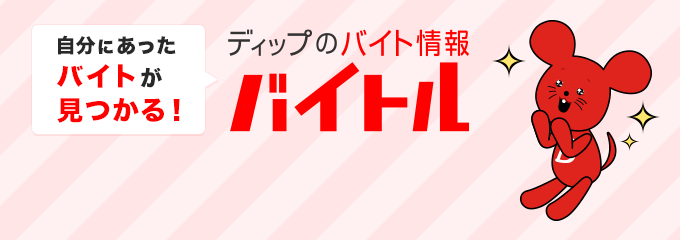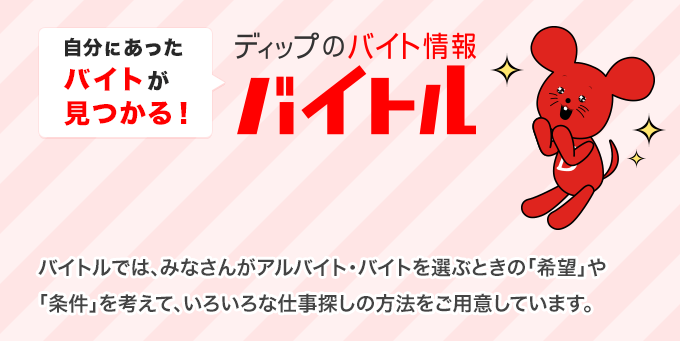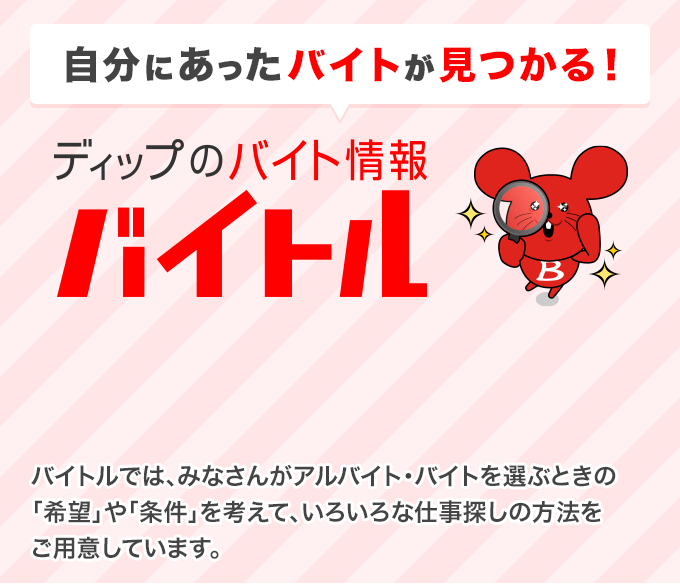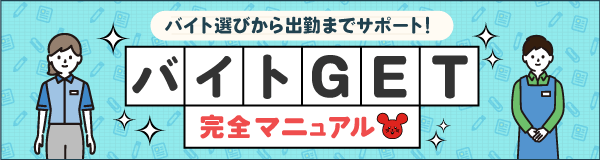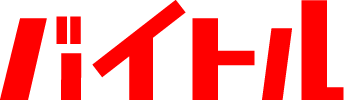DXとは?目的・進め方・課題や具体的な成功事例をわかりやすく解説
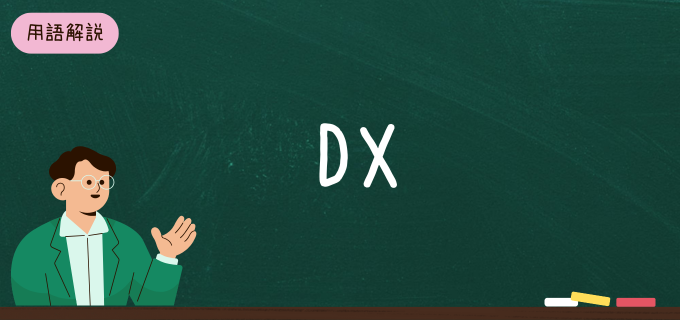
DXという言葉をよく耳にするものの、具体的に何がDXなのかわからない、あるいはDXについて簡単に知りたいという方は多いのではないでしょうか。
DXとは、デジタル技術の活用によって、既存の業務やビジネスモデルを根本から変革し、新たな価値を創造する取り組みです。
本記事を読めば、DXの定義や目的、具体的な進め方、直面する課題を理解でき、企業の特徴や方向性を正しく把握するためのヒントが得られます。ぜひDXへの第一歩を踏み出すきっかけにしてください。
目次
-
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
-
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を駆使して人々の生活や企業活動を根本的に変革する取り組みを指します。2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が発表し、広く知られるようになりました。
ビジネスにおけるDXは、単なる業務フローの改善や旧来のシステムからの脱却にとどまらず、新たなビジネスモデルの創出や企業文化の変革までを含む、包括的な意味を持ちます。
日本では、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」をきっかけに、DXという言葉が広く浸透し、その重要性が認識されるようになりました。
DXは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠な戦略となっており、多くの企業が積極的に取り組んでいます。
-
DXとIT化の違い
-
DXとIT化はどちらもデジタル技術を活用する取り組みですが、目的と範囲に大きな違いがあります。
ITは「Information Technology」の略で、コンピューターとネットワーク技術の総称です。IT化は、デジタル技術を既存の業務プロセスに適用し、業務効率化と生産性向上を目指します。
例えば、紙の書類を電子化したり、手作業の計算をコンピューターで行ったりすることがIT化にあたります。
一方、DXは単なる効率化にとどまらず、社会や組織、ビジネスの仕組みそのものを変革することを目指します。
つまり、IT化はDX推進に向けた手段の一つであり、DXはIT化を含んだより大きな概念といえるでしょう。
-
DXを推進する目的
-
2018年の「DXレポート」では、DXを推進しない企業が「2025年の崖」の問題に直面する可能性が指摘されています。「2025年の崖」とは、企業がDXを実現できない場合、2025年以降に日本全体で年間最大12兆円の経済損失が生じるリスクです。
参考:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」
この問題を背景に、DXを推進する目的はおもに以下の3点です。
- 業務の効率化
- 多様化する消費者ニーズへの対応
- 競争力の強化
それぞれ詳しくみていきましょう。
業務の効率化
DXを推進する大きな目的の一つが、システムの処理時間短縮や作業工程の見直しによる業務の効率化です。
例えば、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション:ソフトウェアを使って単純作業を自動化する技術)を導入し、人間が行っていた単純作業や反復作業を自動化すれば、従業員がより創造的な業務に集中できるようになります。また、クラウドサービスを活用すれば、インターネットを通じてデータやアプリケーションを利用でき、情報共有や共同作業の効率が飛躍的に向上します。
しかし、単に業務プロセスの無駄を排除し効率化するだけではIT化にとどまります。DXでは、これまでの仕組み自体を変革していくことが重要です。多様化する消費者ニーズへの対応
デジタル時代の消費者ニーズに適応することも重要な目的です。
現代では、インターネットの普及により情報収集が容易になった結果、消費者ニーズが多様化しています。そのため、より便利で個別化されたサービスが求められるようになってきています。企業はDXを推進することで、この変化に柔軟に対応していかなければなりません。
例えば、ビッグデータ分析やAIを活用して、消費者の行動パターンや嗜好を詳細に把握し、それに基づいて製品やサービスを最適化するといった戦略的アプローチが必要です。競争力の強化
企業の競争力を強化するうえでもDXの推進は重要です。既存業務や既存システムの見直しを図り、多様化する消費者ニーズに対応できれば、市場における競争優位性を確立できます。
DXの推進は、デジタル技術を駆使した新しいビジネスモデルの創出や、顧客体験の革新的な改善につながります。また、データ駆動型の意思決定によって、市場の変化に迅速に対応できるようになれば、競合他社に先んじて行動することも可能です。
-
DXの現状
-
世界的に急速なDX化が進むなか、日本でも多くの企業がDXの重要性を認識し、取り組みを進めています。しかし、国際社会において日本はやや遅れを取っているのが現状です。
スイスの国際経営開発研究所(IMD)が2024年に発表した世界デジタル競争力ランキングでは、日本は64ヵ国中31位という中位の順位にとどまる結果となりました。参考:IMD/World Competitiveness Center「IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024」
今後、日本の企業が国際的な競争力を高めていくためには、単なる情報システム部門の課題としてDX化をとらえるのではなく、企業全体が一体となって取り組む必要があります。
-
DX化に向けたおもな課題
-
DXの推進は多くの企業にとって重要な課題ですが、その実現にはさまざまな障壁が存在します。ここでは、企業がDXを推進していくうえで直面する、おもな課題について解説します。
人材不足・予算不足
DX推進の大きな障壁の一つとなっているのが、人材不足・予算不足の問題です。
多くの企業では、DXを推進できる人材や、必要なシステムを開発できる人材が不足しています。また、DXの必要性を認識しつつも、高額なコストがネックとなり、十分な予算を確保できていない企業も少なくありません。
特に、中小企業ではこの問題が顕著で、人材育成や外部リソースの活用、段階的な投資計画の策定など、長期的な視点で対策していくことが求められます。レガシーシステムの問題
多くの企業においてDX推進の足かせになるのが、レガシーシステムの問題です。既存システムが老朽化・複雑化し、システムの改修や保守業務の引き継ぎ、システムの復元などに多大な時間と労力がかかる状態に陥っている企業は少なくありません。
さらに、基幹システムが事業部門ごとに構築されているケースも多く、会社全体でのデータ連携や活用を困難にし、DXの取り組みによる成果が限定的なものになってしまっています。
これらの問題を解決するには、システムの再構築や統合、クラウド化などの抜本的な対策が急務です。企業の理解不足
経営陣を含めた企業全体のDXへの理解不足も、DX推進における重要な課題の一つです。
企業がDXの本質を理解せず、単なるデジタル化と誤解している場合も少なくありません。また、既存事業の運営に多くのリソースを取られ、DXへの取り組みが後手に回ってしまうケースもみられます。
この課題を克服するには、経営陣のリーダーシップのもと、全社的なDX教育や啓発を行い、DXの重要性と本質的な意義を組織に浸透させることが不可欠です。同時に、既存事業とDX推進のバランスを取るための戦略的な資源配分も重要となります。
-
DXを進めるための5つのステップ
-
企業がDXを確実に前進させるためには、体系的なアプローチが不可欠です。前述の課題を踏まえたうえで、DXを効果的に進めていくための5つの具体的なステップを押さえておきましょう。
目的を明確化する
DX推進の第一歩は、明確な目的の設定です。まず、自社のビジョンを明確化し、それに基づいて現状を把握し、課題を洗い出す必要があります。
例えば、新たな顧客体験や新規ビジネスモデルの創出など具体的な目標を定めることが重要です。明確な目的設定は、その後のDX推進活動の指針となり、組織全体の方向性を統一する役割も果たします。戦略を立案する
目的が明確になったら、次はDXの具体的な戦略を策定します。このステップでは、自社の課題や目的を踏まえ、複数の戦略を検討することが重要です。
例えば、顧客データの統合と活用、業務プロセスの自動化、デジタルマーケティングの強化などさまざまな選択肢が考えられるでしょう。これらの候補に優先順位をつけ、段階的に実施していく計画を立てます。経営層の理解を得る
DXを成功させるためには、経営層の理解と支援が欠かせません。部署単位での取り組みでは、組織全体にかかわる根本的な課題に対処することが困難です。そのため、DXの目的や戦略を経営陣と共有し、その重要性を理解してもらわなければなりません。
経営層が積極的に関与することで、DXへの取り組みが組織横断的になり、必要なリソースを確保しやすくなります。人材と予算を確保する
DXの推進には、多大なリソースの投資が必要です。業務の片手間で効果的にDXを進めることは難しく、専門部署の立ち上げや専任担当者の任命が必要となるケースは多いでしょう。
社内に適任者がいない場合は、新規採用や人材育成、外部への委託も検討しなければなりません。
また、目的に合ったITツールや機器の導入・整備も不可欠です。短期的には大きなコストとなるかもしれませんが、長期的な視点では競争力強化や業績向上につながる投資となりえます。実行し効果測定を行う
準備が整ったら、策定した計画に基づいてDXの推進を実行します。実行後は、定期的に効果測定を行い、PDCAサイクルを回していくことが重要です。このときに具体的な成果指標を設定しておけば、進捗状況や成果を定量的に評価できます。
効果測定で得られた知見は、戦略や計画を修正し、継続的な改善を図っていくための貴重なデータとなります。持続的な成果につなげるためにも、効果測定とフィードバックを繰り返し、DXの取り組みを最適化していくことが重要です。
-
DXに活用される代表的なデジタル技術
-
効果的にDXを推し進めていくには、先進的なデジタル技術を理解し、適切に活用することが重要です。ここでは、幅広い分野のDXに活用されるクラウド、AI、IoTについて具体的に解説します。
クラウド
クラウドとは、インターネット上のリソースを必要に応じてサービスとして利用する仕組みです。クラウドを活用すれば、システムを一から構築する必要がなく、改修や運用にかかる時間を大幅に短縮できます。
また、データストレージなどのコンピューティングリソースを必要に応じて拡張・縮小できるなど、ビジネスの変化に迅速に対応できる柔軟性も大きなメリットです。
さらに、初期投資を抑えつつ、最新のテクノロジーを利用できる点も、DX推進において大きなアドバンテージです。AI(人工知能)
AIとは、人間の思考プロセスと同じような仕組みで動作するプログラム、および情報処理・技術全般を指します。AIのうち、人間の「学習」に相当する仕組みをコンピューターで実現する技術が「機械学習」です。
DXにおいてAIは、データ分析、予測モデリング(過去のデータやパターンを使って、未来の出来事や結果を予測するための分析)、自然言語処理などの分野で活用され、業務の効率化や意思決定の支援、顧客サービスの向上などに貢献します。
AIは今後も進化を続け、さまざまな製品やソリューションに組み込まれながら世の中に浸透していくと予想されています。IoT(モノのインターネット)
IoTとは、世の中のさまざまなモノに通信機能を組み込み、インターネットに接続することで自動認識や自動制御、遠隔計測などを行えるようにするネットワーク技術です。
例えば、工場でIoTの導入が進めば、工場の状況を離れた場所から情報システムを介してリアルタイムで把握できるようになり、労働力不足の解消が見込めます。
ほかにも、製造業での生産性向上や、スマートホームやスマートシティの実現、物流の最適化など、DXにおけるIoTの活用分野はさまざまです。
IoTによって、リアルタイムデータの収集と分析ができるようになれば、業務プロセスの改善や新たなサービス創出が可能となり、企業の競争力を大幅に高められます。
-
【業界別】DXの成功事例
-
DXの取り組みは、業界や企業によってさまざまな形で実践されています。主要な業界におけるDXの具体的な事例や、企業のDX成功事例を通じて、どのようなデジタル技術が活用され、どのような成果が得られているかをみていきましょう。
小売業
小売業界では、ECサイトの強化や実店舗のデジタル化など、オンラインとオフラインの融合を目指したDXが進んでいます。
例えば、セブン&アイ・ホールディングスでは、AIを活用した配送ルートの最適化と需要予測を組み合わせ、配送の最終段階である「ラストワンマイル」の効率化を実現しました。これにより商品の欠品を減らしつつ、配送コストを削減することに成功しています。
また、店舗のレジ業務においても、AIを活用した自動発注システムを導入し、在庫管理の精度向上と業務効率化を実現しています。
顧客満足度の向上と経営効率の改善を同時に達成したセブン&アイ・ホールディングスの取り組みは、小売業界におけるDX推進の先駆的な事例といえるでしょう。参考:株式会社セブン&アイ・ホールディングス「「DX銘柄2021」に初の選定」
株式会社セブン&アイ・ホールディングス「セブン&アイグループが目指すニューノーマル」製造業
製造業では、IoTの活用や予知保全(機器が故障する前に兆候や異常を検知すること)など、生産プロセスのデジタル化を推進しています。なかでも、製造業におけるDXの多面的な展開を進めているのが株式会社LIXILです。
LIXILは、AI音声認識を活用したオンラインショールームやリフォーム後の完成イメージを3Dで確認できるシステムなどを導入し、顧客とのコミュニケーションを革新しました。
これらのシステムにより、対面での接客が制限される状況下でも、製品の詳細な情報提供や購買決定のサポートを可能にしています。
また、コールセンターに自動音声認識技術を導入して生産性を高める取り組みや、生成AI技術導入により業務の質と効率を向上させる取り組みなど、取り組みは多岐にわたります。
専門性が高く、業務が属人化しがちな製造業においては、今後さらなるDXの取り組みが求められるでしょう。参考:株式会社LIXIL「デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組み」
この措置は、中小事業者を含めた一定規模以下の事業者の事務負担を軽減することが目的で、日常的な少額の経費処理において事業者の負担が大幅に軽減されます。ただし、以下の要件のいずれかに該当している場合が対象です。
金融業
金融業界では、オンラインバンキングやスマートフォンを利用した送金などに代表されるフィンテックの活用が進んでおり、顧客サービスのデジタル化が急速に進展しています。
そのなかでも注目されているのが、デジタルバンキング戦略を掲げるりそなホールディングスの事例です。
同社は、従来の銀行アプリの機能に加え、家計簿機能や資産管理機能、非金融サービスとの連携機能を統合したスマートフォンアプリを開発。顧客は日常的な金融取引だけでなく、ライフスタイル全般にわたるサポートを受けられるようになりました。
また、AIを活用した与信審査システムの導入や、ブロックチェーン技術(暗号化された取引履歴を多くのコンピューターで共有・確認することで、匿名性を保ちながらデータ改ざんを防ぐ技術)を用いた新しい金融サービスの開発など、最新のテクノロジーを積極的に検討しています。
金融業界のDXは着実に進展していますが、法規制への対応やセキュリティリスクの問題などの課題もあるため、業界全体でのさらなる変革が必要とされています。参考:株式会社りそな銀行「スマホがあなたの銀行に」
株式会社りそな銀行「ブロックチェーン技術を活用した新たな国内外送金業務の検討について」
-
まとめ|DXは企業変革を実現し未来への扉を開く鍵
-
DXは単なるデジタル化ではなく、企業の根本的な変革を促す重要な取り組みです。DXの推進は、業務効率化や顧客体験の向上、新たな価値創造を可能にし、企業の競争力強化につながります。
しかし、DX人材の不足やコストの問題など、多くの課題も存在します。これらの課題をクリアするためには、特定の部署だけが関与するのではなく、組織一体となってDXに取り組んでいるかどうかが重要です。
企業の特徴や価値観を詳しく知るうえでもDXの理解は欠かせません。ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。
就業・勤務 の関連記事
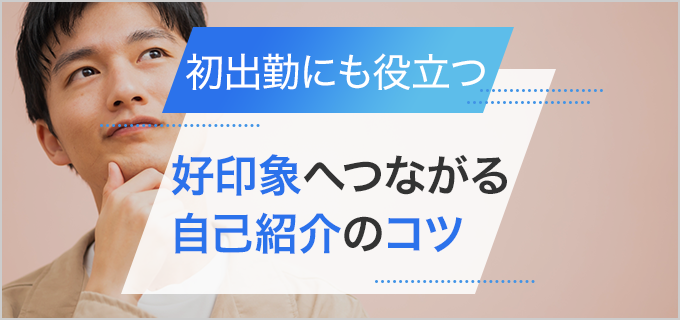
自己紹介|新しい人間関係のスタートで好印象を目指すためのアドバイスと例文

正社員じゃないからムリ?パートなら覚えておきたい産休・育休のあれこれ

バイト敬語要注意!アルバイトするなら正しい敬語を覚えよう

バイトなのに寝坊した!アルバイトに遅刻してしまったときのベストな行動

バイトのシフト入りすぎ?アルバイトに疲れたときの対処法とは?
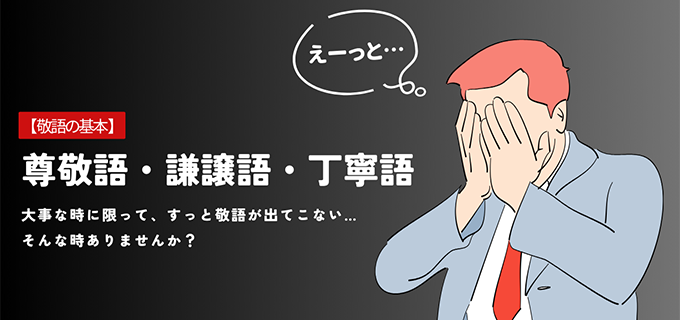
【敬語変換表あり】尊敬語・謙譲語・丁寧語の基礎
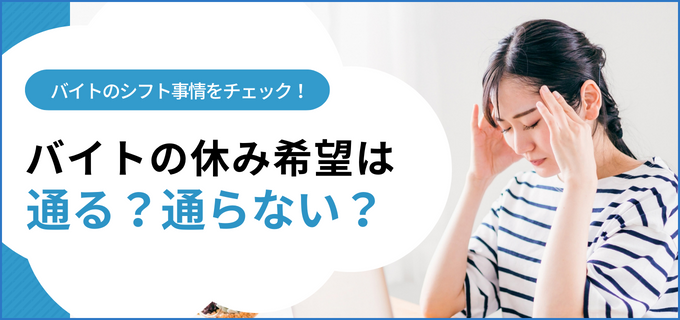
アルバイトのシフト事情!休み希望は通る?通らない?

意思の疎通が苦手な人必見!コミュニケーション能力向上のポイント

バイトに早く慣れるには?アルバイト先の先輩と早く仲良くなろう!
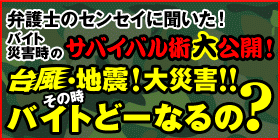
台風・地震!大災害!!その時バイトどーなるの?
カテゴリ一覧
-
派遣の仕事探し派遣の仕事探し
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書
- 自宅でできる仕事46選!スキルや趣味、得意分野を活かせる在宅ワークを見つけよう /バイト探し・パート探し
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート
- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!