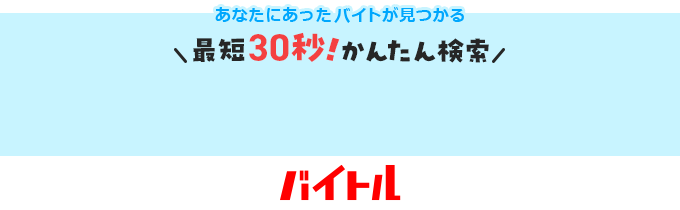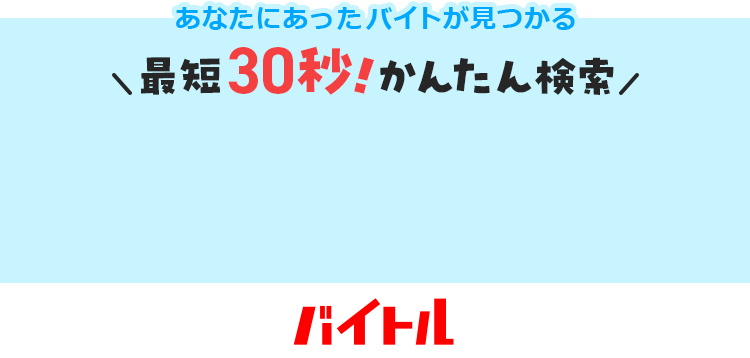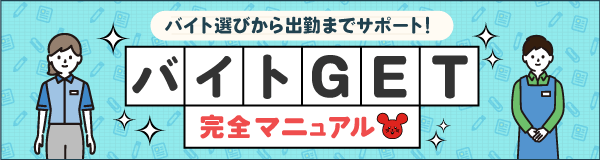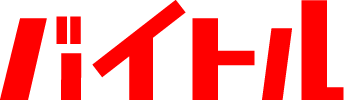2025年問題とは?どんな影響がある?問題点や今できることなどをわかりやすく解説
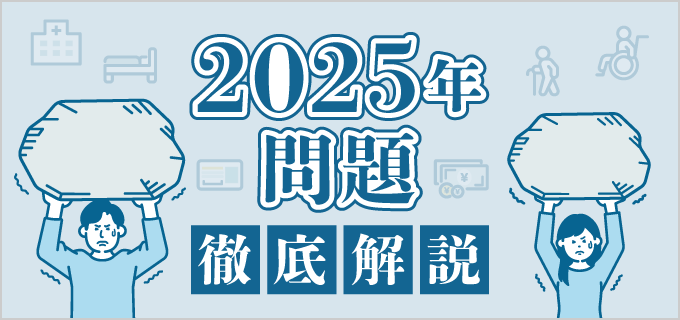
少子高齢化が加速することで浮き彫りになる「2025年問題」。ニュースで報道されているのを見て、「2025年問題とは?」「どんなことが起きるの?」と漠然とした不安を抱いている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、「2025年問題とは何か?」「誰に・どんな影響があるのか?」などについてわかりやすく解説します。これからの日本の動向について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
-
そもそも「2025年問題」とは?わかりやすく解説
-
■2025年問題とは
国民の5人に1人が75歳以上の後期高齢者になる超高齢化社会を迎えることで、雇用や医療・介護、福祉など日本経済や社会のあらゆる分野に深刻な影響をもたらす諸問題の総称。
背景には、急速に進む少子高齢化が挙げられます。
2025年は、第一次ベビーブーム(1947~1949年)に生まれた、約800万人の「団塊の世代」が75歳以上になります。約5人に1人が後期高齢者、3人に1人が65歳以上という構図が現実となり、以下の問題が深刻化すると見込まれているのです。
■高齢化が進んだ2025年の社会像- 高齢者人口の推移:高齢化率の「高さ」が問題化
- 認知症高齢者数:約675万人。65歳以上の高齢者のうち約5人に1人が認知症になると見込まれる
※参考:厚生労働省『認知症施策の総合的な推進について』 (2025年8月5日) - 高齢者世帯数:約1,840万世帯。約7割が1人暮らしか高齢夫婦のみ
- 年間死亡者数:約160万人(うち65歳以上約140万人)
- 都道府県別高齢者人口:首都圏をはじめとする「都市部」。高齢者の「住まい」の問題等、従来と異なる問題が顕在化。
総人口に占める高齢者人口の割合は、29.1%と過去最高を更新しており、社会保障費の増大や人材不足など多岐にわたる課題が懸念されています。
こうした状況下で、どのような備えをすれば将来のリスクを最小限に抑えられるかを考えるうえでも、「2025年問題」の正しい理解は欠かせません。
※参考:総務省『統計からみた我が国の高齢者』(2025年8月5日)「2025年の崖」とは?
「2025年の崖」は、2018年に経済産業省が提示した「DXレポート」に記載されたキーワードです。DX(デジタル変革)を十分に進めないまま2025年を迎えると国際競争力を失い、大きな経済損失が発生すると予測されています。
既存システムの老朽化や複雑化、人材不足などが要因となり、2025年以降は年間で現在の約3倍にあたる最大12兆円もの損失を被る可能性があるとされています。企業が新たな技術や組織改革に着手しない場合、市場での優位性を維持できなくなるリスクが高まるため、今から具体的な対応が求められているのです。
※参考:経済産業省『DXレポート』(2025年8月5日)「2030年問題」とは?
2030年問題は、高齢化に伴う人口減少が2030年頃に顕在化する社会問題の総称です。すでに医療・介護需要がピークに達するとみられる「2025年問題」に続き、さらに人材不足や地方の衰退、経済成長の鈍化といった課題が深刻化すると考えられています。
特に少子化による労働力不足が一段と進み、多くの企業で人材獲得競争や人件費の高騰が懸念されるでしょう。医療・介護の分野でもスタッフの確保が難しくなり、サービスの維持が厳しくなる可能性があります。
こうした流れを乗り越えるには、人口動態の変化を見据えた構造改革や、地方創生をはじめとする長期的な視点での対策が欠かせません。「2040年問題」とは?
2040年問題は、2025年問題をさらに深刻化させた超高齢化の課題とされています。2040年には団塊ジュニア世代(2024年時点で50~53歳になる世代)が高齢者になり、日本の高齢者人口が全体の約35%に達すると予測されています。
医療・介護の需要拡大や労働人口の大幅な減少など、多方面で社会構造の転換を迫られる見通しです。2025年問題だけでなく、さらに先の2040年を見据えた長期的な視点がなければ、企業の人材確保や社会保障制度の維持がいっそう困難になると考えられています。
今後は人口動態の変化を前提にした改革が不可欠であり、業界や規模を問わず各組織や個人レベルでもできることを進める必要があるでしょう。
※参考:総務省『統計からみた我が国の高齢者』(2025年8月5日)
-
2025年問題が与える社会への4つの影響
-
- 社会保障費の負担が増える
- 医療・介護の体制維持が難しくなる
- 後継者不足による廃業が深刻になり経済の縮小を加速させる
- ビジネスケアラーが増加する
社会保障費の負担が増える
高齢者向けの年金や医療、介護保険などにかかる社会保障費は、すでに全体の6割以上を占めています。2025年には団塊世代が一斉に後期高齢者となるため、さらに支出が増える見通しです。
現役世代の人口は減少傾向にあるため、限られた労働力で増大する社会保障費を支える構図が生まれます。医療や介護の費用拡大だけでなく、保険料負担も重くなりやすい点が問題視されており、国家財政や個人の家計に大きな影響を及ぼすことが懸念されているのです。
※参考:財務省『社会保障』(2025年8月5日)医療・介護の体制維持が難しくなる
高齢化にともなう患者や要介護者の増加に対して、医療スタッフや介護職員数の不足が深刻化するといわれています。厚生労働省の推計では、2026年には介護職員を約240万人確保する必要がある一方、実際の増員ペースは追いついていません。
看護師や介護福祉士の求人倍率も高止まりしており、人員を確保できない地域ほどサービスの質や提供体制の維持が難しくなるでしょう。特に後期高齢者が一気に増える2025年前後には、地域によって病床数や施設の空き状況に大きな差が生じ、医療・介護の格差拡大が懸念されています。
※参考:厚生労働省『第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について』(2025年8月5日)後継者不足による廃業が深刻になり経済の縮小を加速させる
中小企業庁の推計では、2025年までに70歳を超える経営者が約245万人に達する一方、約127万人は後継者が未定とされています。経営者本人の引退により、事業継続が困難となる「黒字廃業」が増えれば、累計で約650万人の雇用と22兆円のGDPが失われる可能性があるのです。
貴重な技術やノウハウまで消滅するリスクを抑えるには、早めの後継者育成や事業承継型M&Aの検討が不可欠です。後継者不足を放置すれば、地域経済のみならず全国規模での景気後退を招きかねないため、あらゆる業種・企業が計画的な対応を進める必要があります。
※参考:中小企業庁『中小企業・小規模事業者における M&Aの現状と課題』(2025年8月5日)ビジネスケアラーが増加する
ビジネスケアラーとは、家族の介護が必要になっても働き続ける就労者のことです。2025年問題の一つとして話題になっています。
経済産業省の推計では、ビジネスケアラーは2020年に約262万人に達し、2012年から8年間で50万人以上増えました。団塊世代が後期高齢者となる2025年以降は、さらに増える見込みです。
介護の負担が増すと労働時間の確保が難しくなり、従業員の離職や生産性の低下につながるリスクが高まります。実際に、経済産業省の試算では、2030年時点で仕事と介護の両立が困難になることによる経済的損失が約9.1兆円に達すると推定されています。
※参考:経済産業省『令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業 (サステナブルな高齢化社会の実現に向けた調査)報告書概要』(2025年8月5日)
-
2025年問題が企業に与える影響
-
2025年問題は、企業にも以下のような影響があるとされています。
- 人材不足が深刻になる
- 既存システムの維持が企業の成長を妨げる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
人材不足が深刻になる
2025年問題が企業に与える影響の一つとして、労働人口の現象の深刻化が挙げられます。
特にサービス業や医療・福祉分野では人手確保が難しく、前述の通り人手不足による倒産も増加する見込みです。労働力不足が続くと、事業継続が困難になるだけでなく、市場全体の活力低下につながるリスクが高まります。
企業は早期に人材育成や採用戦略を見直し、多様な働き方を整備するなどして、深刻な人手不足に対応していく必要があるでしょう。既存システムの維持が企業の成長を妨げる
旧来のシステムを抱える企業では、サポート切れによるセキュリティリスクの増大や、運用コストの増加が避けられないとされています。経済産業省のレポートによれば、2025年を境に技術的サポートが終了するケースが増え、最大12兆円にのぼる経済損失が発生する恐れもあるようです。
既存システムに依存し続けると、新たなサービス開発や市場拡大のチャンスを逃し、人材流出や競争力の低下といった問題が顕在化しやすくなります。企業が持続的に成長するためには、既存システムの見直しや刷新を進め、DXを阻む要因を早期に解消することが不可欠です。
-
【業界別】2025年問題で生じる課題も要チェック
-
2025年問題は業界別に生じる課題があります。ここでは、2025年問題にフォーカスした以下の業界の動向を見ていきましょう。
IT・情報サービス業界
IT人材の需要は急増しているにもかかわらず、不足していく一方であるといわれています。経済産業省の調査(2019年)では、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると試算されています。
※参考:経済産業省『IT人材需給に関する調査(概要)』(2025年8月5日)
エンジニアが不足すれば、システム刷新や新規開発の遅延が続き、企業の競争力が落ち込むリスクが高まるでしょう。こうした状況を回避するには、現場の技術者を守る環境づくりや多様な人材の採用を含め、長期的なスキル継承と組織改革を積極的に進めることが求められます。
※参考:経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課『IT人材育成の状況等について』(2025年8月5日)保険業界
保険会社にとって、契約者の高齢化は保険金支払いの頻度や金額の増加を意味します。一方で、若年層の人口が減ることで新規顧客の獲得が難しくなり、収益構造の見直しが迫られるでしょう。
加えて、医療技術の進歩や多様なニーズに合わせて商品を柔軟にアップデートする必要があり、人件費の抑制や顧客サービスの向上を両立させるのは容易ではありません。
こうした環境下で保険業界が市場規模を維持するには、集客・サービスのオンライン化を進めながら、高齢者やその家族に向けた新しい商品・サポート体制を構築することがポイントになるでしょう。飲食業界
長時間労働と低賃金が常態化している飲食業界は、2025年以降さらに人材不足が深刻化すると見込まれます。若年層の減少や働き方改革の影響で、バイトや正社員を安定的に確保するハードルが上がるでしょう。
加えて、高齢者人口の増加にともない健康志向や宅配ニーズが拡大する一方、仕入れコストや人件費の上昇も予想されます。こうした環境で飲食業界の売上を保つには、人材定着を重視した労働条件の改善や、デジタル技術を活用した業務効率化が不可欠です。医療・介護業界
高齢者人口の急増にともない、医療・介護サービスの需要は一層高まると考えられます。そのため、看護師や介護職員などの人材不足に拍車がかかり、病院や介護施設ではスタッフ一人ひとりの負担が増大する可能性が高いでしょう。
外来や入院患者数の伸びに加え、訪問看護や在宅介護のニーズも急増し、ベッドや施設枠が足りない地域が増えるリスクがあります。この状況に対応できないままでは、医療の質や介護サービスの安定供給が揺らぎ、利用者の生活の質に影響が及びかねません。
国や自治体による財源確保や人材育成の強化はもちろん、事業者自身も働きやすい環境整備や職員定着策を早期に講じる必要があるでしょう。建設業界
人材の高齢化と若手の減少が進む建設業界では、2025年以降に専門技術を継承する担い手がさらに不足することが懸念されています。国土交通省の調査によると、建設業界における従事者数はピーク時と比べて大幅に減り、55歳以上が従業員の3割以上を占める状況です。
また、業務の多くはアナログ作業に依存しているため、生産効率が低下しやすい構造が続いています。今後はこうした課題を解消するうえで、現場でのデジタルツール活用や省人化に向けた取り組みが重要視されるでしょう。
若年層や女性、外国人労働者にとって魅力的な職場環境を整備することも、高齢化を見据えた建設業界の最優先事項となりつつあります。
※参考:国土交通省『建設業を巡る現状と課題』(2025年8月5日)運送業界
長時間労働が常態化しやすい運送業界は、若年層人口の減少やドライバーの高齢化で人材確保が難しくなっています。さらに、2024年から自動車運転業務に対する残業規制が本格施行されるため、一人ひとりの就業時間に上限が設けられる状況です。
これまで長時間労働で補ってきた配送量を維持するには、ドライバーの増員や配送ルートの効率化が不可欠ですが、求人数が増える一方で若年層が不足しているのが現状です。
小口配送ニーズが拡大するなか、新たな雇用対策やシステム導入で生産性を高め、労働環境を改善する取り組みが不可欠となっています。
※参考:厚生労働省『統計からみる運転者の仕事』(2025年8月5日)
-
2025年問題を乗り越えるための国の対策
-
社会保障体制の見直し
2025年以降に社会保障費が急増する見通しから、社会保障体制の見直しとして以下の対策が取られています。
- 地域完結型の医療・介護システムの構築
- 高齢者の医療費負担の見直し
- 高齢者の就労促進
2022年10月には、一部の後期高齢者の自己負担割合が引き上げられ、負担の公平化を図る措置が実施されました。
あわせて、介護や予防、生活支援を住み慣れた地域で包括的に提供する仕組みづくりも推進されており、医療・介護サービスの重複やムダを削減して財政負担を和らげる狙いがあります。
また、2021年の法改正では企業に70歳までの就業確保策を求め、意欲のある高齢者が働き続けられる環境づくりを促しています。こうした施策により各世代間の負担をバランスよく分散し、社会保障制度の持続可能性を高めようとする動きが強まっているのです。介護人材の確保
厚生労働省の見通しでは、2025年には介護人材が20万人以上不足するとされており、介護人材の確保を進めています。こうした状況を緩和するために、未経験者が介護業界へ入りやすくなる入門的研修が各地で実施されています。
さらに、子育てや家族の介護と両立しやすい雇用形態をモデル導入し、効果が認められれば全国へ展開する取り組みも始まっているのです。
ほかにも、介護ロボットやICT技術を活用して身体的・事務的負担を軽減する仕組みづくりを進めるなど、離職を防ぐ工夫も重要です。賃金アップや働きやすい環境づくりなど多角的な施策を強化し、多様な人材が長く働ける介護現場を目指すことが急務となっています。企業へのDX推進
少子高齢化にともなう人手不足への対策として、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が急速に注目されており、国を挙げて取り組むべき課題とされています。
たとえば、経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード2.0」は、企業がDXを導入する際の基本指針を示すもので、注目を集めています。
中小企業向けにも手引きがまとめられ、地域別の説明会を通じて具体例が共有されました。これらの取り組みにより、人材不足を補う省人化や生産性の向上につながり、社会保障費の負担増を緩和しながら、持続可能な経済基盤の構築を目指す狙いがあります。地域包括ケアシステムの構築
高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられる仕組みとして、政府は地域包括ケアシステムの整備を推進しています。この体制では、住まいや医療、介護、予防、生活支援を総合的に提供し、個々のニーズに沿ったケアを実施するのが特徴です。
具体的には、各市町村が3年ごとの介護保険事業計画を策定し、地域包括支援センターなどを通じて在宅看護や生活支援サービスを連携させています。地域包括ケアシステムの構築の構築により、重度の介護が必要になっても病院や施設ではなく、安心できる地域環境のなかで暮らせる可能性が高まるでしょう。
今後も自治体や民間事業者が地域特性に応じた運営モデルを整え、多職種連携を強化していくことが鍵となります。
※参考:厚生労働省『地域包括ケアシステム』(2025年8月5日)
-
2025年問題に向けて私たちに今できること
-
2025年問題は深刻で大きな課題ですが、個人レベルでもできることがあります。その例として、以下の3つを取り上げました。
- 健康管理を徹底して元気に長生きする
- 家族や地域のコミュニティと連携する
- スキルを習得してキャリアアップをめざす
今何ができるのかを知るためにも、ぜひ参考にしてみてください。
健康管理を徹底して元気に長生きする
元気に長生きすることは、今できることの一つです。特に、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を指す「健康寿命」に着目するとよいでしょう。健康寿命を延ばす取り組みは、社会保障費の増大を抑えるほか、人生を豊かにするうえでも重要です。
国は2040年までに男女とも健康寿命を3年以上に伸ばす目標を掲げています。食生活や運動、睡眠などの基本的な習慣を見直すことが第一歩になるでしょう。
ほかにも、地域コミュニティへの参加など「孤立しない」暮らし方を心がけると、心身のケアや認知機能の維持に役立つとされています。日々の小さな積み重ねにより、自分らしく長く活動できる社会を目指すことが、2025年問題への個人レベルの対策につながるのです。
※参考:厚生労働省『健康寿命延伸プラン』(2025年8月5日)家族や地域のコミュニティと連携する
高齢者が増える社会では、公的サービスだけでなく、家族や近隣との助け合いも大切です。たとえば、一人暮らしの高齢者には定期的に声をかけ、地域の見守り活動に参加するだけでも大きな支援になるでしょう。
健康に生活する高齢者にはボランティアや地域活動を通じ、支援する側としての役割を担ってもらうのも効果的です。身近な人との関わりを大切にすることで、孤立や孤独感の軽減につながります。
個人個人が家族やコミュニティ内で協力しあうことで、支え合いながら暮らせる持続可能な社会に近づけるでしょう。スキルを習得してキャリアアップを目指す
スキルを身につけてキャリアアップすることも、2025年問題に向けた個人の取り組みのひとつです。労働人口が縮小するといわれるなか、1人1人の生産性のアップが国力を支える原動力となるでしょう。
「リスキリング」という言葉が話題になっており、大人になってから学び直す人が増えているのも事実です。
スキルアップは、多様な働き方が浸透するなかで、自分らしく生きるための選択肢を増やすことにもつながります。仕事に活かせる知識の習得方法は、副業やバイトを通じて実務経験を積む、オンライン講座を利用するなど多岐にわたります。今の仕事と両立しながらスキルアップを図り、柔軟なキャリア形成をめざしましょう。
-
まとめ|2025年問題について理解を深めて今できることをしよう!
-
2025年問題は、高齢化による社会保障費の増加や医療・介護の人材不足、人手不足倒産の増加といった幅広い影響をもたらします。本記事では、社会保障費の負担増から企業の課題、業界別の動向、さらには個人が今から備えられる対策まで網羅的に紹介しました。
ポイントは、まず正しい理解を深め、個人レベルで今できることを知るところにあります。自分自身の健康を保ち、周囲と助け合いながらスキルを磨けば、この変化の激しい時代でも柔軟に対応できるはずです。
2025年問題は避けられませんが、未来をより明るいものにする可能性を高めるためにも、現状とこれからの動向を押さえておきましょう。
就業・勤務 の関連記事
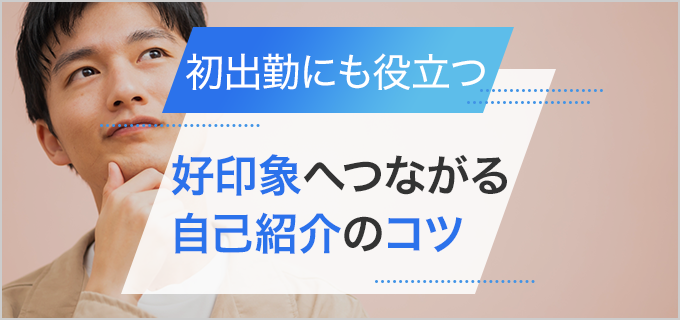
自己紹介|新しい人間関係のスタートで好印象を目指すためのアドバイスと例文

正社員じゃないからムリ?パートなら覚えておきたい産休・育休のあれこれ

バイト敬語要注意!アルバイトするなら正しい敬語を覚えよう

バイトなのに寝坊した!アルバイトに遅刻してしまったときのベストな行動

バイトのシフト入りすぎ?アルバイトに疲れたときの対処法とは?
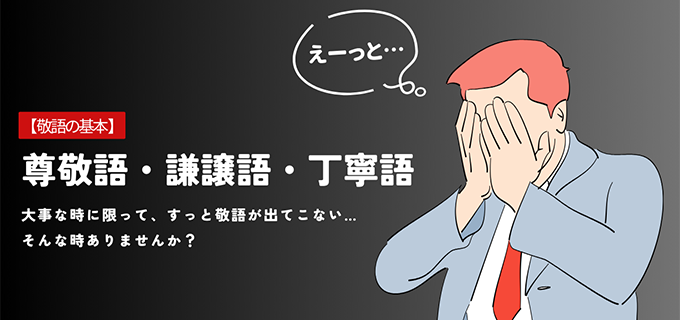
【敬語変換表あり】尊敬語・謙譲語・丁寧語の基礎
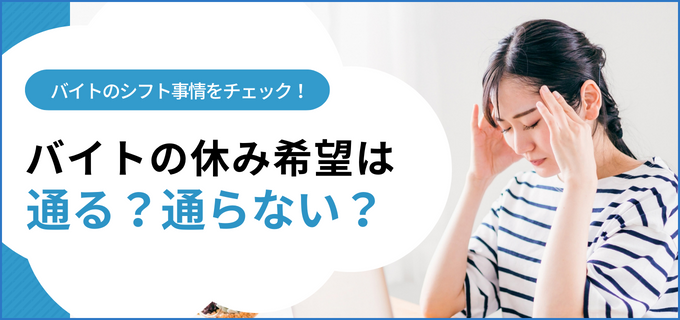
アルバイトのシフト事情!休み希望は通る?通らない?

意思の疎通が苦手な人必見!コミュニケーション能力向上のポイント

バイトに早く慣れるには?アルバイト先の先輩と早く仲良くなろう!
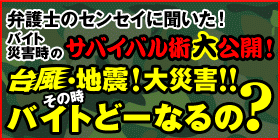
台風・地震!大災害!!その時バイトどーなるの?
カテゴリ一覧
-
派遣の仕事探し派遣の仕事探し
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書
- 自宅でできる仕事46選!スキルや趣味、得意分野を活かせる在宅ワークを見つけよう /バイト探し・パート探し
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート
- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!