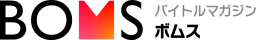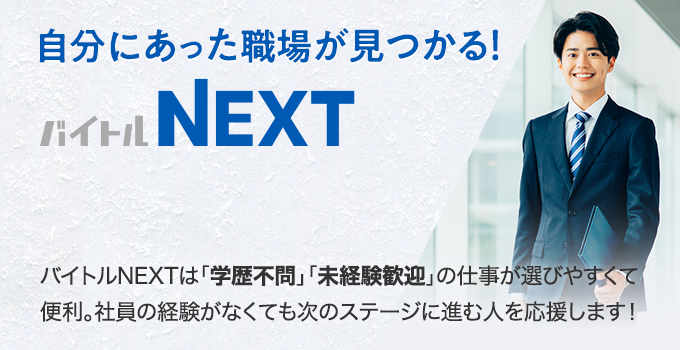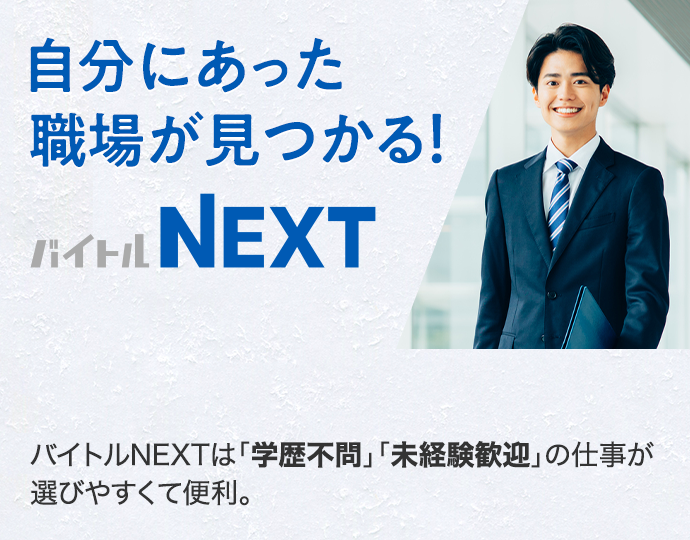転職や失業で「雇用保険被保険者番号」は変わる?必要になるシーンや調べ方も紹介!

雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者番号は、日常生活ではほぼ目にすることがありません。どのような場面で使用するのでしょうか?またどのように活用することができるのでしょうか?
名前にある通り、多くの人が加入している「雇用保険」に関わるものですが、ここでは雇用保険被保険者番号について詳しく解説します。転職にも関わってきますので、これから転職を検討している人も、ぜひ最後まで目を通してみてください。
目次
-
雇用保険被保険者番号とは
-

雇用保険被保険者番号とは、雇用保険加入時に一人ひとりに割り当てられる、11桁の番号です。雇用保険被保険者証などに記載されています。
- ● 1週間の所定労働時間が20時間以上
- ● 31日以上継続して雇用される予定である
- ● 雇用保険の適用事業所に雇用されている
以上が雇用保険の加入条件ですが、学生は原則として対象外です。
雇用保険は、雇用の継続が困難になったときの労働者のセーフティーネットの役割りを果たします。
労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、生活と雇用の安定を図り、再就職への様々なサポートを行うことを目的とした制度です。雇用保険被保険者番号が必要なシーン
雇用保険被保険者番号が必要になるのはどのような場面でしょうか?
ここではそれぞれの場面について紹介します。転職
雇用保険被保険者証には以下の内容が記載されています。
- 雇用保険被保険者番号
- 雇用保険を申請した社名
- 資格取得日
- 保険者名
- 年月日
転職して新しい会社でも引き続き雇用保険に加入する際には、原則として同じ番号で申請します。そのため、転職先で雇用保険被保険者証の提出を求められます。
原本がない場合はコピーでも提出できます。入社日までに紙面で用意できない場合は、上記の内容を担当者に伝えましょう。失業保険(雇用保険の基本手当)の手続き
失業中に、雇用保険の失業等給付のひとつである「基本手当」を受給する場合、その申請にも雇用保険被保険番号が必要になります。
ただし、手当を受け取るには条件もあり、一般的には離職する前2年間で雇用保険への加入期間が通算12か月以上あること、就職する意思と能力がある事などがあげられます。
雇用保険被保険者証を紛失した場合はハローワークで再発行する必要があります。
万が一被保険者番号が確認できず、新しい被保険者証を発行することになった場合、それまでの加入年数のデータは引き継がれません。加入期間が少なくなるため、失業等給付の申請条件を満たさない、受給内容が変わるなどの可能性があります。保険被保険者証の保管には十分注意しましょう。教育訓練給付の手続き
雇用保険に3年(初回は1年)以上加入している在職中の人や離職をした人は、教育訓練給付金を受給できます。
これは「雇用の安定と就職の促進を図る」ためのスキルアップに、厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した場合、受講料の一部(最大50%、年間上限40万円)が支給される制度です。
この制度はハローワークに雇用保険被保険者証を提示して申請して利用できます。在職中の人は会社の担当者に事情を説明し、保険者証を受け取りましょう。
-
雇用保険被保険者番号が変わることはある?有効期限は?
-

基本的に1人に1つの番号が割り振られ、職場が変わっても継続して同じ番号を使用できることがお分かりいただけたと思います。
では雇用保険に入らない場合や、番号が変わるケース、有効期限などはあるのでしょうか?原則番号は変わらない
基本的に、一番初めに雇用保険に加入した際の番号をその後の勤務先でも使い続けるため、雇用保険被保険者番号が変わることは原則ありません。
番号が記載されている雇用保険被保険者証は、普段は会社が保管していることが多いので、あまり手にする機会がなく重要に感じられないかもしれません。
しかし先に説明した通り、失業手当や教育訓練給付金の申請に不可欠な書類です。紛失や破棄しないように、手元に来た際には大切に保管しましょう。番号が変わるケース
ここまで「原則的に」同じ番号を使い続けると説明してきましたが、その例外となる場合を説明します。
雇用保険から外れて最後の離職日から7年経過すると、この雇用保険被保険者番号は失効し利用できなくなる、と定められています。
つまり専業主婦 / 主夫、フリーランスなどに転身してから7年以上経てから雇用保険に入り直すと、別の新しい番号を受け取ることになるのです。
-
雇用保険被保険者番号の調べ方
-
実際に自分の番号を確認するにはどのような方法があるのでしょうか?
ここでは、雇用保険被保険者証などの証明書で確認する方法と、証明書が手元にない場合について紹介します。雇用保険被保険者証か離職票で確認
雇用保険被保険者証は会社の担当者が申請したのち、多くの場合会社が保管しています。
そのため、発行された後に担当者に頼めば確認することができます。雇用保険被保険者番号は「4桁+6桁+1桁」の11桁で記載されています。
また離職票でも確認することが可能です。離職票は個人が会社を離職したことを証明する書類です。退職時に会社が手続きをしてハローワークから発行されるものなので、勤務先が変わらない限り目にすることはありません。
通常確認するには雇用保険被保険者証で充分でしょう。雇用保険被保険者番号が分からない時は?
万が一、手元に被保険者証や離職票がなく、番号が必要になった際は、以下の4つの方法で番号を確認することができます。
- 転職時は勤めていた会社に連絡して確認する
一般的には退職のタイミングで受け取ることができますが、渡し忘れなどが発生して手元に書類がない場合は直近の勤務先に問い合わせましょう。新しい会社で雇用保険に加入する為に必要になります。 - 雇用保険受給資格証で確認する
すでに失業時の基本手当の受給手続きを行っていて、番号が確認できる証明書が手元にない場合、手続き後に行う「雇用保険受給説明会」で受け取る雇用保険被保険者証で確認できます。 - 居住地管轄のハローワークで雇用保険被保険者証を再発行してもらう
紛失などで手元にない場合は、ハローワークで再発行できます。再発行については次の項目で説明します。 - 在職中は担当者に問い合わせ
在職中に教育訓練給付金を申請する場合は、手元に証明書は来ませんので、人事部へ問い合わせ確認できます。
- 転職時は勤めていた会社に連絡して確認する
-
ハローワークでの雇用保険被保険者証の再発行方法
-
大切な雇用保険被保険者票を紛失・破棄してしまった際は、ハローワークの窓口で無料で即日再発行することができます。
再発行はどの地域のハローワークでも申請が可能です。
再発行に必要な書類は以下の通りです。- 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、写真付き住民台帳カード)
- 勤務先名や本社所在地、電話番号がわかるもの
- 雇用保険被保険者証再交付申請書
上記以外にも、事業所が手続きを行う場合には代表者印が必要になります。(本人が手続きする場合には印鑑は不要です。)また、代理の方が申請する場合は、「委任状」、「代理人の本人確認書類」、「ご本人の本人確認書類」が別途必要になります。
勤務先は、在職中なら現在の勤務先を記入し、離職中ならば最後に勤務していた勤務先の情報を記入します。
雇用保険被保険者証再交付申請書は窓口で貰うか、事前にホームページからダウンロードして記入して持参しましょう。
-
混同しやすく整理しておきたいポイント
-

社会保障に関する番号や書類はいくつもあります。私たちの生活に直結している大切なものです。各種手続きで混乱しないように気を付けましょう。
「雇用保険被保険者証」と「離職票」
「雇用保険被保険者証」と同様に、雇用保険被保険者番号が記載されている「離職票」ですが、この2つは必要になる場面が異なります。
離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。前述のように、個人が会社を離職したことを証明する書類です。
退職日の翌日から10日以内に、会社から事業所管轄のハローワークへ「雇用保険資格喪失届」「離職証明書」が提出され、その後ハローワークから会社へ「雇用保険被保険者離職票」が発行されます。
離職票は再発行が可能で、会社には従業員の退職から4年間の保管義務があります。
離職票は2枚からなり、基本手当の手続きの際「離職票-1」に手当の振込先口座を記入し提出します。一方「離職票-2」には、退職した理由などが記載されており、受給資格や受給内容をハローワークが判断するために必要です。
つまり「雇用保険被保険者証」は再就職の際に必要になる証明書、「離職票」は失業中の手当を受け取るために必要な書類です。「雇用保険被保険者番号」と「被保険者整理番号」
「被保険者整理番号」は健康保険と厚生年金保険の加入手続き・内容変更の際に発行されます。
健康保険と厚生年金の2つがそれぞれ別の番号のことも共通の場合もありますし、番号は事業主の任意で割り振られるため、転職すると番号が変わります。
厚生年金被保険者整理番号は資格取得届の控えなどで確認するしかなく、従業員が必要とする際には事業主に確認する必要があります。
健康保険被保険者整理番号は病気や怪我による傷病手当の申請、医療費の払い戻しなどに必要になります。健康保険証に記載があるので確認しておきましょう。「雇用保険被保険者番号」と「マイナンバー」
マイナンバーは平成28年から導入された、行政手続きなどにおける個人を識別するための番号です。カードは個人で申請して発行することができ、日本国内に住民票がある人全員に12桁の番号が割り当てられます。
情報漏洩した場合を除き、個人の番号は一生変わらないとされています。
2018年5月以降、雇用保険被保険者資格の申請や脱退の際に、マイナンバーの記載が必要になっています。「雇用保険被保険者番号」と年金手帳の「基礎年金番号」
基礎年金番号は日本年金機構から国民一人一人に割り振られた、国民年金や厚生年金保険、共済組合の公的年金制度で使用される10桁の番号です。
それ以前は加入する制度が変わるたび、国民年金、厚生年金保険、共済組合とそれぞれの番号を持つ形でしたが、現在は制度を超えて共通する番号が支給されます。
雇用保険被保険者番号と異なり、一度決まった番号から変更されることはありません。ねんきん定期便や基礎年金番号通知書で調べられます。
-
まとめ:雇用保険被保険者番号は失効後の再加入で変わる!再発行できますが紛失には十分注意しよう!
-
雇用保険の仕組みを理解しておくと、在職中から活用することが可能です。雇用保険被保険者証をしっかり管理し、転職や求職のいざという時、手当てが利用できない!という事態にならないよう気を付けましょう。
バイトルNEXTには様々な企業の求人情報があります。転職を考えている方や、現在離職中で就職活動をされている方もぜひ一度、どのような求人があるのか覗いてみてください。
バイトルNEXTは、あなたのお仕事探しを応援しています!【関連記事】
失業保険手続きの流れと受給要件・もらい方とは?手続きを忘れたらどうする?
雇用保険受給資格者証ってなに?いつどうやってもらえる?見方やよくある質問を紹介
初めてでも大丈夫!ハローワークでの相談や基本手当(失業保険)受給手続きの流れを解説!
退職時にもらう書類・返却するもの、転職先に提出する書類を紹介!
【社労士監修】離職票とは?離職票のもらい方を徹底解説!もらえない時の対処法を紹介
採用証明書とは?ハローワークへ提出?採用証明書が必要なケースや書き方などを解説!
【社労士監修】離職証明書はダウンロード不可!ハローワークで受け取ろう
退職後の手続きチェックリスト!退職後に行うべき手続きの期限や場所とは
ハローワークの持ち物を場面別に紹介!初回や雇用保険手続きのときは?どんな服装?
【社労士監修】失業保険(雇用保険の基本手当)の延長申請は可能!注意点などを解説
年金手帳は退職時に忘れずに返却してもらおう!無くしてしまった時の対処法もご紹介!
ハローワークの認定日は指定の時間しか手続きできない?指定日時に行けないときは?
職安とは?ハローワークとは違う?受けられるサービスや利用の流れ、メリットも紹介!
ハローワークで相談できることとは?職業相談ってなに?電話では相談できない?記事監修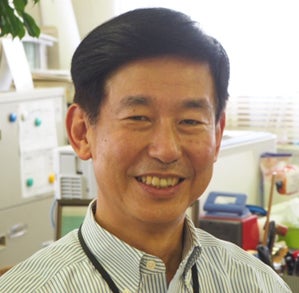
荒武 慎一(あらたけ しんいち)
社会保険労務士、中小企業診断士
昭和53年同志社大学卒業、富士ゼロックス株式会社を経て平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金をわかりやすく解説することで高い評価を得ている。(連絡先:0422-90-9990)
さっそくお仕事を探してみよう
社員の仕事探し・転職 の関連記事

アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説

製造業とは?就職・転職の検討に使える主な職種や仕事内容・メリット・デメリットなどの情報を解説!

建築・土木ってどんな仕事?仕事内容や現場の声、求人の探し方について紹介
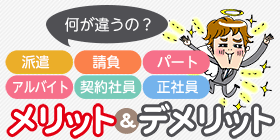
何が違うの?働き方の違いメリット&デメリット|派遣・請負・パート・アルバイト・正社員
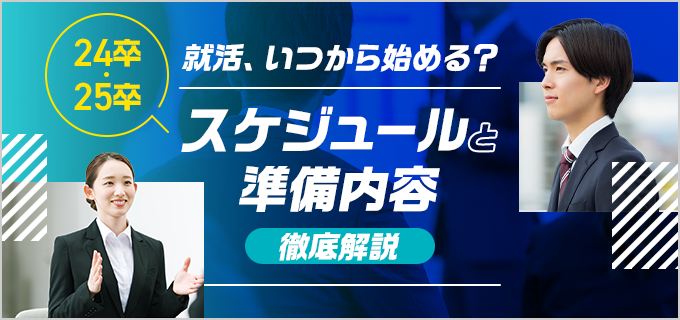
【24卒・25卒】就活はいつから?流れや準備時期を徹底解説

バイトルNEXT 適職診断
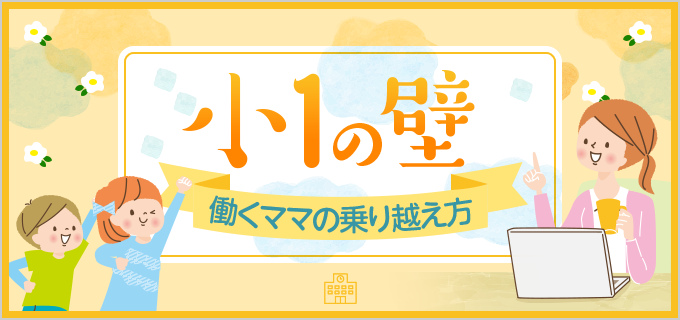
小1の壁を乗り越える!困るポイントと対策、働き方を解説
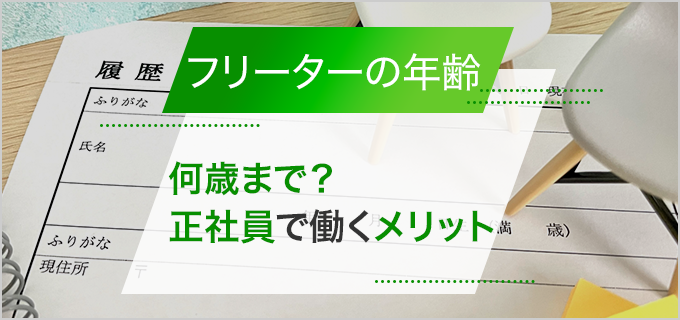
【アンケート】何歳までフリーターを続ける?就職はいつまでにするべき?

NEW中卒の就職は難しい?就職率や男女別おすすめの仕事・資格・職種まで紹介!

内定承諾の返事は電話?メール?連絡する際のマナーを例文付きで紹介
カテゴリ一覧
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 【2023年】最低賃金は全国平均で1,004円、最大で47円の引き上げ|最低賃金を下回っていた場合の対処法 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- アルバイト面接の前日メールはどうやって返信する?マナーやポイント、例文を解説! /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- バイトルCMとの連動企画#はないちもんめチャレンジの受賞作品大公開 /プロモーション
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート