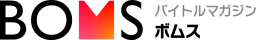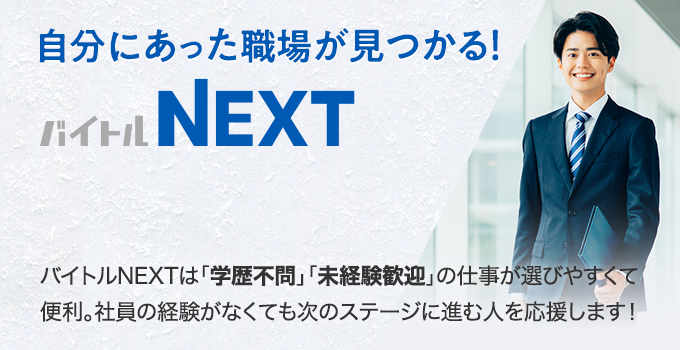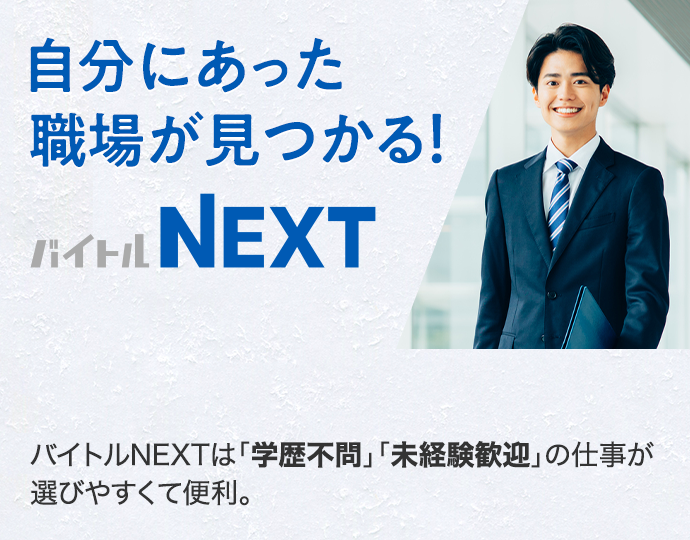初めてでも大丈夫!ハローワークでの相談や基本手当(失業保険)受給手続きの流れを解説!

ハローワークとは、国が運営する公共職業安定所の通称です。
ハローワークでは就職や転職に関する無料相談や、雇用保険(失業保険)の基本手当の受給手続きを行うことができます。
また、職業相談で求人の紹介や就活に関する相談を受けると、求職活動としての実績になります。
この記事では、ハローワークでできる職業相談や、失業保険の受給手続きの流れについて解説しています。
行く際に必要な持ち物や服装、利用方法の流れについても紹介していますので、これから初めてハローワークに行くという人は参考にしてみてください。
目次
-
ハローワークでできること
-
ハローワークでできることは、地域の求人情報の照会や職業相談だけでなく、失業保険受給のための手続きや、職業訓練の申込みなどいくつかあります。
ひとつずつ確認して、自分に合った利用方法を選びましょう。※この記事では、雇用保険の失業等給付のひとつである「基本手当」のことを、俗称で「失業保険」と呼ぶことが多いことから、わかりやすく「基本手当」のことを「失業保険」と呼んでいます。
求人情報の検索と職業相談
ハローワークは地域密着型の職業案内所として利用することができます。施設内に設置されているパソコンで様々な求人が検索できます。
窓口で職業相談の申込みをすれば、就職活動におけるさまざまな相談をすることができます。
職業相談では、履歴書や職務経歴書の書き方の指導や添削や、面接で失敗しないコツなどのアドバイスを受けることができます。
また、自分の適性に合った職業を調べたり、就職活動前に職業訓練を受けるべきかの確認もできます。
求人票の情報確認で、就職した人の定着率や現在どんな人が応募しているのか、未経験者でも応募可能か、といった状況について可能な範囲で調べてもらうことや、就職後、実際にもらえる給与額や賞与額の計算をしてもらうこともできます。失業保険(基本手当)受給の手続き
失業保険の受給については、給付を受けるための条件を全て満たしていなければなりません。
1つ目の条件は、就職しようという積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があり求職活動を行っているにも関わらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就けない「失業状態」であることです。
2つ目の条件は、退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上あること、つまり、一定期間以上雇用保険に加入している必要があります。
3つ目の条件が、ハローワークに求職の申し込みをしていることです。
自分の住んでいる地域を管轄するハローワークで、受付票に、氏名、住所、経歴および就職の希望条件などを記入して提出して求職の申し込みを行います。
このように、失業保険を受け取るためにはハローワークでの手続きが必須となります。公的職業訓練
希望の企業に就職するための必要なスキルを身に付けるためには、セミナーや通信講座などお金がかかることが多いです。
ハローワークでは、条件に該当する人に無料の職業訓練を行っています。
職業訓練には、失業保険を受給している人向けの「公共職業訓練」と、受給していない求職者向けの「求職者支援訓練」の2種類があります。
さらに、複数の条件を満たせば職業訓練を受けながら、給付金(職業訓練受講給付金)を受けることも可能です。
条件には、本人の収入が月8万円以下であることや、同世帯で同時にこの給付金を受給している人がいないことのほか、世帯全体の収入や金融資産についての制限があります。
また、訓練実施日にすべて出席することや、過去3年以内に虚偽や不正行為で特定の給付金の支給を受けていないことなどがあります。
詳しくは、ハローワークで確認すると良いでしょう。
-
初めてハローワークを利用する際の流れ
-

以下、初めてハローワークを利用する際の一般的な流れと各段階についてのポイントや注意点を解説します。
ハローワークの所在地や営業時間を確認したら、忘れ物がないように気をつけて現地で手続きを行いましょう。持っていくと良いもの
ハローワークで何か手続きをする目的でなければ、基本的には何も持っていかなくても大丈夫です。
ただし、初回の登録時には求職情報を登録するために、学歴や資格情報を記入する必要があります。
また、気になる求人があればハローワークを通して申込みを行うため、面接スケジュールなどについては自分の予定と合わせて確認することになります。
そのため、筆記用具と履歴書、職務経歴書、スケジュール帳などは持っていくと良いでしょう。窓口で求職申し込み手続きを行う
申し込みでは、学歴や自己PR、職歴や希望する職種など、複数の項目があります。
求職登録は、事前にハローワークインターネットサービスから仮登録をしておくと、当日の手続き時間を短縮することができます。
最初の登録時には所轄のハローワークへ足を運ぶ必要がありますが、とりあえず登録だけしておいて、利用するタイミングになったら行くということや、在職中でも転職準備として登録だけ先にしておくということも可能です。ハローワークカードを受け取る
仮登録した求職情報をハローワークの職員が確認して、受理されるとハローワーク受付票という書類を受け取ることができます。
ここまでの手続き時間の目安は30分~1時間程度です。
このハローワーク受付票が、通称「ハローワークカード」と呼ばれています。
今後、ハローワークで検索した求人情報の詳しい部分が知りたい時や応募したい時、就活のための職業相談をする時には、必ずこの書類が必要となります。
ハローワークカードは毎回忘れずに持参しましょう。求人検索をする
求職申し込みが完了して、ハローワークカードを受け取ったら、ハローワークに設置されている求人端末のパソコンで、登録されている求人を検索しましょう。
まず、受付で端末を利用したい旨を伝えて、番号札を受け取り順番を待ちます。
順番になったら、案内された端末に、希望する就業条件を入力して検索。気になる求人募集を見つけたら、求人票の印刷をします。
印刷した求人票は窓口での職業相談や応募の際に必要ですので、紛失しないようにしましょう。
混雑時は、端末の利用時間や求人票の印刷枚数に制限がある場合があるため、注意が必要です。相談窓口で相談する
気になる求人が見つかって、求人票の印刷を済ませたら、相談窓口で相談をしましょう。
窓口でハローワークカードと印刷した求人票を提出して、職業相談の申込みを行います。
職業相談では、求人票の応募要件に間違いがないか確認してもらいましょう。
この際に、求人に関して不明な点や不安な部分があれば、必ず調べてもらいましょう。
職員との相談を経て、最終的に応募を決めたら、ハローワークを通して応募先へ連絡してもらい、面接の予約をしてもらうという流れになります。紹介状を受け取って求人に応募する
求人票への応募が決まったら、ハローワークから発行される紹介状を受け取ります。
ここで言う紹介状とは、ハローワークを介して求人票の求人へ応募する際に必要となる書類です。
選考の際、紹介状は本人確認のため応募先へ提出するため、原本はハローワークが保管、求職者側は控えを受け取ります。
紹介状には、氏名、選考方法、面接予定日、応募先の所在地といった選考に必要な情報がまとめられています。
紹介状を受け取ってから、予約してもらった日程で面接を受けます。
その後は、応募先の採用フローに沿って選考が進みます。
-
失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れ
-
ここで、失業保険を受け取りたいという人の、一般的なハローワークでの受給手続きの流れや、事前に準備しておく書類について解説します。
各段階についてそれぞれのポイントや注意点を確認していきましょう。必要書類・印鑑・証明写真などを用意する
失業保険の受給手続きについても、自分の住んでいる所轄のハローワークで行います。
過去にハローワークを利用したことが無ければ、初回にハローワークカードを作成します。
受給に必要な書類は以下の通りです。・雇用保険被保険者離職票1(雇用保険被保険者資格喪失届) ・雇用保険被保険者離職票2(離職証明書) ・写真2枚(正面上半身・縦3.0cm×横2.5cm) ・マイナンバーが確認できる書類 ・写真付きの身分証明書(免許証、パスポートなど) ・印鑑 ・本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード リストの情報は古くなっている可能性もあるため、必要書類は必ず申し込みのタイミングでハローワークの担当者に問い合わせて、漏れがないか確認すると間違いないでしょう。
受付で求職申し込みと書類提出をする
ハローワークの窓口に必要書類を全て提出して、求職書の記入を行います。
そして、提出した書類を元として受給資格が決定されると、雇用説明会の日程が案内されます。
基本的に失業保険は、受給開始までの期間に多少の違いはありますが、条件を満たしており必要な手続きを行えば受給できます。
窓口で失業保険を受け取りたい理由や経済事情などを口頭で説明する必要もありません。雇用保険説明会に参加する
ハローワークでの手続きから約7日間の待機期間ののち、雇用保険説明会が行われます。
説明会では、受給資格者のしおりに基づいた雇用保険の受給中における諸手続きや、失業認定申告書の書き方などについて2時間程度の解説を受けます。
初回講習としてハローワークの活用法についての案内をするところもあります。
この説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の交付が行われることが一般的です。
そして、説明会から約2週間後に、初回の「失業認定日」が設定されます。決定した失業認定日にハローワークへ行く
初回の「失業認定日」は、受給資格決定から約3週間後が目安です。
失業認定日とは、現在も仕事をしていないか、求職活動をしているかなどを失業認定申告書に記載し、受給資格者証を添えて提出して、失業状態の確認を受ける日です。
必ず本人がハローワークに行って手続きを行わなければなりません。
失業認定日は4週間に1回で、その間には求職活動を行う必要があります。
自己都合で退職していて3ヶ月の給付制限期間がある人は、給付制限期間のあと2回目の認定日が設定されます。
認定日は、病気や採用面接などのやむを得ない事情がない限り変更できません。失業保険を受給する
失業の認定を受けてから失業保険が振り込まれるタイミングは、認定日から約1週間が目安になります。
金額は、認定日のときに雇用保険受給資格証に記入されています。
初回の振込は、会社都合退職では初回認定日の後ですが、自己都合退職では2ヶ月の給付制限を経て2回目の認定日の後になります。
振込は土日祝日を除く2~3営業日後の午前が多いようですが、万が一失業保険が振り込まれないは、認定日から5営業日を過ぎているか、指定した銀行口座情報に変更がないか、認定日にハローワークで「不認定」とされていないか確認しましょう。
-
高卒求人における応募前職場見学とは?
-

応募前職場見学とは、就職を希望している高校3年生が最終的に応募書類を発送する前の時期に、入社したい企業を決める参考にするために、実際の職場を見学することです。
大卒採用と違いルールが厳しく期間も短い高卒採用において、企業や職場とのミスマッチを減らすことや、職場への理解を深めてから応募に繋げるという重要な役割を担っています。
ここで、高卒求人における応募前職場見学の流れについて確認していきましょう。スケジュール・期間
高卒採用の採用選考スケジュールは、6月1日からハローワークに求人申し込みを開始、7月1日から求人情報の公開開始、9月5日以降に、正式に応募書類の提出や推薦が始まります。
そのため、応募前職場見学は、一般的には高校生の求人票が解禁となる7月末~8月末の夏休みの期間を利用して行われています。参加するメリット
応募前職場見学では、本人の状況を詳しく聞き取るような採用選考に直接繋がる質問や、内定と受け取られるような話をすることは禁止されていますが、企業側としても応募を検討している高校生と直接コミュニケーションが取れるため、採用時のミスマッチを防ぐことに繋がります。
高校生側も実際の現場に触れて、求人票からはわからない職場の雰囲気を肌で感じることで、企業や仕事への理解が深まるため、入社後のギャップによる早期離職が減るというメリットがあります。マナーや注意点など
企業は学校ではなく「職場」という社会人の働く場所です。そのため、学校のように「学ぶ場所」とは違うということを、学生は意識することが大切です。
見学させて頂く立場であることを自覚して、調べればすぐに分かるようなことや、離職率や手取り金額、ボーナスの額のような、先方に対して失礼になる質問は控えましょう。
また、企業側からの説明はメモを取るなどしてよく聞いておいて、一度説明されたことを繰り返し質問することがないようにして、自己アピールにつながるような前向きな質問を心がけましょう。
-
ハローワーク利用の流れについてよくある3つの質問
-
ここで、ハローワークを初めて利用する人からよくある質問をまとめてみました。
ハローワークに行くときはどういう服装がいいんだろう?初めてハローワークに行こうと思っているけれど、どこのハローワークに行けば良いのかわからない、など、他の人に聞きづらい質問について解説します。ハローワークに通う際の服装は?
ハローワークに行く際は、清潔感のある普段着でかまいません。そもそもハローワークは採用選考をする場所ではありません。
ハローワークを通じて求人に応募する時にはハローワークから企業へ連絡をしてくれますが、その際も服装に関してわざわざ伝えることは無いため、リクルートスーツ以外でも問題ないでしょう。
ただし、職業相談で面接の練習をしたい場合や、良い求人を見つけた時、急な面接やセミナーなどにすぐ対応したい!という人は、スーツを着ていくことをおすすめします。どこのハローワークに行ってもいい?
初回の登録や、失業保険の受給申請などについては、自分の居住地を管轄するハローワークでしかできません。
ですが、既に初回の登録が済んでいて、ハローワークカードが発行されていれば、職業相談については全国どこのハローワークでも利用することができます。
そのため、就職したいエリアや企業が決まっている人や、将来的に転居の予定がある人は、就業を希望する地域の管轄のハローワークで仕事探しをしても良いでしょう。ハローワークを利用できる時間は?
ハローワークは平日8:30~17:10に営業しているところが多く、土日祝日・年末年始は休館ですが、地域によって平日の夜間や土曜日の利用が可能です。
施設によって営業時間は異なるため、行く前には所在地と合わせて時間も確認しておくと良いでしょう。
-
まとめ:ハローワークは年齢や職歴など関係なく利用できます!ぜひ有効活用しましょう!!
-
今回の記事では、ハローワークの利用方法やハローワークでできること、また、失業保険の手続きや、高校生のための応募前職場見学の流れについて解説しました。
就活では、失業保険や職業訓練、応募前職場見学など、自分に必要な方法を活用して、自分のやりたい仕事を探すことが大切です。
バイトルNEXTではインターネット上で様々な企業の求人を登録不要で見ることができるため、ハローワークに行く時間がない人や、事務手続きが面倒だと思う人にもおすすめです。【関連記事】
ハローワークとは?利用の流れやできることについて簡単にわかりやすく解説!
ハローワークの使い方を徹底解説!ハローワークへの登録から就職のためのポイントも紹介
失業保険手続きの流れと受給要件・もらい方とは?手続きを忘れたらどうする?
ハローワークへ行く服装は何がいい?証明写真・失業保険・説明会など場面別に解説!
ハローワークの登録方法を解説!登録の流れや必要なものは?ネットからでもOK?
ハローワークの持ち物を場面別に紹介!初回や雇用保険手続きのときは?どんな服装?
ハローワークで相談できることとは?職業相談ってなに?電話では相談できない?
ハローワークの求職活動って何をするの?簡単&確実に認定される求職活動実績の作り方
ハローワークの職業相談とは?何を話す?実績作りになるの?
ハローワークの営業時間は?平日昼間だけ?土日や年末年始などの営業についても解説!
採用証明書とは?ハローワークへ提出?採用証明書が必要なケースや書き方などを解説!
職安とは?ハローワークとは違う?受けられるサービスや利用の流れ、メリットも紹介!
ハローワークの認定日は指定の時間しか手続きできない?指定日時に行けないときは?
【社労士監修】離職証明書はダウンロード不可!ハローワークで受け取ろう
【社労士監修】失業保険(雇用保険の基本手当)の延長申請は可能!注意点などを解説記事監修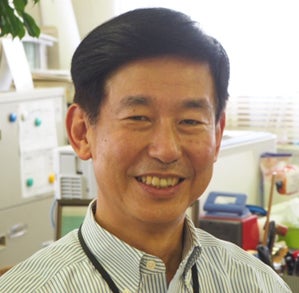
荒武 慎一(あらたけ しんいち)
社会保険労務士、中小企業診断士
昭和53年同志社大学卒業、富士ゼロックス株式会社を経て平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金をわかりやすく解説することで高い評価を得ている。(連絡先:0422-90-9990)
さっそくお仕事を探してみよう
社員の仕事探し・転職 の関連記事

アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説

製造業とは?就職・転職の検討に使える主な職種や仕事内容・メリット・デメリットなどの情報を解説!

建築・土木ってどんな仕事?仕事内容や現場の声、求人の探し方について紹介
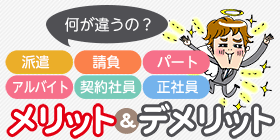
何が違うの?働き方の違いメリット&デメリット|派遣・請負・パート・アルバイト・正社員
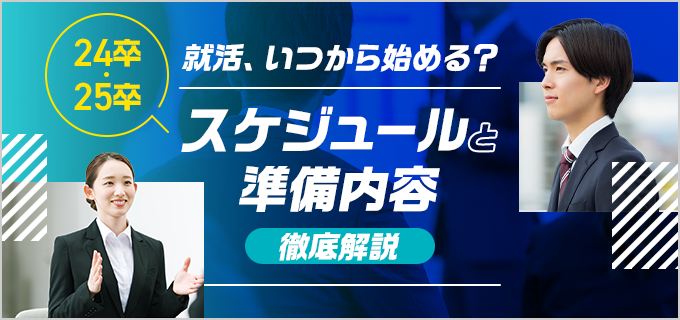
【24卒・25卒】就活はいつから?流れや準備時期を徹底解説

バイトルNEXT 適職診断
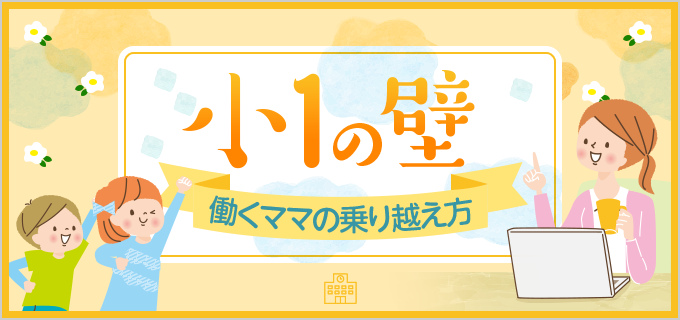
小1の壁を乗り越える!困るポイントと対策、働き方を解説
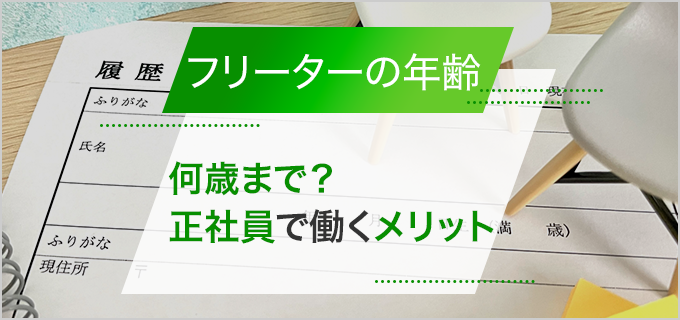
【アンケート】何歳までフリーターを続ける?就職はいつまでにするべき?

NEW中卒の就職は難しい?就職率や男女別おすすめの仕事・資格・職種まで紹介!

内定承諾の返事は電話?メール?連絡する際のマナーを例文付きで紹介
カテゴリ一覧
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 【2023年】最低賃金は全国平均で1,004円、最大で47円の引き上げ|最低賃金を下回っていた場合の対処法 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- アルバイト面接の前日メールはどうやって返信する?マナーやポイント、例文を解説! /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- バイトルCMとの連動企画#はないちもんめチャレンジの受賞作品大公開 /プロモーション
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート