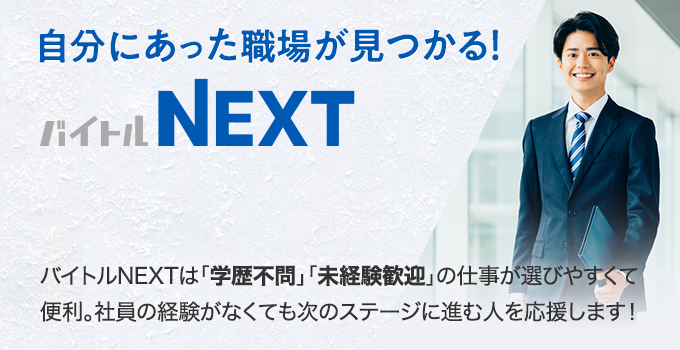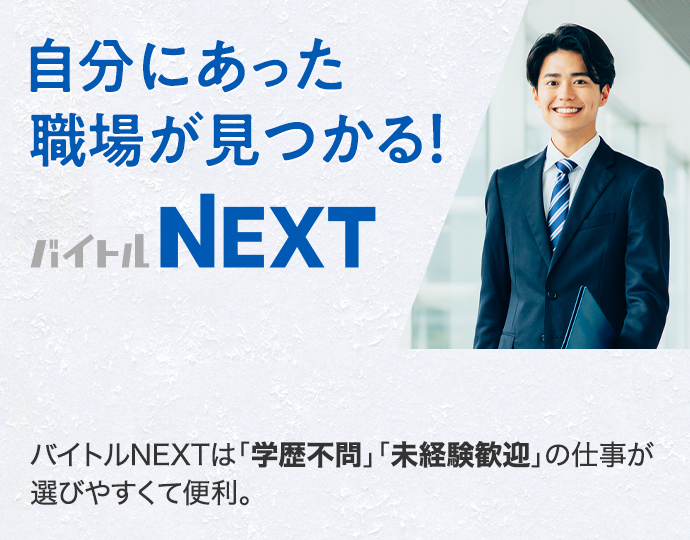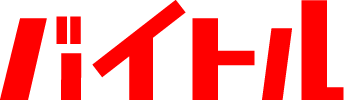配偶者とは何かをわかりやすく解説|履歴書の配偶者・扶養家族欄の記入例付き

履歴書を書く時に「配偶者の有無」を書く項目があり、どう記入すべきかわからず悩んでしまう人もいるのではないでしょうか。配偶者の有無は、応募先の企業にとって重要な情報となるため、正しく記載する必要があります。
そこでこの記事では、配偶者とは何かを解説しつつ、履歴書の配偶者・扶養家族欄の書き方についても紹介していきます。
目次
-
配偶者とは何か
-
履歴書で聞かれる「配偶者の有無」ですが、そもそも配偶者とは、誰を指す言葉なのでしょうか。ここでは、配偶者の意味や配偶者に当てはまらないケースについて紹介していきます。
配偶者の意味
配偶者とは、婚姻関係にあるパートナーのことを指します。つまり、夫から見ると妻が、妻から見ると夫が配偶者となるわけです。結婚している人は、履歴書の「配偶者の有無」の欄に「配偶者あり」と記載しましょう。
厳密にいうと、配偶者の定義は税法上と社会保険上で少々異なります。税法上の配偶者の定義は、民法の規定による配偶者であることで、内縁関係の人は該当しません。
社会保険上の配偶者の定義は、民法の規定による配偶者だけでなく、事実婚や内縁関係を含みます。配偶者に当てはまらないケース
配偶者の要件は、あくまでも法律上で婚姻関係にあることのため、いわゆる事実婚の場合は配偶者に含まれません。事実婚だと配偶者にならないため、公的な控除が受けられない可能性があります。
ただし、事実婚であることを証明できる場合は、社会保険で扶養に入れたり、遺族年金を受け取る権利が認められたりなど、配偶者扱いになることも可能です。
事実婚の証明には、世帯主と内縁の妻(夫)の関係について記載されている住民票が必要となります。
-
扶養家族とは?扶養家族としてカウントされる条件を解説
-

扶養家族とは、わかりやすい言葉で説明すれば「自分が養っていかなければならない家族」です。単に身の回りの世話をされるだけではなく、自分の収入によって生活費の面倒をみている家族を指しています。
扶養家族というキーワードを見ると、妻・夫・子ども・父母などをイメージするかもしれません。しかし、一定の条件を満たすことで兄弟姉妹・孫・祖父母など、ほかの親族も扶養に入れます。
一方、75歳以上(後期高齢者医療制度の対象)の人は扶養に入ることができません。これは、それまで加入していた医療保険から後期高齢者医療保険制度という別の医療保険に切り替わるからです。注意しましょう。
さらに、扶養家族は「社会保険上」と「税法上」で定義が大きく変わります。カウントされるための条件も異なるため、その違いをきちんと押さえておきましょう。
ちなみに、控除額などの観点から勤務先には「税法上」の扶養家族を提出します。社会保険上の扶養家族(被扶養者)
社会保険上で定義される「被扶養者」とは、下記の条件A・Bのいずれかに当てはまる人を指します。なお、下記の「被保険者」は履歴書を作成している応募者本人のことです。
A:被保険者との同居・別居を問わないケース
- 被保険者の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)、配偶者(内縁関係・事実婚も含む)、子(養子縁組も含む)、孫、兄弟姉妹
- 年収が130万円未満(60歳以上もしくは障害厚生年金を受けられる障がい者の人は年収180万円未満)であり、なおかつ被保険者が1年間に得る収入の2分の1未満である人
B:被保険者との同居が必要なケース
- 被保険者から見て、条件Aで挙げた人以外の3親等以内の親族(兄弟姉妹の配偶者、おじおば、おいめいなど)
- 被保険者と内縁関係・事実婚にあった配偶者の父母、連れ子
- 被保険者と内縁関係・事実婚にあった配偶者が亡くなったあとに残された父母、連れ子
- 年収が130万円未満(60歳以上もしくは障害厚生年金を受けられる障がい者の人は年収180万円未満)であり、なおかつ被保険者からの援助として受け取っている金額より少ない人
このように、被保険者とどのような関係性を持っているか、同居しているかどうかによって、被扶養者としてカウントされる条件が大きく変わってくるため、ケース別に押さえておきましょう。
税法上の扶養家族(扶養親族)
税法上で定義される「扶養親族」は、その年の12月31日時点において、下記の条件A~Eをすべて満たしている人が当てはまります。なお、下記の「納税者」も応募者本人のことです。
A:16歳以上の人
B:納税者と生計を一にしている(同居していなくても生活費などを送っているなら該当)
C:被保険者の配偶者以外の親族(6親等以内の血族あるいは3親等以内の姻族)、養育を委託された子(里子)、養護を委託された高齢者のいずれかに該当
D: 1年間の合計所得金額が48万円以下である(所得が給与収入のみなら合計103万円以下)の人
E:青色申告者の事業専従者として、その年に給与の支払いを1度も受けていないか、あるいは白色申告者の事業専従者ではない上記のうち、Cの血族は6親等までを含み、高祖父母の祖父母や昆孫、祖父母のおいめいの子などが当てはまります。一方、3親等以内の姻族は曾祖父母やおじおば、曾孫などがおもな該当例です。
Dの条件で提示されている48万円以下という金額は、課税対象となる所得金額を指します。不動産運用などで得た収入も含めて48万円を超えた場合、アルバイトなどで得た収入が一切なくても扶養に入ることは認められないため注意が必要です。
また、Eの「事業専従者」とは、個人事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族であり、なおかつ年間6ヵ月以上その事業に従事している人を指します。自分に合った仕事が見つかる!
バイトルNEXTで仕事を探す
-
配偶者と扶養家族は採用に影響するか
-

配偶者や扶養家族の有無は、合否に関係ありません。しかし、企業は配偶者欄・扶養家族欄から健康保険や手当支給手続きなどの有無を知る必要があるため、履歴書には正しい情報を記載する必要があります。
間違えた情報を記載すると、企業側に悪い印象を与えかねないため注意しましょう。自分に合った仕事が見つかる!
バイトルNEXTで仕事を探す
-
履歴書の配偶者・扶養家族欄は、結婚して家族がいる人向けの記入欄
-
配偶者・扶養家族欄は、一般的に履歴書の右側にあり、下記の3つの記入欄から構成されています。
- 扶養家族数(配偶者を除く):×人
- 配偶者:有・無
- 配偶者の扶養義務:有・無
※履歴書の種類によって表記が異なる可能性もあるため注意
基本的にこれらは結婚して家族がいる人に向けた記入欄であり、その場合「配偶者」と「配偶者の扶養義務」は「無」に丸をつけておけば問題ありません。
しかし「扶養家族数(配偶者を除く)」の記入欄については、結婚しているかどうかに関わらず、記入しなければならないケースがあります。
一方、結婚している場合は「配偶者」を「有」としますが、内縁関係・事実婚のように婚姻届を提出していない場合でも配偶者とみなされるため、注意が必要です。
なお、ほかの2つの記入欄は、応募者を取り巻く状況によって記入内容が変わるため、正しい書き方を把握しておきましょう。
これらの情報は履歴書を作成している本人だけではなく、応募先の企業にとっても欠かせないものです。
企業は履歴書に書かれている情報をもとに、家族手当や社宅の必要性などを確認します。さらに、所得税・健康保険・福利厚生など、採用後の手続きにも関わってくるため、とても重要な項目になります。
なお、履歴書にこのような記入欄が設けられている理由は、あくまで各種手続きの要否を確認するためなので、記入した内容が採用選考に影響することはほぼありません。
故意に情報を隠したり、誤った情報を記載したりすると、虚偽申告で採用取り消しや解雇といったトラブルに発展する可能性もあります。最悪、損害賠償を請求されかねないため、事実を記載しましょう。
扶養している家族の介護や通院付き添いなど、特別な事情を抱えている場合、その旨を応募先の企業に相談すれば、何らかの対策を講じてくれるケースもあります。自分に合った仕事が見つかる!
バイトルNEXTで仕事を探す
-
【記入例つき】履歴書の配偶者・扶養家族欄の書き方
-
配偶者・扶養家族欄の書き方をケース別・記入例つきでまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
配偶者あり・子どもなしの場合
配偶者との間に子どもがおらず、なおかつ配偶者が専業主婦(主夫)で収入を得ていない場合、収入があっても一定金額を下回っている場合、下記のような記入内容となります。
- 扶養家族数(配偶者を除く):0人
- 配偶者:有
- 配偶者の扶養義務:有
一方、家計を支えるために夫婦共働きで働いていて、130万円以上の年収を得ている場合「配偶者の扶養義務」を「無」にすればOKです。
例)
配偶者あり・子どもありの場合
こちらのケースでは、子どもの数や状況によって書き方が変わるため、注意が必要です。例えば、配偶者が専業主婦(主夫)であり、なおかつまだ働いていない子どもが1人いるときは、下記のように記入します。
- 扶養家族数(配偶者を除く):1人
- 配偶者:有
- 配偶者の扶養義務:有
もし子どもが一人暮らしをしていて、なおかつ就職やアルバイトなどで130万円以上の年収を得ている場合、その子どもはカウント対象外となるため「扶養家族数(配偶者を除く)」は0人と記載しましょう。
例)
配偶者あり・子どもあり・同居の親族ありの場合
例えば、配偶者と子ども1人、応募者の母親(75歳未満)と同居しており、なおかつ誰も収入を得ていない場合、下記のように記入します。
- 扶養家族数(配偶者を除く):2人
- 配偶者:有
- 配偶者の扶養義務:有
母親が180万円以上の年金収入を得ていたり、75歳を超えていたりする場合は対象外になるため「扶養家族数(配偶者を除く)」が1人減ります。
配偶者なし・子どもありの場合
例えば、離婚などで配偶者はいないが、収入のない子どもが1人いるという場合、記載内容は下記のとおりです。
- 扶養家族数(配偶者を除く):1人
- 配偶者:無
- 配偶者の扶養義務:無
子どもがすでに家を出ており、アルバイトなどで収入を得ている場合、扶養に入れない可能性もあります。
自分に合った仕事が見つかる!
バイトルNEXTで仕事を探す
-
まとめ:配偶者の意味や履歴書の書き方が把握できたら、積極的に求人に応募しよう!
-
配偶者の有無や扶養家族の数は、応募者と企業の双方にとって重要な情報です。応募者の視点から見れば、扶養家族になることで税金控除や保険料免除といったメリットを得ることができます。
また、企業の視点から見た場合、家族手当や所得税の手続きに関わってくるため、正しい情報を手に入れなければなりません。もし情報が間違っていた場合、企業に大きな迷惑がかかる可能性もあるため、きちんと記入することを心がけましょう。【履歴書お役立ち記事】
【社労士監修】扶養家族について、税法上と健康保険上の違いや履歴書の書き方を解説
履歴書に書く電話番号は固定?携帯?正しい書き方を解説します
履歴書の本人希望欄は書き方次第で自己PRになる!勤務時間や場所の書き方を紹介
バイトの履歴書の本人希望欄に書くべき内容と書き方のマナー
【社労士監修】履歴書の「賞罰」とは?賞罰欄の正しい書き方や書くべき基準を解説
履歴書の「通勤時間欄」の正しい書き方を解説!転居や在宅勤務などケース別に紹介
履歴書の住所・電話番号・メールアドレスの書き方を解説
履歴書にメールアドレスは必要?記入欄がないときはどうする?
履歴書の「趣味・特技欄」を書くときにおさえるべきポイント!書き方や例文も紹介
履歴書の長所・短所の書き方は?面接時の答え方も解説
履歴書 の関連記事
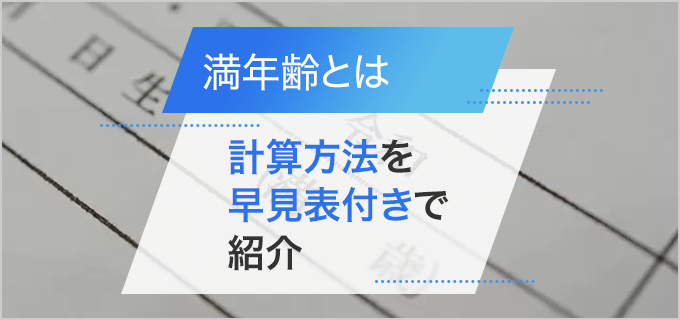
満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう
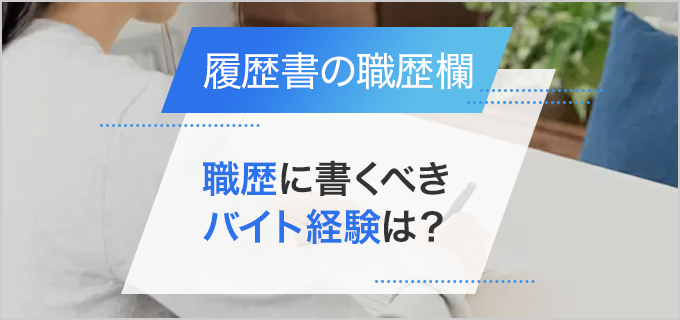
履歴書の職歴欄にアルバイトの経歴は書かない?書き方やアピール方法を紹介

履歴書では「退職と退社」どちらを使うべき?職歴の書き方を例文付きで解説!

パートの履歴書/学歴・職歴の書き方(主婦・主夫編)
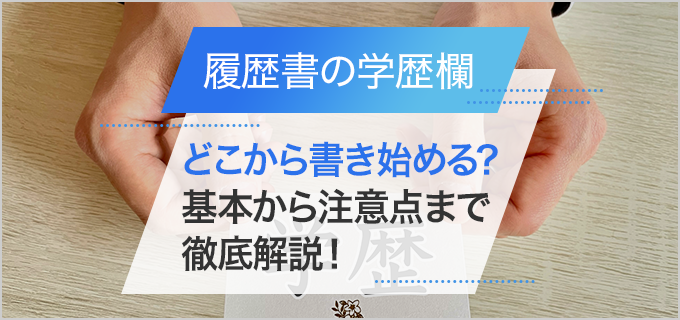
履歴書の学歴はいつから?学歴欄の正しい書き方【学歴早見表・西暦/和暦の変換表】

ダブルワークやアルバイトの掛け持ちをする場合の履歴書の書き方
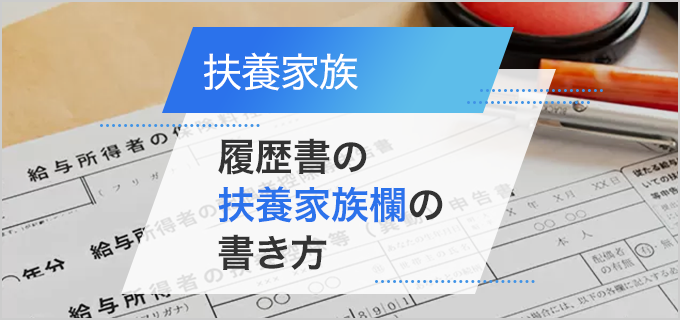
【社労士監修】扶養家族について、税法上と健康保険上の違いや履歴書の書き方を解説

履歴書の封筒にはどんなペンを使えばいい?太さや種類の選び方を解説
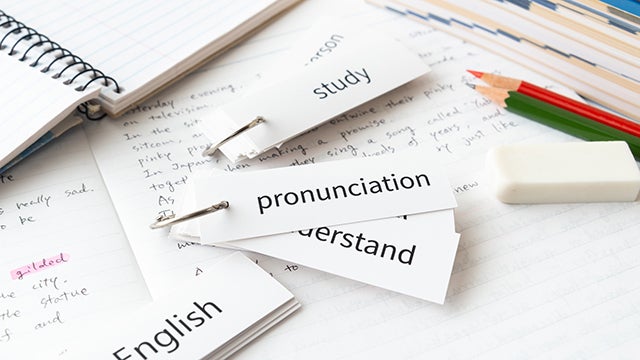
履歴書への英検(実用英語技能検定)の書き方のポイント

履歴書の封筒色のおすすめは?茶封筒はNG!?封筒選びのポイントを解説
カテゴリ一覧
-
派遣の仕事探し派遣の仕事探し
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書
- 自宅でできる仕事46選!スキルや趣味、得意分野を活かせる在宅ワークを見つけよう /バイト探し・パート探し
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート
- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!