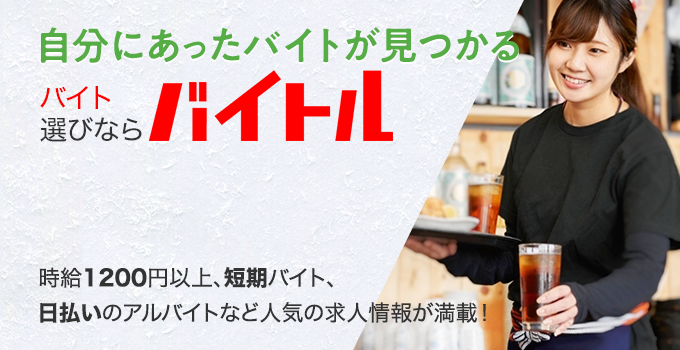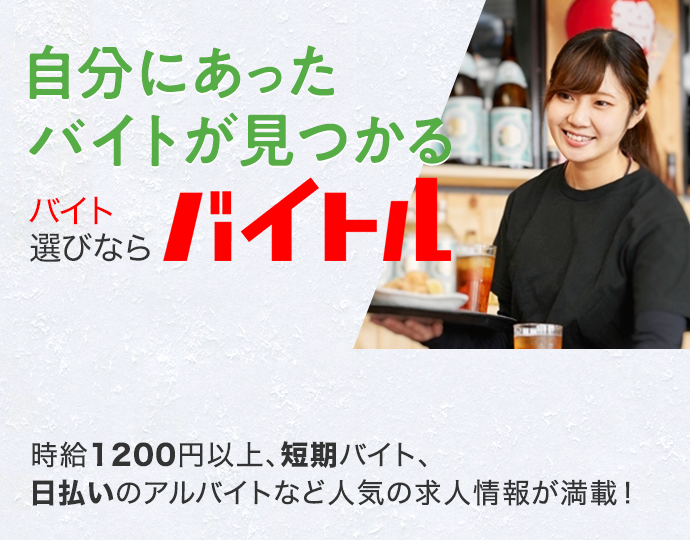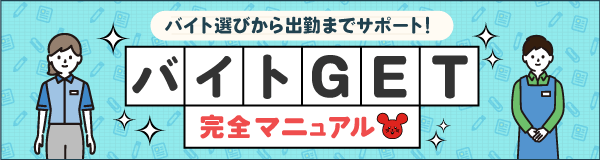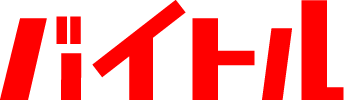「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」の意味は?使い方や例文を紹介!

「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」は、主にビジネスや正式な場面の文書やメールで使われる言葉です。
文書やメール、案内状や招待状は、時候のあいさつから始まるのが一般的ですが、特に「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」というあいさつはよく使われる表現です。
この記事では、「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」の意味や使い方、使う際の注意点などについて、例文を用いて詳しく解説します。
目次
-
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」意味と読み方
-
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」は、ビジネスのメールや手紙で使われます。あまり聞きなれない言葉もありますが、それぞれ以下のような意味があります。
単語 意味 時下(じか) 現在、この頃 ますます さらに、より一層 ご清栄(ごせいえい) 繁栄や健康 お慶び 喜び祝うこと 「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」は、「この頃、より一層あなた(の会社)が栄えていることを喜びお祝いします」という意味になります。相手、または相手の会社の繁栄を祝うあいさつです。とても丁寧に敬意を示す表現で、正式な場で使用されます。
-
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」の使い方
-
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」を使う際のポイントについて解説します。
正式な場で使われるあいさつ
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」は、ビジネスのメールや手紙、招待状・案内状など、正式な場面で主に使われるあいさつです。
程よく丁寧な表現かつ正式な場面に適しているため、重要な取引先や人物などに対して、敬意を示すことができます。
式典などフォーマルな場での冒頭あいさつに使われることもありますが、基本的には書面などの文面での表現です。時候のあいさつの代わり
「時下ますます」は、すでに何度かやりとりがあるため前置きのあいさつは手短に済ませたい、という時にも使えるあいさつです。
正式な書面やかしこまった手紙・メールでは、時候のあいさつから始まります。例えば1月なら、「厳寒(げんかん)の候」、「新春(しんしゅん)の候」など、さまざまな表現を用いた時候のあいさつがありますね。
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」の「時下」は、「現在、この頃」という意味で、季節に関係なく時候のあいさつに代わって使うことができます。「厳寒の候、時下ますます~」だと、時候のあいさつが重複することになるため避けましょう。使う際は「拝啓」や「謹啓」と一緒に
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」を使う際に覚えておきたいのが、「時下」は書き出しに使われないという点です。「時下ますます~」は時候のあいさつを省略した形になるため、前には必ず「拝啓」「謹啓」という頭語を置きましょう。
基本的には、以下のような形になります。セットで覚えておくと安心です。拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
~~~本文~~~
敬具
-
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」使う際のNGや注意点
-
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」を使う際の注意点について説明します。
- 喪中・お悔やみごとでは使わない
- 体調不良の人、お見舞いの連絡には使わない
- 通常の会話では使わない
- 結びのあいさつには使わない
喪中・お悔やみごとでは使わない
「ご清栄」は相手の繁栄や健康を祝う言葉です。そのため、喪中やお悔みごとに用いるあいさつにはふさわしいとはいえません。
体調不良の人、お見舞いの連絡には使わない
上記と同様、病気やけがをしている場合など体調がすぐれない人に対しても、「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」は不適切です。
通常の会話では使わない
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」は、あらたまった手紙や招待状、メールなどで使われる丁寧な表現です。日常での会話や通常業務など日頃使うあいさつではないため、使うシーンはしっかり見極めましょう。
結びのあいさつには使わない
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」は、時候のあいさつの代わりに冒頭で使う言葉です。結びの言葉としては不適切のため、使い際は注意しましょう。
-
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」を使った例文
-
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」を用いた例文を紹介します。
「ご清栄」は個人や団体・企業に対して使用できます。「ご清祥」「ご多幸」などの言葉は、個人に向けた場合に使用するのが一般的です。
▼団体(企業)・個人に向けたあいさつの例文拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
(本文)
末筆ではございますが、貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。
敬具▼個人に向けたあいさつの例文
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
○○様にはいつも温かいお心遣いをいただき、大変感謝しております。
(本文)
最後になりましたが、○○様のますますのご多幸をお祈り申し上げます。
敬具▼お礼状の例文
拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたびは、○○をいただきまして、ありがとうございました。いつもながらのお心遣いに感謝申し上げます。
(本文)
まずは略儀ながら書中にてごあいさつを申し上げます。
敬具▼招待状の例文
拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、弊社は本年で創立○周年を迎えることとなりました。これもひとえに皆様のご厚誼・ご支援の賜物と、深く感謝申し上げます。
つきましては お世話になった皆様への感謝を込めまして、ささやかな披露宴を催したいと存じます。
ご多用中のところ誠に恐縮ですが、何卒ご出席いただきますようお願い申し上げます。
(本文)
敬具
-
「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」の言い換え表現
-
ここでは、「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」の言い換え表現を紹介します。
「ご清栄」の言い換えは「ご発展」「ご健勝」「ご盛栄」
それぞれの意味や使い方を解説します。
「ご発展」
発展は「物事が勢いよく伸びて、盛んになること」を意味します。企業や団体に向けて、相手の会社の繁栄や成功を願う際に使われる言葉です。
▼例文- 貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。
- より一層のご発展をお祈りしております。
「ご健勝」
健勝は「健康がすぐれて元気なこと」を意味します。相手の健康や元気を願い、またはその状態を認める際に使用する言葉です。冒頭のあいさつだけでなく、締めの言葉としても使用されます。
▼例文- ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
- 益々ご健勝のことと存じます。
- 皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
「ご盛栄」
盛栄は「商売などが盛んになる」という意味です。 商売をしている個人や法人に向けて使われるのが一般的。相手の発展と繁栄を祈る気持ちを伝えることができる言葉です。こちらも締めの言葉としても使用されます。
▼例文- ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
- 皆様のご盛栄をお祈り申し上げます。
「時下」をつけない場合は時候のあいさつを!
先述した通り、「時下ますます~」の「時下」はどの季節でも使える時候のあいさつです。「○○の候 時下ますます~」では時候のあいさつが重複するため避けましょう。
反対に、時候のあいさつの代わりとなる「時下」ではなく、「貴社」や「皆様」などに変えた場合の表現を紹介します。合わせて覚えておくと便利です。
▼例文- 早春の候 貴社ますますご清栄の御事とお喜び申し上げます。
- 残暑の候、皆様におかれましてはご清祥のこととお慶び申し上げます。
- 厳寒の候、貴殿におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
-
まとめ
-
この記事では、「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」の意味や使い方、例文について詳しく解説しました。
この言葉を用いたあいさつは、相手への敬意を表した丁寧な表現です。日常ではあまり使わず、初めての相手は久々の相手、特に重要な取引先など、フォーマルな場面で使うのが一般的です。
正式な書面やメールや、スピーチの場面でいきなり要件を伝えるよりも、冒頭のあいさつ文で相手の繁栄や健康などを気遣う気持ちを伝えることができれば、よりいいコミュニケーションがとれるでしょう。
正しい意味や使い方を覚えて、ぜひ活用してみてください。【おすすめ記事】
「お陰様で」は目上の人に使える敬語?正しい意味と使い方を例文付きでご紹介!
「痛み入ります」の意味とは?例文や言い換え表現、返答など、ビジネスにも活かせる使い方を解説!
「~以降」はどこまで含まれる?意味と使い方を紹介!
メールや手紙の「PS」とは?正しい意味とビジネスメールにも使える言い換えを解説
【例文あり】「ご愁傷様です」はメールで使える?意味や使い方・言い換えをご紹介
目上の人に『お大事に』を伝える敬語表現とは?類語やメールでの返答例文も紹介!
「づつ」と「ずつ」どっちが正しい?意味や例文・使い分けのポイントを解説
「往々にして」の意味と使い方を例文付きで解説!ビジネスで使える敬語表現も
「感慨深い」の意味とは?感慨深い気持ちになる瞬間や正しい使い方を例文付きでご紹介
「とんでもないです」を徹底解説!意味・使い方・言い換え表現を例文と併せて丁寧に説明!
「よろしくお伝えください」は目上の人に使える?意味や返答・使い方【例文付き】
「恐縮」の使い方完全ガイド!意味・使い方・言い換え表現を例文と併せて丁寧に解説
ビジネスシーンで使える「気をつける」の言い方は?意味や使い方、丁寧な言い換え表現を紹介
就業・勤務 の関連記事
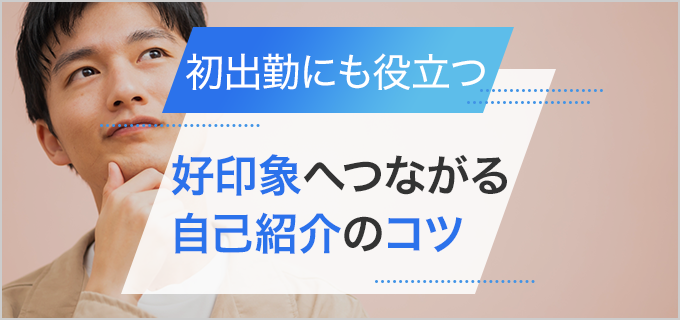
自己紹介|新しい人間関係のスタートで好印象を目指すためのアドバイスと例文

正社員じゃないからムリ?パートなら覚えておきたい産休・育休のあれこれ

バイト敬語要注意!アルバイトするなら正しい敬語を覚えよう

バイトなのに寝坊した!アルバイトに遅刻してしまったときのベストな行動

バイトのシフト入りすぎ?アルバイトに疲れたときの対処法とは?
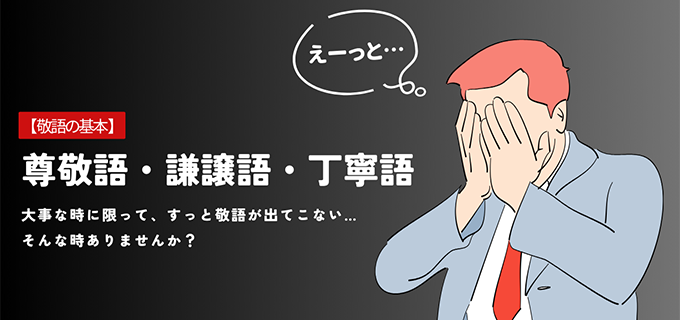
【敬語変換表あり】尊敬語・謙譲語・丁寧語の基礎
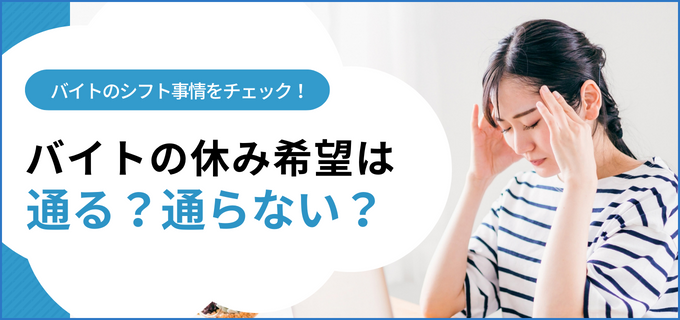
アルバイトのシフト事情!休み希望は通る?通らない?

意思の疎通が苦手な人必見!コミュニケーション能力向上のポイント

バイトに早く慣れるには?アルバイト先の先輩と早く仲良くなろう!
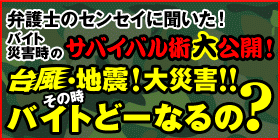
台風・地震!大災害!!その時バイトどーなるの?
カテゴリ一覧
-
派遣の仕事探し派遣の仕事探し
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書
- 自宅でできる仕事46選!スキルや趣味、得意分野を活かせる在宅ワークを見つけよう /バイト探し・パート探し
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート
- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!