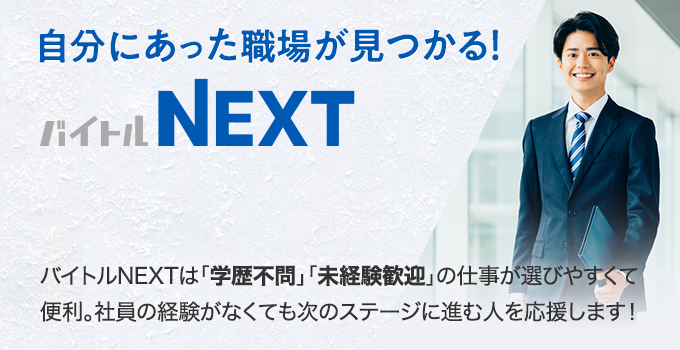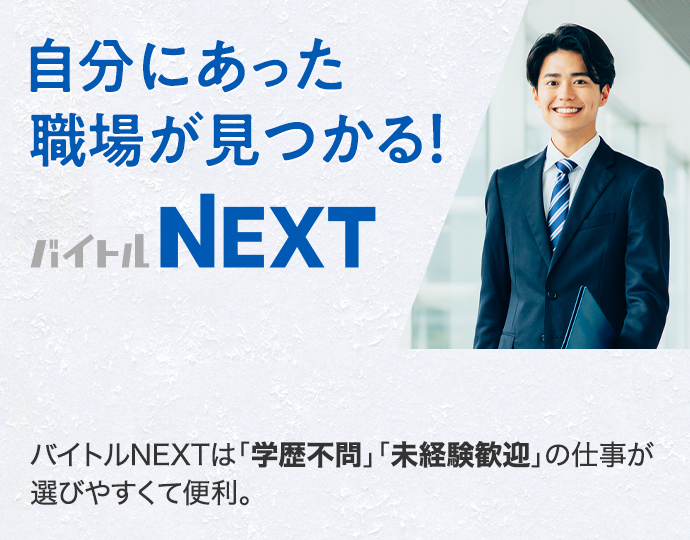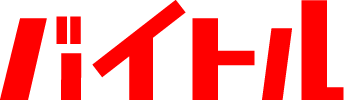転職のタイミングとポイントを解説!いつがいい?社会人何年目?転職すべき状況とは?
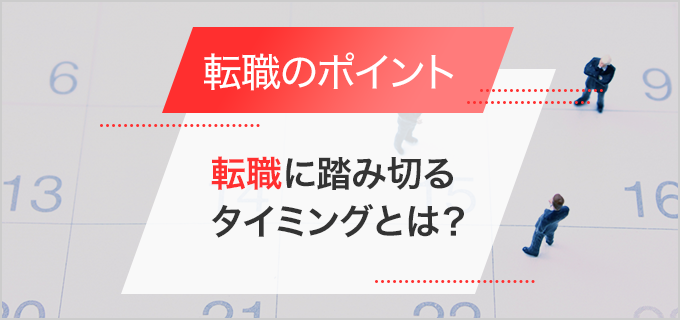
このまま会社にいても不安だけど、いまのキャリアでどんな転職が可能なのかわからない。自分の決断は無謀なのか、妥当なのか?そんな不安を解決します。ここでは転職におけるタイミングとキャリアの捉え方を解説しています。
「転職は気になっているけど、タイミングはいつが良いのだろうか」と考えている人は、ぜひ最後まで目を通してみてください。
目次
-
転職のベストタイミングは人それぞれ
-
 転職のベストなタイミングは、人それぞれで一概には定義できません。
転職のベストなタイミングは、人それぞれで一概には定義できません。
年齢、業種、キャリア、家庭環境と考慮するべき点が多くあるからです。
大切なのは、転職を考えたその時点から見たベストタイミングがいつか、ということです。ここでは、自身のキャリアプラン、ライフプランにあわせて、より良い条件で転職するためのポイントを紹介します。
-
【年代別】転職のタイミングの特徴・ポイント
-
採用する側がまず目を向けるポイントは、年齢とキャリアです。
伸びしろのある若手なのか、即戦力となる中堅層なのか?転職前の経歴・職歴によって、期待されることが異なります。
ここでは転職業界での年齢別のポイントをまとめています。20代前半
卒業後3年目から25歳頃までは、第二新卒とみなされます。
ある程度の社会人経験とマナーが身につき、かつ新しい会社にも柔軟に対応できるとして、企業からのニーズも多い世代です。
また、未経験の業種・業界へ転職する場合も、経験よりポテンシャルを見込んで採用してもらえる可能性が高いです。
しかしあまりに勤務年数が短いと、忍耐力の欠如や再度の転職を懸念されてしまいます。
そのため、転職をする際は3年目近くまで勤務を続ける、もしくは明確な転職理由を伝え入社後のモチベーションの高さをアピールしましょう。
特に新卒で入社した会社を辞めたいと感じる場合、入社前の自己分析や企業研究が不足してミスマッチが起こった可能性が高いです。そのミスマッチの原因や転職したいと思った理由を明確にして、転職活動へ挑みましょう。20代後半
20代後半は業務にも慣れ、人間関係や会社の将来性についても考え出す頃です。
転職市場では若手ながらの柔軟性と社会人としての安定性を見られます。20代の転職活動にかかる期間は平均約3か月で、多くは収入のアップにもつながっています。
20代前半にはなかった、実務を通しての実績をアピールできれば、転職もスムーズに進む可能性があります。また、扶養家族がいない、実家住まいなど、自分の裁量で暮らせる内に、多少年収が落ちてもキャリアチェンジに挑む余裕があるでしょう。
自身のキャリアの棚卸をして自分の市場価値を把握すること、これからのキャリアプランを明確にすることが大切です。30代前半
30代に入ると役職に就く方もいることで、マネジメント能力を測られたり、即戦力として求められるスキルが上がります。
もし役職などについていないならば、キャリアチェンジなどはできれば30代前半で行うことが理想的です。
転職後のミスマッチを避けるため、転職活動をじっくり行うこともあり、3か月~6か月と20代に比べて長期化する傾向があります。転職を繰り返すことが難しくなるため、焦って失敗しないように、転職の目的を絞って成功させましょう。30代後半
30代後半は年齢に伴い、企業の要求する能力も上がります。マネジメント経験がない場合は早めに転職するのが良いでしょう。
役職についていればその実績、マネジメント経験や能力をアピールすることで、同業種への転職はスムーズに決まる傾向があります。また、この年代の特徴としては、自身の健康や家族との時間など、仕事以外に考慮すべき要因が増えてきます。
異業種・異職種への転職の場合は、年収や待遇が今の会社よりも低いところから始まることも予め想定しておきましょう。
今後、転職を繰り返さずに済むように転職する企業について入念にリサーチしましょう。40代以降
40代・50代になると人員整理や早期退職の対象となりはじめ、改めてこれからの働き方を考える機会が訪れることがあり得ます。
この年代では主に高い専門性が求められたり、管理職中心の求人となり、ポストに見合った給与を考えても、求人数も減り求人のハードルが上がります。仕事のスキルや経験に加えて、社風ともマッチし、年下の上司とも提携できる柔軟性なども求められます。
高度なスキルや得意な分野がある場合、即戦力として採用される可能性が高いです。今までの自分のキャリアやスキルが活かせる企業を目指しましょう。
未経験の職種にチャレンジするならば、年収にこだわらないなど、優先順位を明確にすることで幅広く探すことができるでしょう。
-
転職をおすすめするタイミング
-
 入社する企業へどれだけの熱意を持っていたとしても、入社するまで分からないのが人間関係、会社の体質です。また社会状況の変化の影響は働くうえで避けられません。
入社する企業へどれだけの熱意を持っていたとしても、入社するまで分からないのが人間関係、会社の体質です。また社会状況の変化の影響は働くうえで避けられません。
希望していた企業へ就職できても、働くうちに、将来のことを考えて「このままここにいてよいのか」と悩むこともあるでしょう。
ここでは、そんな悩みのうち、転職をおすすめするタイミングについて紹介します。これ以上の昇給・昇進が見込めなくなった
昇給は必ずしも義務ではありませんし、会社によって昇給・昇格のスピードや評価制度は様々です。今の会社での昇給・昇進が頭打ちであるならば、成長が見込める企業や年収アップできる企業への転職も検討するべきでしょう。
もっと成長したいということであれば、キャリアアップへの意欲を面接等でアピールすることができます。
業務成績を評価してもらえていない、ボーナスへの反映が低いなど給与や待遇の面でモチベーションの維持が難しくなった場合には、評価制度や給与形態などを転職活動の時にしっかりと確認することが大切です。自分が仕事に求める条件を明確にして、次の進路を探していきましょう。会社の今後が心配になった
「優秀な人ほど早く辞めていく」と言われますが、業績不振から離職する社員が増えるなど、目に見える変化から転職を考えることもあるでしょう。
確かに、迷っているうちに人員整理や倒産となれば、同じようなキャリアの人と転職活動が被ってしまいます。
会社の業績が心配な場合、今後業績が改善・伸びる可能性があるのか検討したうえで、転職へと踏み切りましょう。
ただし、業績不振が業界全体で起こっている場合には、募集が少ないなど転職活動自体の難易度が高くなります。その場合には他の業界への転職を視野に入れるのもおすすめです。
また、業績不振から合併や買収になった場合、福利厚生や評価制度が変わることで、社風や業績が改善される場合もあります。不安から焦って動くだけではなく、自分の務める会社や転職についての情報収集をしながら、年単位で先を考えることが大切です。労働環境の悪さにより心身の健康を悪くしている
超過勤務やハラスメントにより心身のバランスが崩れてしまった際は、転職活動の前に体調回復を優先しましょう。
社内外の然るべき部署があれば相談をして対応をお願いし、休職をすることをおすすめします。
労災が下りるのには時間が掛かります。労災が認められない場合は、健康保険の傷病手当金を申請することで、給与の約2/3の金額を最長1年6か月受給することができます。
他にも医療費控除、自立支援医療費制度などが利用できます。
まずは治療に専念し、改めて環境を改善するために転職先を選びましょう。「辞めにくい」「休みにくい」ということもあると思いますが、一番大切なのはあなたの身体と健康です。
-
ケース別!前と後、どちらが転職するのにベスト?
-
ここからは4つのライフイベントについて、転職の前と後のどちらを選べば有利になるか検討します。
昇進前と昇進後
自身のキャリアにおいてその昇進を望むか望まないかで、転職のタイミングは変わります。
昇進を望まず、転職を考えている最中に昇進の話が来たならば、昇進が決まる前に転職する旨を伝えましょう。管理職への昇進であれば、昇進後すぐに転職することは難しいですし、会社の人事にいらぬ混乱を起こさないのがマナーです。
昇進を望むなら、転職先で昇進の機会を待つより今の会社で昇進し、実績をつけた上での転職が有利になります。ただし、有利になるには結果を出すことが前提になるので、転職は早くても数年後になると考えましょう。住宅ローンを組む前と組んだ後
住宅を購入するならば転職前がベストです。
住宅ローンの審査では年収、借入時の年齢、健康状態の他、勤続年数も審査の対象になります。
勤続年数が1~3年では審査の対象にはならない銀行もあります。
審査中は在籍確認もあります。審査中に転職活動をしていくことが伝わると、ローンが通りにくくなる、借入の金額が下がる、連帯保証人が必要になるなどローンを組むことが難しくなります。
転職活動を開始するのは本審査も終わり、住宅ローンの手続きが済んだ後が良いでしょう。資格取得前と取得後
資格には受験資格に制限のない誰でも受験できるものから、就業年数など受験への規定を求めるものもあります。
国家資格などは予備校もあるので、退職して資格試験に集中できる環境を選ぶという選択肢もあります。
しかし、評価される資格ほど取得難易度は高く、合格までどれだけ時間がかかるかは不明です。そのブランクが今後の転職活動で不利になってしまうこともあります。
もし在職中であるならば、現在の仕事と並行して資格を取得することをおすすめします。職歴にブランクを作ることなく、収入を確保しながら効率よく転職の準備ができます。
実務に結び付く資格を選び、キャリアアップの武器にしましょう。ボーナスをもらう前・もらった後
転職をするタイミングは、ボーナスを貰った後が一般的です。
転職後の年収がダウンすることがわかっている場合や、転職に伴う引っ越しなどの出費が見込まれることもあるからです。
ただし、転職1年目でもボーナスを支給する会社も多くあります。
転職後に年収が上がる予定ならば、早めに転職し、ボーナスの計算対象期間中に在籍実績をつくり、次の会社でボーナスをもらいましょう。
受給資格と内容を、就業規則や求人要綱からしっかり確認をして、前職のボーナスをもらうのと、次の会社でもらうののどちらが得をするのか考えて転職時期を見極めましょう。出産の前・後
出産後の働き方を見直す為に、出産を期に転職する人もいるでしょう。出産の前後どちらで転職するべきかは、正解がなく産休や育休、復帰などの制度について確認して自分に合う選択をしましょう。
出産後に転職をする場合、これまで努めてきた会社で産休・育休の取得、復職ができるため不安材料が少ないというメリットがあります。
これまで共に働いてきた親しい仲間がいる環境であればフォローも受けやすいでしょう。
しかし、出産後の転職は育児と同時進行になりますし、時間や条件面で転職活動が思うように進まない可能性もあります。
出産を見越して転職するならば、転職先の育児休暇制度の条件などをしっかり確認しておきましょう。
申請には就業後1年以上の在職期間と、子供が1歳6カ月になる日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないなどの条件を満たす必要があります。
入社1年未満でも育休を取れる会社もありますが、該当する企業は少ないでしょう。
出産前の転職であれば、転職活動の期間や新たな環境や仕事内容に慣れるための期間も必要になります。その為想定していた時期よりも出産が先延ばしになる可能性も考えられます。
-
転職のタイミングに関するその他のよくある質問
-
 このほかに転職についてよく聞かれる疑問は以下のものがあります。
このほかに転職についてよく聞かれる疑問は以下のものがあります。1年で転職に適したタイミングは何月?
先に紹介した通り、ボーナスの時期や四半期など転職で人が動きやすい時期はありますが、企業によって人材が必要になるタイミングは異なるので、年間でいつが良いかということにはあまりこだわる必要はないでしょう。
ただし、2月~3月、8月~9月は、組織編成を見こして求人が増える傾向にあります。
中途採用などは入社時期も人によって異なることが一般的ですし、求人も不定期に発生します。
自分の業界・職種の動きと、希望条件に合わせ、いつでも応募できるようにこまめに求人情報のチェックを続けましょう。また職務経歴書の作成なども準備しておくと、希望の求人がでたときスムーズに活動を開始できます。社会人何年目からの転職がおすすめ?
キャリアアップを目的とする転職であれば5~6年目がおすすめです。
第二新卒ではまだキャリアが足りない場合がありますが、5年~6年であればキャリアアップに好意的に採用される可能性は十分にあります。
未経験の業界や職種への転職を考える場合は第二新卒での採用枠を狙ったり、まだ若くポテンシャル採用の見こみのある3~4年目がよいでしょう。
年齢が上がれば不利になると思われがちですが、実績と目的、企業側とのマッチングが合えば、30代、40代での転職も十分可能性があると言えます。新型コロナウイルスの影響で今は転職タイミングではない?
コロナ禍から経営悪化のニュースなどがみられ、慎重になった方も多いでしょう。
しかし逆にいえば、大きく影響を受けていない分野や新たな可能性がみられる業種・分野が明確になりました。
そのような活性化がみられる分野にむけて、キャリアの棚卸をして現在の情勢でアピールできる強みを示せられれば、大きなチャンスはあるでしょう。迷っていては時間だけが過ぎてしまいます。
現在はコロナ禍以前の水準に戻りつつありますし、転職活動において年齢は大きく影響します。転職を考えているのであれば新しい職場に求める条件・目標を明確にして、こまめにチェックと応募を続けましょう。
-
まとめ:転職のタイミングを見極めて新しいスタートを切ろう!
-
転職は年代やシチュエーションによって考慮すべきポイントが異なります。
それでも、いつでも新しい働き方、生き方への意欲が高まった時が転職を進めるベストタイミングです。新しいスタートを切るために、最善の方法を探しましょう!
バイトルNEXTにはさまざまな求人が掲載されているため自身に合う仕事を見つけらます。
自身の仕事探しの条件を明確にして、様々な求人から自分の理想に近い仕事を探してみましょう。【関連記事】
転職するか迷うときはどうする?転職のリスクや年代別転職ポイントを解説!
退職のタイミングはいつがいい?いつ申し出ればいいの?避けるべき時期やポイントとは
転職したいけど何したいかわからない場合は?そんな人のための転職活動解説!
転職が難しいのはなんで?年齢別の原因や女性にとっての難しいポイントも解説!
退職はいつまでに言うべき?意思表示をするタイミングや伝える際のポイントを解説!
30代・未経験での転職は厳しい?成功のポイントやおすすめ職種を紹介!
転職活動は働きながらできる?メリット・デメリットと働きながら転職するコツを紹介!
転職先の探し方6選!転職に向けてするべきことやホワイト企業を見つけるコツを紹介!
やりたい仕事がないとダメ?やりたい仕事が見つからない原因と見つけ方を解説!
やりたいことがないけど転職したい!解決のヒントや年代別の転職のポイントを紹介
社員の仕事探し・転職 の関連記事

アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説

製造業とは?就職・転職の検討に使える主な職種や仕事内容・メリット・デメリットなどの情報を解説!

建築・土木ってどんな仕事?仕事内容や現場の声、求人の探し方について紹介
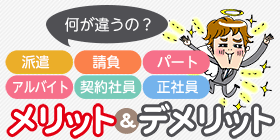
何が違うの?働き方の違いメリット&デメリット|派遣・請負・パート・アルバイト・正社員
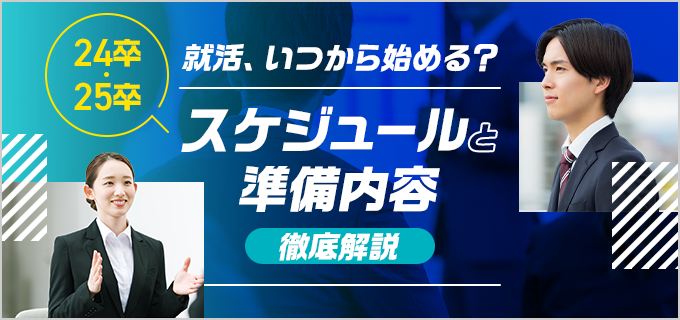
【24卒・25卒】就活はいつから?流れや準備時期を徹底解説

バイトルNEXT 適職診断
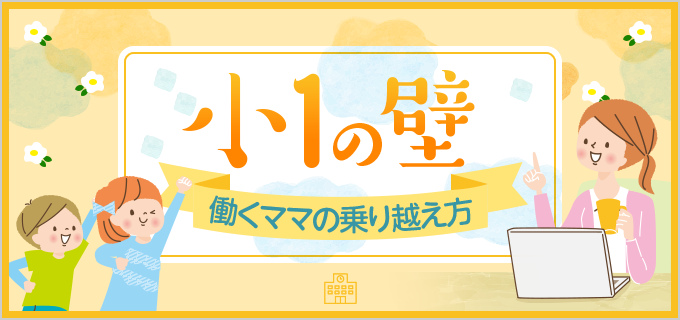
小1の壁を乗り越える!困るポイントと対策、働き方を解説
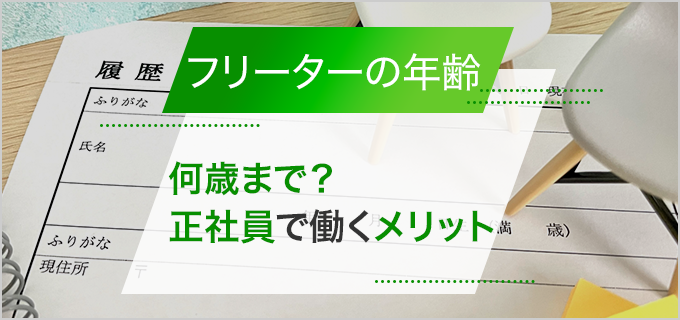
【アンケート】何歳までフリーターを続ける?就職はいつまでにするべき?

30代男性・スキルなしの正社員転職は難しい?おすすめの業種・職種10選を紹介!

ハローワークの求職活動って何をするの?簡単&効率的に認定を目指せる求職活動実績の作り方
カテゴリ一覧
-
派遣の仕事探し派遣の仕事探し
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書
- 自宅でできる仕事46選!スキルや趣味、得意分野を活かせる在宅ワークを見つけよう /バイト探し・パート探し
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート
- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!