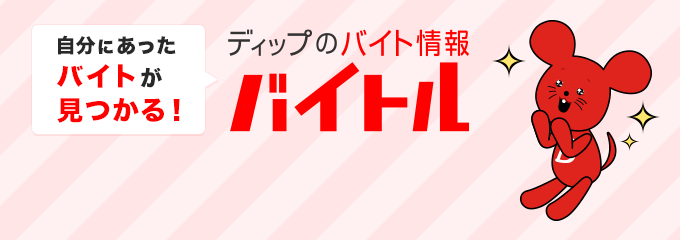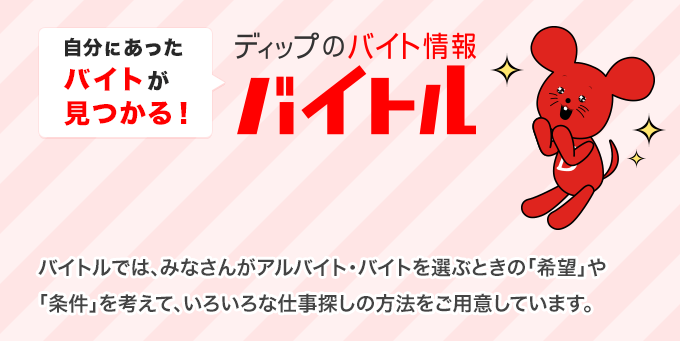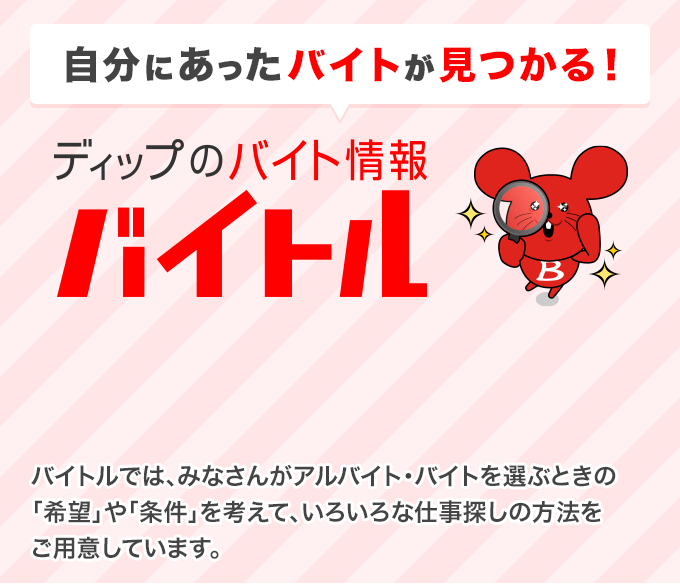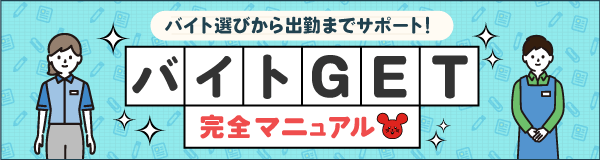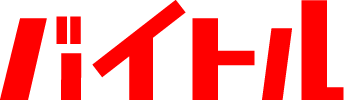「三々五々」とは?意味や使い方、言い換え表現を例文付きで解説!
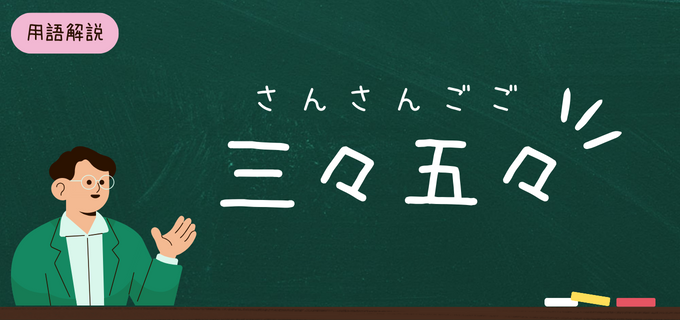
「三々五々」の読み方や意味を知っていますか?聞き馴染みがない方は検討もつかない言葉ではないでしょうか。また聞いたことがあっても、どのシチュエーションで使うかわからない人も多いでしょう。
本記事では「三々五々」の読み方・意味・由来などの基本情報から使うシーン、使う際の注意点に至るまでを丁寧に解説。また、類語や言い換え表現、反対語・対義語も紹介します。
目次
-
「三々五々」の読み方・意味・由来
-
「三々五々」の正しい読み方、語句の意味、由来について解説していきます。
「三々五々」の読み方
「三々五々」は「さんさんごご」と読みます。
「三三五五」と表記されることもあります。「三々五々」の意味
「三々五々」の意味を辞書で引いてみました。デジタル大辞泉には、以下のように書かれています。
■「三々五々」の意味
三人、五人というような小人数のまとまりになって、それぞれ行動するさま。
(参考:デジタル大辞泉)「三々五々」の由来
「三々五々」は中国の盛唐期の詩人、李白の漢詩『採蓮曲』に由来するという説があります。
「三三五五映垂楊(さんさんごごすいようにえいず)」という詩の一節は、三人五人が枝垂れ柳の影にちらほらと見え隠れしているという意味です。この様子を「三三五五」と表現し、それが後に「三々五々」として日常用語に取り入れられたとされています。
他にも「あちらこちらに散らばること」を意味する漢語表現の「三五」からきている説もあり、「三五」を繰り返した熟語が「三三五五」となり、一般的に「三々五々」と書くようになったとされています。
-
「三々五々」を使うシーン
-
「三々五々」を使うシーンには以下のようなものがあります。
■「三々五々」を使うシーン
- 1. 集合や解散の際
例えば、会社の飲み会やイベントが終わった後、参加者が一斉にではなく、少しずつ帰っていく様子。 - 2. 人々が散らばっている風景
公園やビーチなどの広い場所で、人々がグループごとにまばらに散らばっている光景。
- 1. 集合や解散の際
-
「三々五々」は副詞
-
「三々五々」は形容詞ではなく副詞です。
「三々五々」という言葉は、人々の動きや行動の様子を説明する際に使用されます。例えば「人々が公園に三々五々集まる」という文では、「三々五々」という部分が「集まる」という動詞を修飾して、人々がどのように集まるか(ばらばらに、少しずつ)を表しています。
副詞のため「三々五々に」「三々五々と」のように後ろに「に」などを付けるのは厳密には誤りです。【補足】
- 形容詞
形容詞は名詞を修飾します。つまり、物や人の性質、特徴を表す言葉です。
例えば、「青い空」の「青い」は空の色を表しています。 - 副詞
副詞は動詞、形容詞、他の副詞、または文全体を修飾します。
例えば、「とても速く走る」の「とても速く」は走る動作の様子を表しています。
- 形容詞
-
「三々五々」を使った例文
-
このセクションでは、「三々五々」という表現の使用例を紹介していきます。日常生活の中でこの表現をどのように活用できるか、具体的なシーンを通して理解を深めましょう。
【例文】
「週末の午後、カフェには客が三々五々集まり、それぞれがコーヒーを楽しんでいた。」
「レストランでは、友人たちが三々五々到着し、にぎやかな夕食会が始まった。」
「美術館の庭園では、訪問者が三々五々散策しており、穏やかな午後を過ごしていた。」
「夏祭りが終わり、人々は三々五々、帰宅の途についた。」
「パーティーが終了し、ゲストは会場から三々五々出て行った。」例文を通して「三々五々」が意味する「小人数のまとまりになって、それぞれ行動するさま。」の理解は深まったでしょうか。
-
「三々五々」を使う場合のポイント
-
以下のポイントを意識し「三々五々」という言葉を適切に使いましょう。
自然な動きを表す場合に適している
人々が自然に、無理なく動いている様子を表現したいときに適しています。
集まりや解散のシーンで効果的
人々が集合したり、散ったりするシーンで使うと、その流動的な動きがよく表現できます。
少人数のグループを想像させる
「三々五々」は少数の人々がバラバラに行動している様子を連想させます。大勢が一斉に動く場面には適していません。
「三々五々」は四字熟語ではない
「三々五々」は副詞であり、四字熟語ではありません。四字熟語は漢字4文字で成り立っており、各文字が独立した意味を持ちつつ、合わせて一つの意味や概念を表します。
一方で、「三々五々」は「三」と「五」を繰り返しており漢字4文字ではないため、伝統的な四字熟語の定義には当てはまりません。「三々五々」は比喩表現として使われることもある
「三々五々」はその文字通りの意味に限らず、比喩的な使い方をされることもあります。この表現は、文字どおりに人々がばらばらに集まる様子を描写するだけでなく、より広い意味で「事物が散在している」という状況を表すのにも使われます。
例えば、考えや意見がまとまらず、多方面に散らばっている状況を「三々五々の意見」と表現することができます。「三五」だと相手に意味が伝わらない可能性がある
「三々五々」を略して「三五」と言うことがあります。しかし、「三々五々」の方が一般的な表現のため、「三五」だと相手に意味が伝わりにくくなる可能性があります。
「三五」と略さずに「三々五々」を使う方が良いでしょう。
-
三々五々の類語・言い換え表現
-
以下の表現も「三々五々」に似た意味を持ち、少数の人や物がばらばら、あるいは断続的に存在している状況を表現するのに使用されます。文脈やニュアンスによって、表現を使い分けると良いでしょう。
【「三々五々」の言い換え表現】
- 三三両両/三々両々(さんさんりょうりょう)
- ちらほらと
- ちらちらと
- ぽつぽつと
- ぱらぱらと
- ばらばらと
- 点々と
- まばらに
-
三々五々の反対語・対義語
-
「三々五々」は、散在する様子や少数がばらばらにいる様子を表す言葉です。それに対する反対語や対義語は、集団が密集しているか一斉に行動している状態を指します。
以下に「三々五々」の反対語・対義語をいくつか紹介します。【「三々五々」の反対語・対義語】
- 一同に
- 一斉に
- 一丸となって
- 勢ぞろい
- びっしりと
- ぎっしりと
- どっさりと
-
まとめ
-
- 「三々五々」は「さんさんごご」と読む
- 「三々五々」の意味は、三人、五人というような小人数のまとまりになって、それぞれ行動するさま
- 「三々五々」は中国の盛唐期の詩人、李白の漢詩『採蓮曲』に由来するという説がある
- 「三々五々」を使うシーンには、集合や解散の際や人々が散らばっている風景など
- 「三々五々」は形容詞ではなく副詞
- 「三々五々」の言い換え表現は「ちらほらと」「ぽつぽつと」などがある
本記事では「三々五々」について、その読み方、意味、由来から使い方を幅広く解説しました。
「三々五々」は人々が少人数のまとまりになって、ばらばらに集まる様子や散る様子を表現するのに適した言葉です。
この言葉の使い方や注意点についても触れましたので、日常会話や書き言葉で活用する際にはこれらのポイントを参考にしてください。【あわせて読みたい】
ビジネス用語「フィックス(fix)」とは?業界ごとに違う意味や使い方をご紹介
ビジネスで活かす「ご尽力」の正しい使い方とは?意味と言い換え表現、例文も紹介
「鑑みる」の意味とは?ビジネスシーンでの使い方、類語を紹介!
例文あり!「周知」の意味とは?ビジネスでの使い方や類語・誤用表現も詳しく解説
自己研鑽とは?ビジネスや就職・転職のアピールにも使える例文と自分磨きのコツを解説
ビジネスシーンで使える「気をつける」の言い方は?意味や使い方、丁寧な言い換え表現を紹介
「恐縮」の使い方完全ガイド!意味・使い方・言い換え表現を例文と併せて丁寧に解説
「よろしくお伝えください」は目上の人に使える?意味や返答・使い方【例文付き】
「とんでもないです」を徹底解説!意味・使い方・言い換え表現を例文と併せて丁寧に説明!
「感慨深い」の意味とは?感慨深い気持ちになる瞬間や正しい使い方を例文付きでご紹介
「往々にして」の意味と使い方を例文付きで解説!ビジネスで使える敬語表現も
「づつ」と「ずつ」どっちが正しい?意味や例文・使い分けのポイントを解説
目上の人に『お大事に』を伝える敬語表現とは?類語やメールでの返答例文も紹介!
「~以降」はどこまで含まれる?意味と使い方を紹介!
「痛み入ります」の意味とは?例文や言い換え表現、返答など、ビジネスにも活かせる使い方を解説!
「お陰様で」は目上の人に使える敬語?正しい意味と使い方を例文付きでご紹介!
「ワンオペ」とは?バイトや育児などで起こる問題とそれを乗り越えるコツ
「シュール」の意味って何?意味や語源・使い方を分かりやすく解説!
大学生必見!GPAとは?計算方法や平均値・就活における重要性を解説
【やり方解説】ブロ解とは?なぜブロ解するのか・ブロ解するとどうなるのかをご紹介
就業・勤務 の関連記事
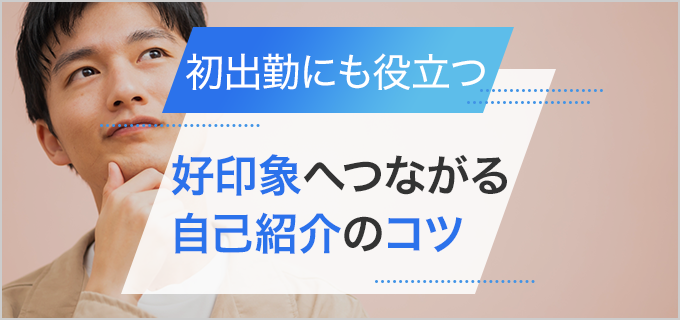
自己紹介|新しい人間関係のスタートで好印象を目指すためのアドバイスと例文

正社員じゃないからムリ?パートなら覚えておきたい産休・育休のあれこれ

バイト敬語要注意!アルバイトするなら正しい敬語を覚えよう

バイトなのに寝坊した!アルバイトに遅刻してしまったときのベストな行動

バイトのシフト入りすぎ?アルバイトに疲れたときの対処法とは?
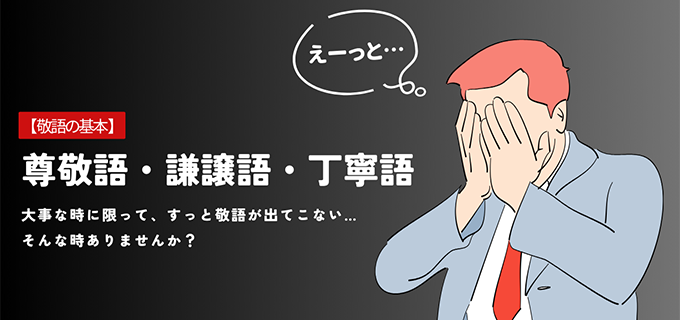
【敬語変換表あり】尊敬語・謙譲語・丁寧語の基礎
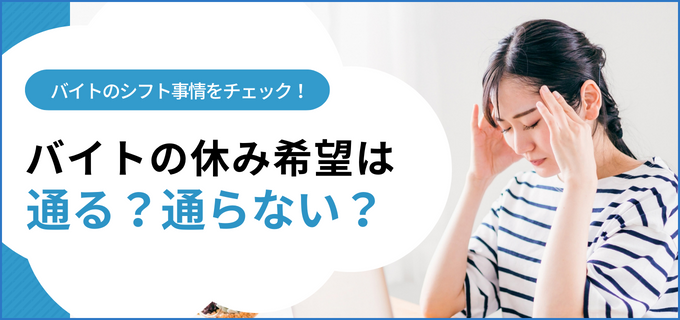
アルバイトのシフト事情!休み希望は通る?通らない?

意思の疎通が苦手な人必見!コミュニケーション能力向上のポイント

バイトに早く慣れるには?アルバイト先の先輩と早く仲良くなろう!
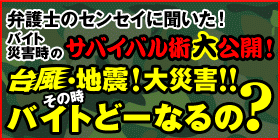
台風・地震!大災害!!その時バイトどーなるの?
カテゴリ一覧
-
派遣の仕事探し派遣の仕事探し
-
dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト
-
dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト
-
退職・辞め方退職・辞め方
-
フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集
仕事記事 ランキング
- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律
- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律
- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律
- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接
- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し
- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律
- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接
- アルバイトとパートの違いとは?法律や働き方、待遇を解説 /社員の仕事探し・転職
- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書
- 自宅でできる仕事46選!スキルや趣味、得意分野を活かせる在宅ワークを見つけよう /バイト探し・パート探し
エンタメ記事 ランキング
- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち
- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち
- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち
- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート
- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート
- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち
- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート
- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート
- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート
- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!